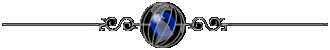|
『暗いニュースが続く中、なんともワクワクするニュースが届きました。
世界的に著名なアマチュアコメット・ハンター……氏により、新たな彗星が発見されました。この彗星は地球から…………、離れ、大きさは…………。
この彗星は、地球から三週間程度観測することができ、10月27日から11月2日ごろまでは一般的な双眼鏡でも見ることができるということです。最接近は10月31日で、午後7時から午後9時にかけてが天気も良く、見ごろだということです。
さて次のニュースです……』
そんなニュースが10月初頭から伝えられ、久方ぶりの大彗星の話題に地球の人々は双眼鏡や天体望遠鏡を買い求め始めた。毎日のように特集が組まれ、そのためにわか日曜天文家が大量発生し、みんながその運命の日に彗星が眺められるように、と特集を参考に空の見上げ方を練習し始めた。
だがそれも10月が中旬をすぎ、下旬に入りかけると下火になってきた。何故か?
そう、10月31日には毎年恒例の、あのイベントがあるのだ。
その準備に追われて、人々は彗星のことを後回しにするようになった……。
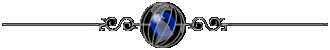
「えっ、ハロウィンパーティーやるの?!」
そう、奇しくも10月31日は万聖祭の前夜祭である“ハロウィン”なのである。
ケルト人の大晦日の祭事に起源を持つこのイベントは、キリスト教が世界の一部を支配するようになるとキリスト教用に再編成され、長く生き延びることとなった。
近年では宗教的な祭事と言うよりは街をあげた仮装大会という様相を呈してきたハロウィンではあるが、その楽しさのために子どもはもちろん大人にも世界中で愛されている。
それは、欧州のとある国の海に面したとある大学都市でも変わらなかった。
大学が創建された300年前から発展し始めた、古い町並みと石畳の道路を多く残すこの街の若者たちももちろんハロウィンを心待ちにして、その準備に追われているのである。
「そうそう、ハロウィンパーティー!マイクの家でやるんだけど、どうかなと思って」
「マイクの妹の友達も来るっていうんだけどさ、どうせなら人数多いほうが楽しいだろ?」
大学都市の名に相応しく、街の象徴となっている大学のとある講義棟のとある教室。講義が終わった後、三人の男女が居残りなにやら話をしている。一人は男で、二人は女だ。
今日は10月29日、彗星が双眼鏡で見えるようになって二日目だった。
「ハロウィンって……彗星の最接近の日じゃない。観測レポートはどうするの?」
机の端に腰掛けた男子学生と、その隣に立っている栗毛のセミロングの女子学生はその言葉に顔を見合わせる。口を開いたのは男子学生だった。
「そんなの、ちゃちゃっと終わらせちまえばいいし。ていうか、一週間のうち一晩分だけでいいんだろ?だったら一日でもいいじゃねーか?」
男子学生の言葉に栗毛の女子学生がかくかくと頷く。
「本当は今日か明日やってしまえばいいんだろうけど、ハロウィン前は準備したいし、明日は大学主催の観測会のボランティアがあるでしょう?だから、一日に皆でやろうかって言ってたの。共同レポートでもいいって先生言ってたから、ね?」
すると、残りの一人のブルネットの髪を背中の半ばまで伸ばして椅子に腰掛けている女子学生は不満そうな声を出した。
「でも、観測に適してるのは31日だと思うわ」
「真面目だなー、アンナマリアは。だったら、31日はマイクんちから彗星見ようぜ。
んで、パーティーもするんだ。レポート用の観測は1日ってことで」
男子学生がからからと笑って言うと、アンナマリアと呼ばれたブルネットの学生はますます不満そうな顔になった。
「レポートはともかくとして、マイクの家は街の真ん中じゃない。明るすぎるわ。観測には不適当な環境よ」
すると、栗毛の学生が不安そうな声を出した。
「マリー、ハロウィンパーティー出たくない?」
アンナマリアは困ったような、怒ったような顔で栗毛の友達を見た。
「ミリアム、そうじゃないけど……私たち、天文学専攻なのよ?」
天文学専攻、と言う言葉に残りの二人は顔を見合わせた。
そう、この三人は――男子学生の名前はシェーン、栗毛はミリアム、ブルネットはアンナマリアと言った――この大学の理学部地球宇宙物理学科の天文学専攻の学生であった。
つまり、久方ぶりの大彗星の接近というのは彼らにとって一般的な「一生にあるかないかの大イベント」ではなく「専攻分野に関係する(かもしれない)貴重な学問的体験」であるのだ。
ちなみに先ほどから名前が出ているマイクというもう一人の男子学生は、文学部歴史地理学科の学生でシェーンの友人だ。今回のハロウィンパーティーはそのマイクの主催だ。マイクはもちろん天文学専攻ではないので、31日の最接近日をそれほど重視していなくとも仕方のないことだった。
「彗星は一週間見れるけど、今年のハロウィンは一回だけなんだぜ?」
けれど、シェーンとミリアムはそういう結論になったらしい。アンナマリアは少々がっかりしていた。
「私ね、マリー用の仮装も作ったの。魔女と黒猫、どっちがいい?ほら、私たちってサイズ一緒でしょ、だから……」
「行かない」
「「えっ」」
ぶすっとしたアンナマリアの応えに、二人は素っ頓狂な声を出した。
「私、もう27日からいい場所見つけて観測記録とってるの。31日だけないってことにはしたくないから、行かないわ」
「えっと……マリー?」
シェーンがなだめるような声を出した。ミリアムは哀しげだ。
「行かないわ」
だがアンナマリアの声は頑なだった。そう言い切ると、音を立てて立ち上がる。
「そういうわけだから、そろそろ私帰るね」
「マリー!」
ミリアムが叫ぶような声を出したが、アンナマリアは肩で風を切って教室を出て行ってしまった。
開けられたドアがゆっくりと閉まる様子を、残された二人は複雑そうな視線で見ていた。
「シェーンが上手な誘い方しないからよ」
「オレの所為かい!……せっかく、元気付けるいい機会かと思ったのにな」
「“事件”からもう三ヶ月は経ったけど、やっぱり元にはもうもどらないのかな……」
「頑なになっちまったよな……」
二人は深く深くため息をついて、ぱたんとひとりでに閉まったドアを見つめた。
|