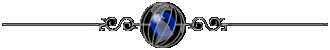|
青くて綺麗な海の上 白波ぶつかる崖の上 落ちたらおさらば崖の上
立派なお屋敷あるでしょう 伯爵さまが住んでるよ 何百年も住んでるよ
不思議不思議さお屋敷の 伯爵さまはひとりきり
前にも後にもひとりきり 親もなければ子もいない
何百年もひとりきり 屋敷のご主人 ひとりっきり
何百年も住んでるよ お館さまは 吸血鬼 伯爵さまは 吸血鬼
青くて綺麗な海の上 白波ぶつかる崖の上 落ちたらおさらば崖の上
立派なお屋敷あるでしょう お館さまは 吸血鬼
(とある街のわらべ歌)
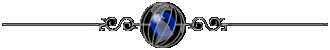
古ぼけて重そうな石造りの外観を持つ大学の第3講義棟を出て、若者たちがたむろする芝生の広場を突っ切り、警備員が常駐する白い石の門をくぐる。すると、「大学前」のバス停がある。アンナマリアはちょうどそこへ来たバスに乗り込み、海に近い郊外を目指す。
バスは、250年ほどまえに敷き詰められてその後取り替えられながら使い続けられている石畳の街のメインストリートをのんびりと走っていく。四角いドイツ車がバスとすれ違った。
バスの車窓からは、彼女のお気に入りのイタリアン・レストランが見える。その隣の傾きかけた建物に入っているCDショップのチャート上位には今週もUKロックが入っていた。
世界で進むグローバル化の象徴のような光景だった。だがどちらの建物もやはり石造りで、築100年はゆうに越しているだろう。
古い景色を残しながら、この街とその象徴の大学は世界と新しい文化を受け入れているのだ。
バスはのんびりと海に近い郊外を目指す。アンナマリアは見るともなしに古いものと新しいものが交じり合う街並みを見ていた。
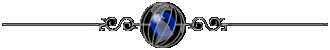
さて、街の外観以外にこの街が持ち続けている古いものがもう一つあった。
開発の及ばない郊外にそれはある。ほぼ直角に海に面する断崖の上にある、石造りの大きな屋敷――それがその“古いもの”の舞台だった。
実際屋敷自体も古く、300年前にできた大学より、その前にあった街の前身の小さな村よりも前からあるのだ、という老人もいる。
もう一つの古いもの、それはこの屋敷に関する言い伝えだ――それはこの屋敷には吸血鬼が住んでいる、という伝説である。
屋敷には伯爵と呼ばれる吸血鬼――ただし有名なドラキュラ伯爵とは別人――が住んでおり、実は街を影から支配しているとの伝説がこの屋敷にはあるのだ。
街の一番はずれにあり、海からそそり立つ断崖に程近いバス停から、ひょろひょろした舗装されていない道が伸びていることを街の人は知っている。
だが、多くの人はバス停から先へとその道を辿ることはほとんどない――なぜならこの道はその不気味な伝説を持つ屋敷へと続いているのだ。今はちょうど夕暮れ時で、オレンジ色の夕暮れの中、少し遠くから波が崖にぶつかる音が聞こえる。
アンナマリアはそんな中、その人気のない舗装されていない道の上を歩いていた。
トートバックがなぜか重く感じられる。アンナマリアは肩からずり落ちかけていたトートバックを立ち止まって肩に掛けなおすとまた歩きだした。
彼女はその道を通ってどこに行こうというのか。
やはり道の先には、黒い石造りの、立派な城壁をめぐらせた城のような――吸血鬼がいるという伝説を持つ屋敷しかない。アンナマリアは舗装されていない道をとぼとぼ歩いて、そこを目指しているのだ。
アンナマリアはやがて屋敷の入り口の門に辿りついた。鉄製の門は黒い石造りの城壁のような塀にしっかりと収まっている。乗用車どころか、丈高い馬車さえも楽々と通すことができそうな大きさの門だ。しかし彼女はそちらの門には目もくれず、その脇にある小さな通用口のような門をくぐった。
城壁の向こうには、薬草園が広がっていた――伝説やわらべ歌からはまるでこの屋敷は廃墟になってしまったかのような暗い印象を受けるが、そうではないのだ。
ここには人の出入りがあり、屋敷と庭は隅々まで手入れがしてある。潮風が吹いてきて、緑の草たちが揺れた。この屋敷の主は鑑賞するだけの花よりも、役に立つ薬草を好むのだ。
しばらく広大な薬草園を歩くと、やっと屋敷の玄関が見えてくる。アンナマリアはほっとため息をついて、ドアのノッカーに手を伸ばした。
ゴン、ゴン、ゴン。
三度ノッカーでドアを叩いてしばらく待つ。すると、ドアがようやっと開いた。
「お帰りなさいませ、アンナマリアさま」
「ただいまもどりました、ダドリーさん」
ドアを開けたのは白髪と揃いのひげを蓄えた紳士だった。アンナマリアはじつはこの“帰り方”にまだ慣れない。自分でドアを開けて家に入ることを注意されて三ヶ月――ここは彼女がずっと暮らしてきた家ではないのだ。
ダドリーと言われた老紳士はこの屋敷の執事だ。いつもにっこりとして彼女を迎えてくれる。ほっとすることもあれば、こっそりと部屋にたどり着きたいと思うこともある。
ダドリーに先導されて、屋敷の廊下を進む。
廊下の左右には歴史上の偉人たちの胸像が並ぶ――カエサル、アウグストゥス、その妻リウィア、ティベリウス――カリグラの像はなく、次はクラウディウス、ネロ、かわいそうなオクタウィア、アグリッピナ――――まずは古代の帝国の偉人・変人・悪人たち。
それから、名もわからぬ人々の像。
夜になれば少し不気味に感じられる空間だが、アンナマリアは慣れ始めていた。
ダドリーがとある部屋のドアの前で立ち止まった。
「ご主人様は今晩もどっていらっしゃいます。しばらくはリビングでおくつろぎください」
そう言って、彼女のためにドアを開ける。ドアの向こうの“リビング”と言われた部屋は呆れるほど広かった。
ソファーとテーブルのフルセットが部屋の右手の暖炉の前と、左手のオーディオセットとテレビの前に一つずつ。それでも、全く狭いとは感じさせない空間だった。美しい工芸が施してある食器棚には、マイセンのティーセットが飾りつけてある。しかもこのマイセンは最近作られた新作ではなく、目玉が飛び出るほど高いアンティークなのだ――じつをいえば、ここの屋敷にある物はほとんどがアンティークと言えるものなのだが。ここの主は平気でこれらのアンティークを使う。そして時折壊すが、気にしない。
アンナマリアはそんな空間で過ごすようになって三ヶ月になるが、やはりまだアンティークを使うことには緊張する。一生慣れることもないだろうが。
アンナマリアは暖炉の方の三人掛けのソファにトートバッグを置いた。そして目の前にあるマントルピースを見つめる。これもとんでもない年代物で、複雑な意匠を施してあり、そしてその中には、もう薪がつんである。ハロウィンが終わったら、冬が来るのだ――アンナマリアは漠然と思った。
そこへ、ひゅっと冷たい風が吹いて彼女のうなじを撫でた。アンナマリアはぶるりと怖気に身を震わせてからそっと振り返った。ドアが開いた気配はしなかった。振り返ると、部屋の入り口近くに一人の男がいた。見知った男の姿に、アンナマリアはほっと息をつく。
男は奇妙なことに、全身をシルクサテンの黒いマントで覆っている。歳は若くて30代前半、遅くても40代と言ったところだが、どこか年齢不詳な印象を受ける。印象的な闇より黒い髪は丁寧に後ろへ撫で付けてあった。
そして何よりも彼を印象付けるのは、どんな美女よりも美しい顔立ちだった。肌はすける様に白く、目鼻ははっきりとしており、海よりも空よりも深い青をした瞳はどこか物憂げだ。
彼はマントの下から右腕を出すと、首元で止めてあるリボンを解いた。するりとマントが優雅に床に落ちる。
マントの下に彼は黒いスーツを着ていた。
そのスーツ越しに彼の体つきは、どんな男性モデルや俳優よりも美しいのではないかと思わされる。――背は高いが、体は太くもなければ細くもなく、長い足は優雅に体重を支えている。指も手もまるで古典古代の彫刻から取り出したような美しい形をしていた。
アンナマリアは、彼はどこかの女ピグマリオンが作り出し女神によって生命を与えられた美しい大理石の彫刻ではないかと思うことがあった。
そんな彼女の視線に気づいたのか男は床に落ちたマントから目を上げて、視線をアンナマリアにあてた。
そしてにっこりと笑う――笑った瞬間、口からわずか、人のものにしては長すぎる犬歯が覗いた。
「お帰り、天文の女神」
アンナマリアはため息をついて額を押さえた。
「私はウラニアなんかじゃありません――伯爵もお帰りなさい、早かったですね」
「冬が近づくと日の出ていない時間が増えるからね――」
アンナマリアが伯爵と呼んだ彼が、まさしくこの屋敷の主だった。
ドアが開いた気配をさせず、冷たい空気と共に部屋に入り、美しい容姿と長い犬歯を持ったこの屋敷の主――彼こそが、わらべ歌や伝説に詠われた吸血鬼その人であった。
|