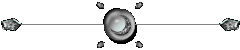|
伯爵の書斎と寝室は地下にある。窓の作りようのない地下と言う場所は、日光アレルギーの伯爵には素晴らしい場所であった。
蛇足だが、伯爵の寝室にあるのは普通のベッドである。断じて断じて、古風な棺おけではない。ふかふかとした羽毛が彼をつつむのだ。ただし、ベッドそれ自体の大きさはは新婚夫婦が暴れても余りあるものであるが。
ついでに言えば、伯爵の書斎はいたって普通のもので――つまり、黒檀の机とすわり心地のいい椅子に、立派な年代物の本棚(中には羊皮紙や革装丁の本がずらりと並んでいる)や未だに現役のレコード・プレイヤーなどが並ぶだけで、恐ろしい拷問道具や血を溜める樽などはない。
伯爵が吸血鬼で、やはり地下にその居室を持つと聞いて期待した方には、拍子抜けの話かもしれないが。
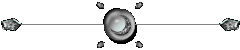
さて、ハロウィンから数日が過ぎたある日のこと。
なにやら壮大な世界観を持つクラシック音楽をかけつつ、伯爵は机のところで考え込んでいた。
書斎の机の上には、ノートパソコンが一台。これは美形ではあるが古風な佇まいをもつ伯爵と、その彼に相応しい書斎の雰囲気とは少々そぐわないものであるが、事実、伯爵はそのノートパソコンの画面を見つめ続けているのだから仕方あるまい。
伯爵は整えられた髪を撫でて、ため息をついた。
「やはりこのワイナリー、代替わりしてから全くダメだな……」
画面にはなにやら折れ線が映し出されている。みればそれは横の軸は月日の移り変わりに対応しており、縦の軸はなにやら数値の上がり下がりを示しているようだった。そしてその棒グラフは、ほぼ半年前から鰻上りならぬ鰻下がりをしていた。
それは、伯爵が懇意にしているワイナリーの株の変動を表すものだった。先代の代で株式会社となったこのワイナリーとは伯爵は百年以上の付き合いあった。超有名とはいかないものの堅実にワインを造り続けてきた一族で、本当のワイン通がひっそりとだが長く品を求めるようなワイナリーであった。元々伯爵は先々代のころからこのワイナリーに数本葡萄の木を持っていた。そして株式会社になると聞いたときには、個人としては一番にそれを買い求めたものだった。
だが、先代が亡くなりその息子が社長となって数年――そのワイナリーの評判が落ちてきたのだ。もともと、先代の社長と違って息子はあまり賢いとは言いがたい部類の人間であったことは知っていたが、それがワイナリーの経営にまで影響を与えるものだったとは、と伯爵は思う。
だが人間と違い、短い期間で利潤を求めない伯爵には多少株価かが落ちようが構わないことであった。しかし。
――このワイナリーもこの一族の手を離れるときなのかもしれんな。
株式会社となったからには、一族の長が愚か者であってもすぐにはだめにならずに、第三者――たとえばたたき上げの社員――が長となり立ち直ることがある。伯爵はそれを思いながら、画面を閉じた。先代までの苦労を思うとそのような変化は少し寂しい気もしたが、仕方あるまい。会社に限らず、国を背負うものであっても“交代”はあるのだ。それが伯爵の見てきた人間の世界だった。
室内に満ちる音楽は壮大なヴァイオリンの音色の大河に差し掛かっていた。
伯爵は椅子の背もたれにもたれかかり、その音楽に耳を浸しかけた――が、吸血鬼のするどい聴覚は、ぱたぱたバタバタと暴れる音を美しい音楽たちの向こうに捉えてしまった。
伯爵はアンティークの置時計に目をやった。ジャック・ルイ・ダヴィッドの『ホラティウス兄弟の誓い』を模した黄金の仕掛け時計は七時三十分を示している。
執事のダドリーや給仕頭のマーサーなど、住み込みの使用人以外の主要な働き手はすでに帰宅している。それに、使用人がこんな大きな音を立てるわけがない。ちなみにダドリーは昨日から風邪を引いている。
――と、くれば一人しかおるまい。
伯爵はため息をついた。
――ウラニアか。
彼が愛情をこめて天文の女神と呼ぶ人間の居候――アンナマリアという女子大生だ――はときおりそそっかしいところがある。きっとなにやらやらかして、二階に与えられた自室で慌てふためいているのだろう。
そして、その足音は彼女に与えられたスペースを飛び出した。
伯爵は――ああ、来るな――と思って待つ体勢になった。思ったとおり、数分後、書斎のドアがノックされた。
「入りたまえ」
言うと、がちゃりとやや乱暴にドアが開いた。
「伯爵、A4のコピー用紙持ってませんかっ?!」
ブルネットの髪をあっちへこっちへとバサつかせながら、飛び込むと同時にアンナマリアは言った。伯爵はことさらのんびりと答える。
「そこのチェストにないかな」
伯爵は入り口近くのチェストを示した。アンナマリアはきっとそれを睨みつける。
「ここですか?!」
「……下から三段目だ」
アンナマリアは見たこともない速さで屈みこむと、チェストの引き出しを引っ張り出した。
そして、中を見つめて一言。
「ありませんッ!」
「ではこの部屋にA4のコピー用紙は存在しないな」
すると、アンナマリアは引き出しを静かに元に戻し、頭を抱え込んだ。伯爵は首を傾げる。
「ウラニアよ、この世の終わりが来そうな顔をしてるが、何があったのだ?」
「私は天文の女神じゃありませんてば」
いつもどおりの応酬をした後、アンナマリアは深くため息をついた。
部屋に流れるオーケストラは彼女の心情を表すかのように劇的に変化していた。
「ほら、あったじゃないですか、彗星のレポート」
「思い出深い、あれだな」
「からかわないでください。それのレポートが書きあがったんです。提出は明日で」
「間に合うではないか」
「話は最後まで聞いてください。印刷しようと思って、紙を捜したんです。そしたら」
「なかったと」
「ええ」
偶然にも曲が終わり、つかの間の沈黙が部屋をつつんだ。数秒後、ノートパソコンのファンが動き出す音がした。
「……、大学にパソコンルームはないのかね」
伯爵が思い出したようにポツリと言うと、アンナマリアは一息で長い返答を寄越した。
「ええ、あります。しかしながら部屋の開放は1コマ目開始と同時刻からです。そして提出講義は見事1コマです」
「……五分ほど遅刻してみてはどうか」
「三年間すべての履修講義を無遅刻無欠席およびAマイナー以上で修得してきた私に今更遅刻をしろと?」
「……わたしが悪かった。許しておくれ」
一息にまくし立てるような口調で言ったアンナマリアに伯爵は必要のない降参をした。そして彼はこめかみを撫でる。
「……使用人控え室か倉庫に予備があるかも……しれん」
ちょっと自信無げに言った伯爵に、ばっとアンナマリアは顔を上げた。
「控え室と倉庫ですね!ありがとございます!!」
ばたばたと足音を立てていったアンナマリアに、伯爵はぼそりと言った。
「淑女の作法を教えねばならん……か?」
さらに三十分後――黄金の置時計は八時を示していた。
伯爵はノートパソコンを閉じ、レコードを変え、読書を楽しんでいた。
そこへ、弱々しいノックの音が響いた。どうぞ、と言うとこれまた弱々しくドアが開く。
顔を半分だけのぞかせて、アンナマリアが言った。
「B5とかしかありませんでした」
「ではこの屋敷にA4のコピー用紙は存在しないことになるな」
ずるずるとアンナマリアはその場にへたり込んだ。
「ああ、街の文房具屋はもう閉まってるし……どうしよう」
「コンビニは?」
「伯爵、あの24時間営業の“便利な”と言う意味を持ち世界的に普及している形態の店がなんでも売っていると思ったら大間違いです」
「……そうなのか」
郊外に吸血鬼屋敷を持つ、大学を中心に発展してきた海に程近いこの街は――不便なのか伝統的なのか、未だに商店街が現役で、しかも夜八時にはバーやレストランを除いて店仕舞いをしてしまうのだ。
へたり込んでぶつぶつと何かを言い続けているアンナマリアをしばし観察した後、伯爵はふむ、と言った。
「……たしか車で三十分のところに大型のモールがなかったかな?」
「……モール?」
伯爵の言葉に顔を上げたアンナマリアに、こっくりと彼は頷く。
「ほら、深夜までやっている大型のショッピングセンターだ。たしか、建設されるときにこの街からもだいぶ反対の声が上がったが……車で三十分もかかるとなると、日常的には皆近場で済ませているらしいからいつの間にかその声も止んだな。ただ、どこかの店主は週末の売り上げが減ったと言っていたが……」
「ああ、わすれてました……」
幾分拍子抜けした、だが落ち着いた声でアンナマリアは言った。
「そうだ、モールに行けば大体物は揃ってますもんね……。遅くまでやってるし、行ってきます」
「どうやって?」
伯爵が言った。今は夜。ここは郊外の吸血鬼の屋敷。もはやバスはない。
しかしアンナマリアは今度はめげなかった。
「私には自動車の運転免許があります!」
「ほう」
「なので、伯爵、車を貸してください」
アンナマリアが言うと、伯爵は意地の悪い笑みを浮かべて見せた。
「構わんが……貸すと言うことは、使用した分のガソリンは返してくれるのかね?あと、磨り減った分のタイヤだ」
その言葉に、ぐっとアンナマリアは詰まった。
「ガソリンは可能ですがタイヤはちょっと……」
「冗談だ」
くつくつ笑いながら彼が言うと、アンナマリアはやっぱりと言いつつ肩を落とした。
「しかし、夜道のドライブはいかがなものかな。ダドリーに車を出させたいところだが、生憎彼は風邪だしな。他の運転手も帰してしまった」
「大丈夫ですよ。免許取りたてじゃあないですし」
アンナマリアは胸を張って言った。
「じゃあ、ダドリーさんに鍵借りてきますね」
そう言って出て行った人間の娘の後姿を、吸血鬼は意味深長に見つめていた。
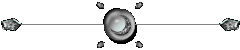
口元をマスクで覆ったダドリーがガレージまでついてきた。
「アンナマリア様……」
「ぶつけない様に気をつけますね」
ガレージにはいかにも、と言った感じの黒塗りの車が一台と、雪花石膏のように白いドイツ製クーペが一台。アンナマリアが貸してもらった鍵は白色のクーペのものだった。
「そのクーペは新車ですので……しかし、セダンの方はご主人様が公用で使いますので……ちょっと心配ですが……」
ダドリーは本当に心配そうだった。実は、アンナマリアは事件以来、つまり三ヶ月以上ハンドルを握っていない。
「すごく気をつけます……」
「わたしのおんぼろ車をお貸しできればよかったのですが、息子が乗っていってしまいまして……」
ごほごほとダドリーは咳をした。アンナマリアは二つのドアのうち、運転席側を開けた。
「うわっ!」
彼女の目にまず飛び込んできたのは、磨き上げられた本革のシートだった。そして、ハンドルなどのステアリングも揃いの黒い本革である。
センターコンソールは美しい銀色のパネルでAM/FMラジオはもちろん、CDプレーヤーにMDプレーヤーがついている。
それら内装は優雅な線を描き、静かな高級感をアンナマリアに見せ付けていた。
アンナマリアはスピードメーターさえもどこか優雅なので――デザインはレトロ風なのが拍車をかけている――しばらくそれらに圧倒されていたが、最後にあっと気づいて言った。
「でもテレビが付いてない!」
「必要ないからな。それに余所見の原因になる」
ダドリーではない落ち着いた声がして、アンナマリアは振り返った。そこには、ジーンズにカジュアル・ジャケットという珍しい格好をした伯爵がいた。明らかに先ほどまで着ていた部屋着ではない。その後ろには、マーサがすまし顔で控えている。
「伯爵、ジーンズなんて履くんですか……」
アイロンの効いたスラックス姿の伯爵しか見たことがないアンナマリアは目を丸くして言った。伯爵は腕を広げて見せた。
「可笑しいかな?」
アンナマリアは首を振った。足が長い彼は何でもよく似合う。みれば、靴は革靴のようだったがやはりこれもアンナマリアが見たことがないカジュアルなデザインのものだった。
「伯爵は何でもお似合いになりますし、何より私の見立てですからね!」
マーサが胸を張って言った。伯爵は慇懃に「ありがとうマーサ」と言った。
「それで……どうしたんです?」
アンナマリアが戸惑いながら聞くと、伯爵は笑って答えた。
「君一人では心配なのでね。それに、モールとやらも見てみたいしな」
「心配……って車がですか?」
アンナマリアが言うと、伯爵は顔をしかめた。
「幾度も買える物を心配してどうする?」
その返答に人間の平凡な娘は声も出なかった。マスクをしたダドリーが意味ありげに首を振る。その間に、伯爵は助手席側に回りこんでいた。
「運転はできんのでね――ウラニア、君を信頼しているよ」
金持ちの思考回路はわからない、とアンナマリアは思った。
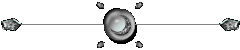
「二台あったほうが便利だというのでな。カタログを見て好みの形だったからコレにしたのだ。白いのを選んだのは、もう一台が黒かったからだ」
およそ吸血鬼に似つかわしくない美しいアラバスター色の車の中で、伯爵はあっけらかんと言ってみせた。
「でもクーペってはっきり言って誰かに運転してもらって乗るものじゃないですよ――本来伯爵が乗るべき後部座席は狭いですし」
伯爵は後部座席を肩越しに覗き込んだ。
「確かに兎小屋風だな」
「……もしかして、こっち乗ったことないんですか」
「君が来る少し前に買ったばかりでね」
アンナマリアはクラクションに頭突きをかましたくなる気持ちをぐっと堪えた。これは、ドイツ製高級クーペなのだ!
「アンナマリア、ちゃんと前を見たまえよ」
屋敷からの細い道を抜け、モールへと繋がる太い道路に出る。だがそこは大学のある街から外れているので、太くとも山の中、と言える道だった。ここから一山超えてトンネルを抜けると、新興住宅地が近くにあるモールに行けるのだ。
頼りになるのはヘッドライトと時折来る対向車の灯りだった。
アンナマリアが緊張しながら運転しているなかで、伯爵はなにやらセンターパネルをいじっている。
アンナマリアはぎょっとしつつ、伯爵に尋ねた。
「伯爵!この機械いじるの初めてですか?!」
「無論。」
「じゃあちょっと待って下さいよ!」
伯爵は極度の機械オンチで、以前パソコンのOSを何らかの方法で――未だに原因は不明だ――ふっとばしたことがあるのだ。しかも、OSがとんだだけなのに、アンナマリアが再セットアップしようとすると彼はどこからかそっと「余った」との言葉つきで一本ネジを差し出したのだ。
以来、彼女は伯爵が機械をいじるときに注意を怠らないようにしている。
「何したいんですか?」
「無音なのが気になってな」
車内は確かに外に似合いの不気味な静けさを孕んでいた。アンナマリアはほっと息をつく。
「私、カバンにCD入れてきたんです。それ聞きます?」
「それは準備がいいな」
「聞けると思ったんです。当たりでした」
伯爵は一旦シートベルトを外すと器用に体を捻って後部座席のアンナマリアのバッグに手を伸ばし、CDを取り出した。
女性アーティストのCDアルバムだ。
「リズム・アンド・ブルースか」
シートベルトを再び締めながら伯爵が言う。
「嫌いですか?」
「いや、音楽に嫌いな物はない」
そう言う伯爵の返答を聞いて、アンナマリアは彼がパンク・ロックを聴いているところを想像してちょっとぞっとした。美しい吸血鬼にはやはりクラシックが妥当だ。
伯爵がCDのケースを開ける。そしてCDを取り出し、センター・コンソールのプレーヤーと向き合った。
「そっと差し込むタイプですね……押し込まないで!」
ぐっと指先に力を入れかけた伯爵に気づいて、アンナマリアは少し語気を強くしていった。
しかし伯爵はそれを気にした風もなく、彼女の指示に従った。
起動音がしてCDが飲み込まれた。そして、賢い車が彼にしかわからない譜面を解読している音がした。
やがて車内から無音が去り、ハスキーな女声で満たされ始める。
「いい声だ」
伯爵は静かに感想を述べた。
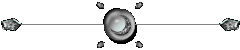
やがて道の先が一斉に明るくなりだした。道の左右にレストランが並び始める。
「もうすぐです」
道の左右にある店は、モールにつられてやってきたものたちばかりだ。つい数年前まで、ここが何もないただの広い草地だったとは誰も思うまい。
窓の外を眺めていた伯爵が窓のわずかなスペースに肘を付いた。
「人工的な空間だな」
アンナマリアは左折のためにウィンカーを動かした。白いクーペの目指す先には、外見的にはお世辞にも芸術的とはいえない巨大な箱と、白い線で長方形が描かれたアスファルトの広大な大地が待っていた。
|