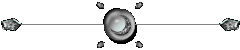|
「あった!」
夜でも昼並に明るい――伯爵はその明るさを不気味だと評したが――ショッビング・モール内。
その、家電製品売り場の一角にて、アンナマリアは目的のA4コピー用紙を手に入れた。
「……二束くらい買っておこう……」
そう言って商品ラックの前で中腰になっている彼女の隣で伯爵は辺りを見回していた。
「ものすごい物の量だな。入っている店の数も商店街並だ」
「なんとなく商店街の人が反対したの、わかりますよね」
「そうだな」
アンナマリアは二束のA4のコピー用紙を大事そうに胸に抱えると、伯爵に言った。
「伯爵、何か見たいのあります?」
「そもそも何があるのかわからんな。適当に歩かせてくれれば幸いだ」
「それじゃあ、まず、コレ買ってきます」
駆け出しかけたアンナマリアを伯爵が引き止めた。そして彼は、ひょいと彼女から紙の束を取り上げた。
「他にほしい物は?」
「えっ……特にないですが……」
「そうか」
すると、彼はすたすた歩きだした。慌ててアンナマリアが後を追うと、彼は彼女に確認してきた。
「こういう店では釣りはいらないというと迷惑なのだよな?」
「え、ええ……あの、伯爵?」
伯爵はアンナマリアが疑問符付きで呼びかけてきたのに気づいただろうが、無視した。
そして空いているレジにたどり着くと、ひょいとそれを台に置く。そして見慣れた光景に伯爵は取り込まれた。
伯爵はレジ係が合計を告げると、ジーンズのポケットから財布を取り出した。そして代金を支払い、釣銭を受け取る。
会計は滞りなく終わった。
そして伯爵は気にした風もなく、コピー用紙二束が収まった半透明のビニール袋を下げている。
「あの、伯爵お金……」
「若い者が金のことなど心配する必要はない」
有無を言わさぬ口調にアンナマリアは頭が下がった。
「あの、ありがとうございます……」
「なに、勉強に必要なものなのだろう?」
今度は打って変わってにこやかな口調だった。
「そういえば、外付けのなんとかも欲しいと先日言っていたな。ここにはないのか?」
「あ、外付けハードディスクですか?」
「そう、それだ」
「ここより別なところの方が安いんです……って、結構ですから!」
そう言ってアンナマリアは伯爵が持っているレジ袋に飛びついた。
「あの、これも私持てますから」
「いや、レディに物を持たせてはいかん。なんなら君のバックも持つが?」
「いえあの、わたしが嫌なのでレジ袋持たせてください」
「嫌?」
――レジ袋持った吸血鬼って、夢が音を立てて崩れていく光景そのものだわ!
などと言うことはできず、アンナマリアは「持てますから!」と言ってレジ袋を半ば強引にもぎ取った。
伯爵は不思議そうな顔をして彼女を見下ろしている。彼女はわずかにため息をつくと、気を取り直した。
「そうだ、伯爵何か食べます?」
「食べる?何があるのかな?」
アンナマリアは少しだけうーんと考えた。
「あ、伯爵。クレープって食べたことあります?」
「クレープ……話には聞いたことがあるが、ないな」
その返答にアンナマリアはにっこりと笑った。
「じゃあ、クレープ屋さんに行きましょう!」
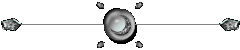
二人は場所を移動して、レストランやカフェが並ぶ区画に来た。移動する間も、伯爵は珍しげに辺りを見回し楽しげなカップルなどとすれ違うと目を細めていた。
「なるほど、一日過ごせるように設計されているのだな」
「ええ。何でも売ってますから。あ、映画館とゲームセンターもあるんですよ」
伯爵は少々目を丸くした。
「結局は一つの建物に街のメインストリートが入っているということなのだな――やれやれ」
「あ、伯爵あそこです」
アンナマリアが指差したのは、かわいらしいカフェだった。キッチンが外からも見れる造りの店で、店員がパフォーマンスを兼ねてクレープを焼いて見せるのだ。
そしてカウンターの下部には、クレープのサンプルがたくさん並んでいる。
アンナマリアははずむ声で言った。
「伯爵、どれがいいですか?」
伯爵は並ぶサンプルを一通りみると、彼女に尋ねた。
「よくわからんな。一番オーソドックスなのはどれだ?」
アンナマリアは一番左端のサンプルを指差した。
「“チョコバナナ”かな。生クリームとバナナのスライスとチョコレートソースのクレープなんです。あ、アイス付きもありますけど……」
「アイスは結構だ。冷えるからね。では、それにしようか」
「じゃあ私は……」
アンナマリアはしばしサンプルの上で視線を行ったり来たりさせ、うん、と言って控えていた店員に行った。
「“チョコバナナ”一つと……ええと、“フルーツたっぷりの生クリームチョコレートアイス”一つ」
そして、財布を取り出そうとしている伯爵を制する。
「ここは私が」
有無を言わさずバッグから財布を取り出すと、伯爵は肩をすくめた。
店員は会計を終わらせると、丸い鉄板に向かい二人に少々お待ちください、と言った。
鉄板に生地を落とし、伸ばし、ヘラを使ってひっくり返し、いい色になったところで、隣のトッピングのためのプレートに移す。次に店員は手際よくスライスしたバナナを並べていった。
「ほう、面白いな」
「私、昔クレープ屋さんに憧れてたんですよ」
店員が真っ白な生クリームを搾り出す様子を見ながら、二人は言葉を交わす。ちょっと間をおいて、伯爵がサンプルを見下ろしながら言った。
「ところでウラニアよ、サンプルを見たところ君の頼んだ物は、その、いいのかね?」
その言葉にアンナマリアは首を傾げた。
「なにがです?」
伯爵はキウイ、イチゴ、バナナ、アーモンドチップに生クリームにチョコレートソース、そしてバニラ・アイスが乗ったサンプルをじっと見つめながら言った。
「……よく言うではないか、夜八時過ぎの食事は控えたほうがいいと」
アンナマリアは伯爵の言いたいことを悟った。
「少しくらいのカロリーオーバーを気にしていたら、何も食べられません。
それに、今日はレポートを仕上げたのでご褒美なんです」
その時、店員がクレープをくるりと紙に巻き終わり、客に差し出した。伯爵は少し躊躇してからそれを受けとり、しばしそれを珍しそうに観察していた。
そして、店員がアンナマリアの注文したものを作るためにクレープ生地の上に様々なものを並べ始めるとぽつりと言った。
「……いつの世になっても女性というのはよくわからん。」
と。
二人で向かい合わせになる席に座り、クレープを頬張る。
アンナマリアは特に幸せそうだ。
「ずいぶん甘いな」
伯爵が感想を述べると、アンナマリアがクレープから顔を上げた。
「苦手ですか?」
「いや、美味しいよ」
答えて、伯爵はアンナマリアの顔のほうへ手を伸ばしてきた。アンナマリアが驚いて身を引きかけると、伯爵は苦笑しながら親指で彼女の口元を撫でた。
見れば、指には生クリームがついている。伯爵はひょいとそれを自分の口元にもって言った。
アンナマリアはそこからの伯爵の行動を正視せずに、クレープを口に運んだ。
まぁ、齢2000歳を超えるこの吸血鬼のことだ。その行動に“ある種の深い意味”などなく、ただ「レディらしく上品にお食べ」ということを言外に言いたかったのだろう。
アンナマリアはそう思って、クレープの向こうで重いため息をついた。
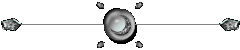
「――コーヒーが一杯欲しいところだな」
食べ終わると、伯爵は一言言った。アンナマリアは自分のクレープの包み紙を丸めると、彼に言う。
「せっかくだから、他のところの飲みますか?」
「うん?」
「街にはないんですけど、世界展開しているコーヒーショップも入ってるんですよ。せっかくだからどうです?」
「そうだな……」
伯爵が言うと、アンナマリアは立ち上がった。
「じゃあ行きましょう」
ゴミをゴミ箱に放り込み――どうしたらわからない、といった顔をしていた伯爵のものも投げ入れて――二人は歩きだした。
数歩歩いたところで彼女に伯爵が並び、彼女は口を開く。
「そういえば、伯爵、お財布なんてもってらっしゃるんですね、びっくりしました」
「マーサに持たせられたのだ。と、言ってもわたしが財布を持たなくなったのはここ二百年のことで、その前は自分で買い物をしていたがね」
「いえ二百年持ってなかったら十分だと思います……」
そんな彼女の言葉が聞こえなかったのか、伯爵は何を思ったか貨幣経済の発展について自論を展開し始めた。マックス・ウェーバーの見解についての反論や、カール・マルクスの論の落ち度などを自分が見てきたことを交えて話す伯爵の話に、アンナマリアはくらくらした。
天文以外の専門的な話には彼女はお呼びでない。
やがて、目指すコーヒー・ショップが現れてアンナマリアはほっとした。
「伯爵、何にします?」
「エスプレッソ」
「じゃあ私はキャラメルマキアートで」
注文後、作られ始めたキャラメルソースがかかった暖かな飲み物にまた伯爵は何か言いたげだった。だが二度も同じことを言うのは野暮だとわかっているらしく、何も言わない。
席に着くと、アンナマリアはカプチーノを口元に運ぶ伯爵を見ていった。
「でも珍しいですね、伯爵がコーヒーを頼むなんて。いつも紅茶ばかりだから……」
「たまにはね」
そう言って彼が足を組むと、なんとも絵になる。二人連れの若い女性が、向こうのテーブルから彼に熱い視線を送っている。アンナマリアはあの二人がこの人の正体を知ったらどうするだろう、と想像してちょっと青ざめた。
「どうかしたのかね?」
「いえ、なんでもないです」
温かな飲み物を黙って啜るアンナマリアに伯爵はしばし首を傾げ――そして切り出した。
「飲み終わったらすこし歩きまわらせてもらってもいいかな。君にも付いてきてもらえるとありがたいんだが――迷子になるのはいやなのでね」
アンナマリアはその言葉に笑って「はい」と言った。
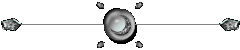
レストランやカフェが集まるエリアのすぐ隣には、ゲームセンターがある。
伯爵は居並ぶ箱型のゲームだけに特化したコンピュータたちを眺めている。
「コインを入れればできるんですよ。伯爵、やってみます?」
伯爵は肩をすくめた。
「興味がないわけではないが、わたしがこういうのがダメなことを知っているだろう?」
そう言いながら、伯爵は数々の筐体の間を抜けていく。レースゲームでは夢中になっている二人の若者に面白そうな視線を向け、クレーンキャッチ式のプライズゲームの前で真剣になっているカップルにはやや年寄りくさい目を向ける。
アンナマリアはそんな彼の後を、背中でゆるく手を組み合わせてゆっくりと付いていった。
しばらくして伯爵がふと歩行の速度を緩めて、アンナマリアに並んだ。
「娯楽と言うのは、中身が変わっても本質は変わらんな」
ふと、誰に語りかけるでもなく独り言のように言った伯爵の言葉に、アンナマリアは辺りを見回した。
その彼女の視線が、ふととある一角で止まった。
「……」
「どうした?」
伯爵の視線がアンナマリアの視線を追う――二人視線がたどり着いたところには、ベビーカーに乗った赤ん坊と、立ち尽くす三歳くらいの男の子がいた。
アンナマリアは首筋に手をやり、服の中から父の形見の銀の懐中時計を取り出した。
カチリと音を立てて蓋が開くと、開いた蓋の裏に彼女の亡くした家族の写真――ただし妹が赤ん坊の頃のものだ――とその隣の本体部分にレトロな白い文字盤の時計が並んであった。
伯爵がそれを覗き込む。
「夜の九時はとっくに回ってるな」
アンナマリアと伯爵が顔を見合わせると、立ち尽くしていた幼い男の子がフラフラと揺れだした。アンナマリアは「わぁ!」と声を上げて、眠りの攻撃に陥落する幼児を床に崩れ落ちる前になんとか駆け寄って抱き上げた。受け止められた幼児はアンナマリアの肩を枕にしてすぐに寝息を立て始める。
伯爵は困り顔のアンナマリアに歩み寄る――そしてベビーカーの中ですやすやと眠る赤ん坊と、男の子を見比べて歯の間から低く威嚇するような声を出した。
「この子達の親は何をしている?」
伯爵が言い終えると同時に、二人の背後から悲鳴が上がった。
「誘拐犯!」
そして二人が振り返ると同時に、アンナマリアは腕に抱えていた男の子をひったくられた。
男の子はびっくりして目を覚まし、一瞬後わっと泣き出した。
「あー怖かったねーヨチヨチヨチ」
アンナマリアはぽかんとしてその光景を見つめていた。彼女から男の子を奪ったのは、いかにも、と言う感じの短いスカートに派手な格好の女だった。そしてその後ろからは先ほどまで何かのゲームに熱中していた、だらだらした服装の男がゆっくりとふてぶてしく歩み寄ってくる。伯爵は眉根を寄せた。
男は彼らの元にたどり着くと、ベビーカーを乱暴に引き寄せた。またしても赤ん坊が目を覚まし、ぎゃっと声を上げて泣き出した。
「おめぇらヒトサマんちのガキに何しやがるッ!」
明瞭でない発音。明らかに頭の悪そうな言葉遣い!
アンナマリアは「はぁ?!」という言葉が喉を駆け上がってくるのを感じたが、ぐっと唇を引き結んだ。
伯爵は顎を引いた。そして、一歩前へ出る。すると、父親らしいその男も一歩前へ出た――と、どうだろう、伯爵の方が頭一つ分背が高い。男はそれが予想外だったのか、多少怯んだようだった。
「君たちがこの子たちのご両親かね」
伯爵はあくまでも冷静だ。いやむしろ、口調は冷淡だった。
子どもはあやす母親など構わずに泣き続ける。男は妻を振り返った。
「黙らせろ!」
「今やってる!」
妻の口答えに夫たる男は悪態をついた。そして、伯爵にまた向き直る。
「子どもを作るのは容易いが、親になるのは難しい――典型だな」
「あ?」
「今は夜の九時過ぎだ。君たちはいつも何時に子どもを寝かせているのかね」
伯爵は冷たい声で男に尋ねる。すると、男は口答えしようと口を開いた。
「てめぇにはかんけ――」
「夜は子どもは寝る時間だ」
だが、伯爵はぴしゃりとそれを遮る。
アンナマリアはちょっとはらはらしていた。こういう手合いは、後で仕返しが怖いのだ。だが、伯爵には臆する気配が全くない。
「幼児期に夜八時以降まで起こし、活動させておくと脳と神経および精神の発達に障害が生じる。
性格が荒くなったり、集中力がなくなったり、暴力的になったりな。
睡眠というのは食事とともに人間とって絶対的に必要なものだ。彼らには健全な眠りを得る権利と義務がある」
「なんだと、オレらはコイツらの親だ!親がどうしようと」
「わたしが言ったのは君たちの権利ではない。子どもたちの権利だ。年端も行かず、物心も付かないからと言って彼らの睡眠の権利を侵害することはしてはならないことだ。親であっても、な」
伯爵はそこで泣き止まない、母親の腕の中の男の子を指差した。
「現に彼は睡魔に勝てず床に顔から着地するところだった。アンナマリアが抱きかかえなければ大変なことになっていたぞ。君たちはわたしの連れに感謝することはあっても、誘拐犯などと罵る権利はない。それに、親の権利を主張したいようだが、君たちはそれに相応しい態度を示しているようには見えないな。
自分たちは遊戯に夢中になり、この子達を放置していたようだが?」
父親らしい男は伯爵が息もつかずすらすらと言葉を並べたことに対して、口をパクパクさせていた。たぶん、彼が伯爵の言葉を理解するのにはもうしばらく時間がかかる。
その間に、つかつかと伯爵は母親に歩み寄った。そして、「ひっ」と言って後ずさりした母親に声をかける。
「その子をかしたまえ――」
アンナマリアでさえ、伯爵が何を言っているのか一瞬理解できなかった。だが、女は腕を差し出されて、投げるように子どもを差し出した。伯爵はまた一瞬むっとしたようだったが、すぐに子どもの顔を見て表情を和らげる。
男の子の方は、母親から知らない男――しかもこの男、体温が低い――の手に投げるように預けられて、さらにその泣き声を大きくしていた。
だが伯爵は怯む様子もなく、彼をあやし始めた。体を揺らし、なにやら彼に話しかける――話し声に気づいて、集中しようと思ったのか彼は自らの声を小さくし始めた。
すると、低い声だが限りなく優しい子守唄が聞こえてきた。
伯爵が歌っているのだ!
と、アンナマリアも気づくのに数秒かかった。
伯爵の腕に抱かれた男の子は不思議そうな顔をして伯爵を見上げ、親指をくわえ始めた。そしてそれからしばらくすると、彼はうつらうつらしはじめた。
彼の母親はすっかり目を丸くしている。
気がつけば、ベビーカーの中の赤ん坊もいつの間にか泣き止んでいた。
やがて男の子はこてん、と伯爵の胸に頭を預けすやすやと寝息を立て始めた。
伯爵はそれを見て、歌をぴたりと止めた。そして、母親に目配せする。短いスカートをはいた母親は戸惑いながらもそっと腕を差し出した。伯爵はその腕へとゆっくり慎重に子どもを移動させる。
子どもは母親の腕の中で幸せそうだった。
「あ、ありがとうございます……」
伯爵は穏やかな表情で母子を見下ろしたあと、視線を動かした。
伯爵の視線の先には、ぽかんとした顔をした子どもたちの父親がいた。
「子どもが健全に育たないということは、君たちの苦労も増える。
将来の幸せのために、いま少し自分たちの楽しみを我慢してはどうかな」
男は伯爵の顔を見つめながら、ぽかんと開いていた口を閉じた。
「関係ないだろ、おっさ――」
おそらくその先は「おっさんには」と言いたかったのだろうが、伯爵の年齢不詳気味の美貌に気圧されたらしく彼は言葉を止めてしまった。
――おっさんどころかおじいちゃんでも足りないくらいなんだけど……。
いつの間にか蚊帳の外ぎみになってしまったアンナマリアは伯爵と親子を見比べながら思った。その視界の中で、伯爵が穏やかに畳み掛ける。
「子どもは夜八時には寝かせる。なに、ちょっとだけ根気がいるだけだ。子どもたちが寝静まった後は、二人で静かに過ごすのも悪くないと思うがね――こんなに五月蝿いところではなく」
伯爵は様々な効果音が流れる一帯を優雅な手振りで示した。たしかに、耳慣れないとここは頭痛がするほどに音に溢れている。
「どうだね、子どもたちは八時には寝かせるかね?」
そして、伯爵は一家を見つめながら言った。すると、答えたのは母親だった。
「はい、寝かせます!」
「おいっ」
みれば、母親は頬を赤く染めている。アンナマリアはなんとなくその理由がわかり、
――伯爵、人妻をも惚れさせる容姿の持ち主……。
と思って青ざめた。おそらく、彼女は子どもを返されたときにまともに彼の美しい顔を見てしまったのだろう。
だが幸いなのか、その夫にして子どもたちの父親はその様子に気づかない。
「では、子どもたちを八時には寝かせるのだね――約束だよ」
伯爵はにっこりとした口調で言った。その言葉にこくこくと人妻は頷き、夫のほうもしぶしぶと言った感じではい、と言った。
「そうか、それはよかった」
伯爵のその言葉に、ほっとしたのはなぜかアンナマリアだった。そして彼女は、辺りを見回してぎょっとした。
人だかりができていたのである。
人だかり、といっても夜なので高が知れた数ではあったがアンナマリアが驚くには十分なものだった。そして、彼女の様子に気づいたのか伯爵も辺りを見回した。
「おや……これは」
そこへ、客の一人に誘導されてこのゲームセンターのスタッフが一人やってきた。
「あの、どうかなさいましたか」
スタッフはおずおずと騒ぎの中心人物――ほとんど蚊帳の外だったアンナマリアも含まれていた――を見回した後、伯爵を選んでそう尋ねてきた。
伯爵は苦笑するような笑みを浮かべて答えた。
「これは失礼。しかし、君の手を煩わせるようなことはなにもないよ――どうぞ仕事にもどってくれたまえ。皆さんも、すまなかった」
伯爵は優雅な動作で謝意を表した。すると、取り囲んでいた人のうち女性はぽっと顔を赤らめ、男性は畏怖を感じたような顔をした。その様子を見て、アンナマリアはまた少し青ざめた。
「ほら、あの、もう行きましょう――本当にすみませんでした」
アンナマリアは伯爵の左腕に自分の腕を――しがみつくように――絡ませて、後ずさりした。伯爵は不思議そうな顔で彼女を見下ろしている。
すると、人々は――女性は名残惜しげに、男性は足早に――自然と解散していった。後には二人の子どもを抱える夫婦だけが残される。アンナマリアは腕を解いて伯爵に向こうを向かせてその背中に回りこみ、そこを押す――そして、若い夫婦を振り返った。
短いスカートの妻はぼうっとしてこちらを見ており、ダラダラした格好の夫は苦々しげな顔をしている。アンナマリアはなんとなく事情を察して、つい言ってしまった。
「あの、約束は守ったほうがいいですよ。
じゃないと、吸血鬼が祟りますから」
その言葉に夫のほうはぎょっとした顔をした。どうも、やはり図星だったようである。
アンナマリアは伯爵を背中を押して歩ませた。
|