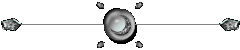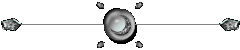|
さて、伯爵は車が車庫に入る直前に庭の一角が明るいことに気づいた。そこには、一軒の木造の小さな小屋がある――伯爵がとある人物に、庭の草花の世話とひきかえに貸し出している小屋なのだ。
ワインの入った袋を提げて、アンナマリアを屋敷に見送った伯爵はぶらぶらとそちらに歩いていく。庭師はべつにいるが彼はもっぱら木々の担当で、伯爵が庭の一角に家を貸し出している人物は薬草などの世話を担当している。
――この時間ならいつもはもう寝ているのに。
その人物は早寝早起きなのだ。
暖かな色の灯りに惹かれるように伯爵は小屋のような家に歩み寄った。いつだかもっと立派なものも建てられるぞ、と彼女に言ったこともあったが彼女は断固として拒否したのだ。
入り口は一段高くなっている――踏み台になっている灰色の石の周りには、鉢や薪が整然と並んでいる。伯爵は石に乗ると、軽くノックをした。
数秒、間があり――そして伯爵の耳には、小さな声のやり取りも聞こえた――ドアが開く。
「まぁ!ご主人さま!」
「やぁマーサ」
そこにいたのはマーサだった。しかし、伯爵がこの家を貸し出しているのは彼女ではない。
お迎えもしませんで、というマーサに伯爵は片手を上げた。
「珍しいな、君がここにいるとは」
「いえ、実はあのあとダドリーさんの具合が悪くなって。
内科か獣医か迷ったんですが、やっぱりシビラ様にお見せするのがいいかと思いまして」
伯爵は頷いてドアをくぐった。そこはリビング兼ダイニング兼キッチンという空間だった。
壁にはやはり木で作られた棚が並び、棚の中には食器や本などのほかに、調味料やジャム、そして薬草が入ったビンがそれなりの秩序で鎮座していた。
そして、リビングである場所に置いてあるソファの上には白い狼姿のダドリーがぐったりと横たわっていた。そして、その前にはこちらに背中を向けて彼の様子を見ている女。
癖の強い、少し赤みをおびたような黒く長い髪が背中の半ばまで垂れている。女がふと振り返った。その顔は、よく言えば意志の強そうな、悪く言えばきつそうな顔立ちだ。
「具合は?ホットワイン用に買ってきたんだが」
女はスッと立ち上がる――背はそれほど高くないが、すらりとした立ち姿の美しさは伯爵に負けないほどだった。
女は伯爵の差し出した封のあいていないドイツ産ワインを受け取った。そして、マーサに言う。
「マーサさん、ハチミツがそこの棚にあるの。よかったらそれでホットワインを作ってあげて」
ハチミツのビンを取り出したマーサはワインも受け取り、ダドリーを見下ろした。
「自室にもどって寝せましょう。その方が落ち着くでしょうから。
さっ、ダドリーさん!立てます?もどりますよ!!」
白い狼はよろよろと立ち上がった。
「シビラ様にもご主人様にも、ありがとうございます……ご主人様、このワイン本当に戴いても?」
「ホットワインに合いそうなものを選んだ。魔女殿のハチミツとマーサの腕があれば、体がよく温まるものになるだろう。よく眠るといい」
白い狼はすっと首を下げ、マーサについて小屋を出て行った。
ドアが閉まると、女が言った。
「私は魔女じゃないわよ」
「これは失礼を、カサンドラ」
伯爵は意地の悪い笑みを浮かべると、すっと彼女に礼をした。女はさらにむっとする。
「私は、シビラよ――その名前で呼ばないで」
「異教の巫女か、相変わらずセンスがないな。それとも、“誰でもないもの”と名乗ったオデュッセウスのように実は意味があるのかい?」
「その男の名前は出さないでって言ったでしょ――このやり取り、何百年続ける気?」
シビラが怒ったように腰に手を当てて言うと、伯爵はくつくつと笑った。そして、彼は先ほどまでダドリーが寝そべっていたソファに腰掛ける。
「ダドリーが世話になったな。何か悪い病気ではないな?」
「ただの風邪ね。ちょっと歳もとってきてるから、それもあると思うけど」
「それならよかった。しばらく暇を出そう」
そう言ってから、伯爵はもう一本の試飲してきたワインを取り出した。
「一緒に飲むか?今の基準ではまずい部類に入るが、ふと懐かしい気がしたのでね」
にっこりと笑って言う伯爵に、シビラはため息をついてグラスを二つ持ってきた。そして彼女は伯爵の前の床にすっと腰をおろして、彼にグラスを差し出した。伯爵は美しい手でワインビンをつかみ、そこへワインを注いだ。そして次に、自分のグラスにワインを注ぐ。
長年の慣習に従って、シビラと伯爵はグラスを合わせて涼やかな音をさせた。伯爵が見守るなか、シビラがワインを口に運んだ。
一口飲んだ後、彼女はじっと深い赤の液体を見つめて言った。
「確かに、懐かしいわ――水で薄めたみたいな味」
伯爵は笑う。そして自分も一口口へとワインを流し込むと、言った。
「そうだろう?しかし、わたしは気づくのにちょっと時間がかかってね。最近のワインに舌が慣れてしまっていたようだ」
「こんなワイン、何年ぶりかしら。――徐々に変わっていったから、正確な年数はわからないわね」
水で薄めたような味――それは、シビラと伯爵には懐かしいものであるようだった。
古典古代の時代、つまり二千年以上前には葡萄酒とは薄めて飲むほどに濃いものであったのだ。
――つまり、その味を知っている、伯爵の庭に間借りする“シビラ”という女も、やはり人ならぬ存在なのだろうか?
「それはそうと」
シビラは躊躇することなく現代の基準にしては不味いワインを口に運びつつ言った。
「あの娘、元気になってきてるのね」
「ああ、おかげさまでそのようだ。完全とはいかないがね。“事件”のときには君にも迷惑をかけたな」
「気に入ってるのね」
「うん?」
「あのこのこと」
シビラは瞼を半ば伏せて伯爵を見上げた。伯爵は口元に運びかけていたグラスをぴたり、と止めた。
「……そうだな。なかなかにいい子なのでな」
「まぁ、奥ゆかしいこと」
シビラは大きく目を見開き、胸に手を当てて白々しいと言いたげな口調で言った。伯爵は傾かせかけていたグラスを下ろした。
「それ以上でも、それ以下でもないよ、何なら君の能力で未来を覗いてみたらどうだね」
「私の予言は当たりますけど、誰も信じませんから」
二人は無言でグラスを傾けた。しばらくして、シビラが言った。
「私の方があなたより年上よね、たぶん」
伯爵はゆるゆると首を振った。
「確かに私の記憶があるのはアクティウム海戦の前年からだが、吸血鬼は古代ギリシアからいたらしいからな。私は関知しないが」
「アクティウムはギリシアの地だから可能性はあるわね」
シビラが指摘すると、伯爵は首を傾げた。
「それで?」
「何が?」
「我々の歳の差を指摘して、なにかあるんじゃないのか?」
シビラは一口ワインを飲んだ。
「あなたみたいな“生ける死者”と私みたいな“生かされ続ける者”の年齢を比べても仕方ないわね――言ってみただけよ」
そう答えたシビラの顔を、伯爵はさぐるような視線で見ていた。そんな伯爵に、シビラはさらに言う。
「それ飲んだらもどってね。私、もう眠いのよ」
その言葉に伯爵は苦笑すると、一息にワインを飲み干した。そして眉をひそめて「まずい」と言った後にすっと立ち上がった。
「邪魔したな。たまには屋敷で夕食でも一緒にとろうじゃないか」
「考えておくわ」
シビラは伯爵の手からグラスを回収しながら、平坦な口調で言った。それから、ソファの傍らに置きっぱなしのワインビンに気づく。
「ワイン、持ってかえらないの?」
「料理にでも使ってくれ。わたしは舌が肥えてしまってね」
「古代のあなたの主人が聞いたら、たぶん退化したって言うかもね」
シビラが柔らかな口調で言うと、伯爵は苦笑した。そして彼は出て行った。
シビラはグラスをキッチンの流しに運んだ後、リビングであるところにもどってきてワインのビンを取り上げた。
「……“アンナマリア”、ね。吸血鬼たるあの男には、ちょっと合わないわね」
ラベルに目を落としながら彼女は一人ごち、明日は煮込み料理にしましょう、と思った。
|