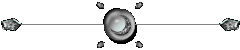|
「失礼だな、わたしは祟らんぞ」
「例えですってば」
モールの母体となっているスーパーマーケットを歩きながら、伯爵は苦言を呈し、アンナマリアは言い訳した。
だがすぐに伯爵は機嫌を直し――それ自体演技だったのかもしれないが――、スーパー内を珍しげに眺めだした。積んであるリンゴをとりあげて、眺め、もどし、居並ぶスナック菓子に驚いてみせる。
「そういえば伯爵、子どもあやすの上手なんですね、意外です」
そんな彼を見つつ、アンナマリアがふと思い出して言うと伯爵は苦笑した。
「むかし、子守奴隷の真似事をしたことがあってね」
「……どれい?」
伯爵は笑っただけで答えない。
そして彼は、うろうろした末に酒屋を見つけた。伯爵はすこし弾んだ声で人間の娘に尋ねた。
「あそこに入っても構わないか?」
アンナマリアはこっくりと頷いた。
思えば、こんな様子の伯爵を見るのははじめてである。アンナマリアは彼に数歩遅れてついていった。酒屋に入ると、彼は温度が保たれたワイン売り場に真っ直ぐ向かった。アンナマリアは色々な形のビンに入った様々な種類のリキュールを眺めから、彼に続く。
天井まで続くワインの棚前で、伯爵は顎をつまんでいた。
「新しいものばかりだな」
「まぁ、スーパー内の酒屋ですから」
言葉面では不満そうだった伯爵だが、棚を眺める横顔は楽しげだ。そして彼は一本のワインを手に取った。白く美しい横顔が、ラベルを眺める様子はとても絵になる。ここがスーパーの一角でさえだ。
アンナマリアが見るともなしにその光景を眺めていると、不意に外野から声がかけられた。
「試飲なさいますか?」
それはエプロンをした女性店員だった。伯爵はそれを聞いて顎を引く。
「構わないのかね?」
「はい、そちらになさいますか?」
にっこりと言う店員に伯爵は笑みを返す。アンナマリアは内心で頭を抱えたくなった。彼女の予想通り、女性店員は一瞬ぱっと頬を赤らめていた。
「いや、これではなく……そうだな」
伯爵は持っていたワインの瓶を棚に戻すと、とあるワイナリーの名前を挙げた。すると店員はふたたび接客笑顔を取り戻した。
「はい、かしこまりました」
そして彼女は備え付けの、棚ではないちゃんとした温度管理ができるワインセラーから一本のワインを取り出した。
つまり、そのワインは棚に無造作に置かれるようなものではないのだ。
店員はなれた手つきで封印をあけ、コルクを抜いた。
彼女がグラスを二つ取り出したところで、アンナマリアは慌てて手を挙げた。
「私は車を運転するので……」
すると店員はひとつ頷いて、ひとつのグラスだけにワインを注いだ。伯爵はそれを受け取ると、ワインに空気を含ませながら、色を見た。しばしそれを眺めて香りを確かめ――少し眉を寄せた後、伯爵はワインを一口口に含んだ。舌の上で十分に転がした後、嚥下する。
そして再び、彼はグラスの中のぶどう酒を見つめた。
「こちらのワイナリーのものはとても人気があるんですよ!口当たりも優しいですし、お値段も手ごろなものから、高級なものまで……」
店員のセールス・トークを聞きながら、アンナマリアは伯爵の顔を見上げた。
店員は商品の素晴らしさをまるで音楽のようにとうとうと語っているが、その言葉に似合わないほど伯爵の顔は渋い。
彼は渋い顔をしたまま、残りのワインを喉に流し込んだ。
そして苦笑を浮かべると、店員にグラスを返した。
「試飲した、その開けたワインは買わせていただこう。しかし、封をした物はもっと別なものがいいな」
店員はびっくりして伯爵に言った。
「いいえ!試飲分のワインはサービスなので、買い取っていただかなくとも……」
「ワインは生き物でね。開けてしまったら飲むしかない。それにここはもうすぐ閉店で、わたしの他にそれを試飲する客ももう来ないだろう。
……そうだな、封をしてあるのはドイツ産のものがいい。フランコニアのアイスワインはあるかね?」
「えっと……アイスワインは当店では扱っていないんです……」
「では普通のもので十分だ」
伯爵は試飲したワインのビンを取り上げると、器用にコルクを差し込んだ。店員はその行動にちょっとびっくりしていたが、すぐに気を取り直し、ドイツ産のワインを探しに行った。
店員の姿が見えなくなると、伯爵はアンナマリアを振り返り肩をすくめた。
アンナマリアはええと、と言った。
「アイスワインって……なんですか?」
すると、伯爵は目を丸くした。
「知らんのか。……今度飲ませてあげよう」
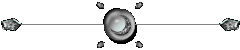
何本かのドイツ産のワインから伯爵は気に入ったものを今度は試飲なしに選び出し、試飲したものと一緒に有無を言わさず会計させた。
アンナマリアは彼の強引さ等々にやや呆れながら、もうかえりましょう、と彼を駐車場の方へ引きずっていった。
その途中、彼女はまたしても買い物袋――ただし今回は茶色の紙袋だった――を下げる伯爵からそれを奪おうとしたが今度は失敗した。
伯爵曰く、
「女性に重いものを持たせるわけにはいかん」
とのことだった。
暖かく明るい店内を出て、暗く寒い駐車場を歩く。
アンナマリアは空を見上げた。ここは明るすぎて、星はどこかへ隠されてしまい、月さえも遠慮をしているように思われた。
――街は山一つ隔ててるから、そんなに光度が上がらなかったけれど……。
最近、教授たちが観測施設の移転について話し合っているとの噂も聞く。しかしアンナマリアには、これはどうしようもないことだ。彼女はため息をついた。
と、そこで不意に隣を歩いていた伯爵が立ち止まった。
「伯爵……?」
伯爵は前を凝視していた。その方向に目をやれば、フードつきパーカーを来た男が歩き煙草をしつつ、彼女と楽しげに歩いている。なんでもない光景だった。
「あの人たちがどうかしたんですか?」
アンナマリアが不思議に思ってそう尋ねたのと同時にそれは起こった。
ぽと、と男が火が付いたままの煙草を道路に何気なく捨てたのだ。
暗い闇の中で、赤く燃える煙草の先端と白い煙はよく目立った。
「「……」」
アンナマリアは絶句し、伯爵は眉間に皺を溜めていた。
何気ない喫煙男のその動作。あきらかに常日頃そのようにポイ捨てしているのだろう。
二人は捨てられた、まだ吸殻とはいえない煙草に近づいた。
アンナマリアはため息をついて、靴底でその煙草をもみ消そうとした。
「待て」
そんなアンナマリアの行動を伯爵は寸前で止めた。
「何も君の靴を痛める必要はない」
「あ、灰皿探した方がいいですか?」
だが伯爵はそれには答えず、黙って優雅な仕草で煙草を拾い上げた。少々汚いものを扱うかのように指先でつまんでいる。
「いや、もっといい場所に捨てよう」
そういうと、彼はアンナマリアの反応を待たずに何気ない動作で手首を動かした。
摘まれていた煙草が解き放たれ、美しく完璧な放物線を描きながら飛んでいく。
アンナマリアはその行方を顔を動かして追った。
すると。
見事、火のついたままの煙草は元の持ち主のパーカーのフードに綺麗に収まった。
アンナマリアはびっくりして声を上げそうになった。が、伯爵は口元に意地の悪い笑みを浮かべている。
数十秒後、フードから細い白煙が上がりだし、男がぴたりと立ち止まった。その連れの女がどうしたの、と立ち止まる。
男はなんかへんだな、と言った感じで肩越しに背中を探り始める。女は首を傾げてそれを見守っている。
それからまた数十秒後――白煙が、黒くなった。
途端、男は悲鳴を上げてパーカーを脱ごうとした。女もさすがに事態に気づいて、慌ててそれを手伝おうとする――が、しばらくの混乱。
そして、やっと男がパーカーを脱ぎ捨てたときには、フードには小さな明かりが灯っていた。
二人は呆然と焦げてゆくパーカーを見つめている。
アンナマリアは呆然として口を半開きにしていた。
その隣からくつくつと実に楽しげに笑う声。
アンナマリアは口を開けたまま、伯爵を見上げた。
そして一言。
「……やりすぎって言葉をご存知ですか?」
「やりすぎ?いやいや、因果応報というのだよ」
伯爵は実に楽しげだった。そして、アンナマリアは心の中でそっと呟くのである。
――この人、やっぱり吸血鬼だわ。
と。
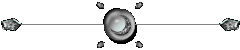
アンナマリアはやや疲れながら白いクーペのハンドルを握った。思ったより遊んでしまった。早く帰って印刷をしなければ。
――とはいえ。
伯爵はたしかに吸血鬼だが、同時に曲がったことは嫌いらしい、と思う。彼女はこの謎めいた人――「人」でいいのかはわからないが――について、ほんの少し、本当に少し、ふと何かが見えた気がしていた。
――でも、人に説教する吸血鬼っていうのも、買い物袋の次に夢が壊れるわ。
アンナマリアはちらりと伯爵を見た。
ちょっと怖い「因果応報」を体現して見せた吸血鬼は、音楽と心地よい振動に身を任せて目をつぶっている。
アンナマリアはため息をついた。
やがてクーペは屋敷に帰り着いた。
門を抜け、車庫へと向かう。車庫入れの苦手なアンナマリアは極度に緊張していた。
だから彼女は伯爵がふと庭の一角を見つめていたことにも気づかない。それでもすぐにクーペは囲われた車庫に入ってしまったので、伯爵は今度はアンナマリアのハンドルを握る手に視線を移した。
太めのハンドルを捌く手指細くどこか頼りなげだったが、十分に鑑賞に堪えられるものだったのか伯爵はふと――どこかの映画で見たような雰囲気で――目を細めた。
やがてクーペはおっかなびっくり定位置に納まった。
ハンドルを離したアンナマリアはふぅと息をついた。伯爵は笑いながら、CDを取り出した。
その伯爵に驚きの表情を見せると、彼は言った。
「取り出すのは簡単なんだ――マークが統一されているしね。さて、降りようか」
二人はシートベルトを外し――アンナマリアは荷物をすべて後部座席からとりあげてから――クーペを降りた。鍵をかけると、クーペは沈黙した。
伯爵はそのまま運転席側に回り込んだ。ふと横に来た伯爵をアンナマリアはぱっと見上げる。
「ワインと鍵を渡してくれるかな――」
アンナマリアはワインの入った袋をまず渡し、鍵に関しては一言言った。
「私が戻しておきますから」
「いや、わたしが預かるよ――君は早く印刷をするといい。印刷してから見つかる誤字脱字というのはよくあるからな」
アンナマリアは数瞬迷ったようだが、「じゃあお願いします」と言って鍵を差し出された伯爵の指が長く美しい造形をした手の上に落とした。
そして、彼女はビニール袋を胸に抱えると伯爵に一礼して踵を返した。
その背中に伯爵が声をかける。
「時間を掛けさせてすまなかったな――今日は楽しかったよ」
すると、行きかけていたアンナマリアは立ち止まって振り返った。彼女は心からの笑みを伯爵に見せた。
「私も楽しかったです――ちょっとびっくりしましたけど」
そして翌日、彼女は遅刻することもなくレポートを提出し、Aプラスの成績を得たのだった。
|