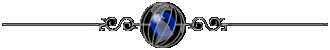|
「学校はどうだったね」
伯爵はマントの上をまたいで彼女の傍らに来た。アンナマリアはため息をついて肩をすくめる。その間に執事のダドリーがマントを拾い上げていた。
「いつもどおりに、何事もなく。伯爵のほうはどうでした?」
「女帝陛下のご機嫌麗しくてね、おかげで早く帰れたよ」
伯爵は笑ってソファを示した。アンナマリアが腰を下ろすと、伯爵もその隣に腰を下ろす。
「“何事もなく”というわりに浮かない顔をしているね、お嬢さん」
人の叡智の及ばないほどの年月を生きているこの男――つまり、この老吸血鬼に何事も隠し通すのは無理だと気づいたアンナマリアは降参した。
「じつは、ちょっと――あの、愚痴を聞いていただいてもいいですか」
伯爵は吸血鬼とは思えないほどにっこりする。ちょっと牙が見えた。
「もちろんだとも。だが、その前に着替えの時間をくれるかな。スーツは少し居心地が悪くてね」
アンナマリアはこっくりと頷いて、自分のトートバッグをみた。
「私も、一度部屋にもどります」
「そうか、では後で」
そう言って立ち上がった伯爵は、ふと気づいたようにああ、と言った。
「そうだ、ベルリン・フィルのレコードが手に入ったんだった、それを聞きながら話をすることとしよう」
「レコード……?」
アンナマリアが首を傾げると、伯爵は言った。
「君、聞きたいといっていたじゃないか――ホルストの『惑星』に、コリン・マシューズの『冥王星』が入ったものだよ」
「ああ!」
ぽん、と手を叩いてアンナマリアは声をあげた。が、気づいたように言った。
「……伯爵、それならそれは“レコード”ではなく“CD”なんじゃ?」
すると吸血鬼は美しい顔に面白い表情を浮かべた。
「ああ、人の開発という名の進化は本当に早くてね、……そうだ、CDだな、これは失礼を」
言い終えると同時に優雅に腰を折った吸血鬼にアンナマリアは笑った。
その表情を見て吸血鬼も笑う。そして彼は身を返して、自分の部屋へと一旦下がった。アンナマリアもトートバッグを取り上げると、自分に与えられた部屋へと向かった。
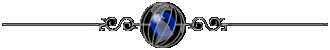
さて、噂話が正しいとアンナマリアが知ったのはほんの数ヶ月前のことだった。
数ヶ月前、とある“事件”に巻き込まれて家族を失うまでは、彼女はただ天文が好きな普通の女子大生だった。そして“事件”のときにこの屋敷の主で伯爵と呼ばれる吸血鬼に助けられ――以降、彼を後見人として彼と共に暮らすことになってしまった。
だがこの吸血鬼、奇特と言うか、それとも「変人」と評するしかないのか――なんと人間好きなのであった。もちろん、――あまり考えたくないが――食料としての人間も好きなのだろうが、純粋に生き物としての人間を愛していた。
厭世的な性格をあまり持ち合わせていない、どの伝承にも伝わり、また幾度も作品化された吸血鬼像とも全く異なる吸血鬼――それが“伯爵”だった。
必要となる食料――もしくは飲料――としての血液は、生血を吸うのではなく、血液製剤を手に入れワインに溶かして飲む。彼曰く、その血液製剤は彼女の大学の医学部に独自のルートを持っているがために入手できるという。
それを裏付けるように、“事件”最中も、この断崖の屋敷で暮らすようになってからも、伯爵はアンナマリアを襲う様子を見せない。それどころか彼女が嫌がるので、血液入りワインは部屋に下がってから執事に用意させるようになっていた。
こういう展開だと、大体の人間が「わたしを肥やしてから食べるつもりね」と悲観的な考えに走りがちだが、アンナマリアは“事件”で悲観的になりすぎたためか、伯爵をいつしか信用するようになっていた。
だいたい、肥やして食べるつもりだけだったら、のちのちフォアグラになるガチョウのように食料だけ喉の奥に流し込んでやればいいのである。何も観測に便利な屋根裏部屋とそこにつづく二階の部屋を与えたり、学費を払ってくれたり、屋敷を好きに歩かせたりはしなくていいのだ。――まぁ、人生に嫌気が差した悲観論者なら「それは後々地獄を味合わせるためだ」と言うかもしれないが。
ともかく、伯爵はその長い時間によって得た知識ともとより持ち合わせた知恵によって彼女の良き話し相手にして最大の理解者となっていた。
ちなみに、伯爵はべつに吸血鬼であることを隠してはいない。ただし吸血鬼独特の極度の紫外線アレルギーのために昼間街に出られないことが、結果「正体を隠す」ことになってはいるのだが。
しかし一般人はともかくとして、街の有志はだいたいが彼の正体を知っているし、実は街の象徴である大学を創設した“三校祖”の一人はほかならぬ彼であったのである――と、なれば前出の「独自のルート」の理由もなんとなく察せられる――。だから、街の有力者層は彼を“街の偉大なる親にして生ける守護聖人”としてあがめているところがあった。つまり伝説に言われた「街を支配している吸血鬼」というのはある意味では当たっているのである。
これもアンナマリアの伯爵への信頼の裏づけになっているといえるだろう。“守護聖人”のくだりは、バチカンが聞いたら怒り出しそうではあるが……。
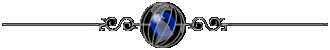
アンナマリアが再び広すぎるリビングに下りてくると、ハイネックのセーターに黒いスラックス姿に着替えた伯爵がオーディオセットのほうのソファにすでに腰掛けていた。
アンナマリアが主人の席の隣のソファに腰掛けると、彼は彼女に言った。
「紅茶は?」
「いただきます」
アンナマリアが答えると、伯爵は肩越しに振り返った。そこにはティーセットを運んできた給仕頭のマーサがいた。マーサは給仕用の移動台の上で紅茶をポットからカップへと移し始める。
「アンナマリアさまは、お砂糖とミルク、どういたしましょうか」
「お願いします」
「はい、かしこまりましたよ、だんな様は……」
「阿片を一つまみだな」
「お砂糖は?」
「最近体重が増えた」
吸血鬼がおどけたように言うと、マーサはわらった。
「そうでしたら、阿片も控えたほうがよろしいのでは?」
吸血鬼はゆるゆると首を振った。マーサは台の下から、慎重に小さな美しい砂糖壷を取り出した。その中に阿片が入っているのだ。この阿片は、血液製剤と同じルートで手に入れているのか、それとも庭の薬草園のどこかで育てているのかもしれない。
マーサは砂糖とミルクの紅茶をアンナマリアに、阿片入りの紅茶を伯爵に渡して一礼して下がった。
アンナマリアが美しいアンティークのカップとソーサーに怯えている間に、伯爵は阿片入りの紅茶を一口含んだ。人間にとっては危険な薬物であるものも、彼にとっては砂糖と同じような嗜好品らしい。アンナマリアはしばらく伯爵の様子を観察していたが、彼はやっぱりなんでもなさそうだった。
気づけば、ダドリーがオーディオ本体の操作部の前で悪戦苦闘しはじめていた。伯爵はそれをのんびりと眺めている。アンナマリアは立ち上がった。
「ああ、歳をとるとこういう新しいものがだめになりますね……リモコン系ならなんとかなるのですが」
アンナマリアは辛抱強くダドリーに操作の仕方を教えながら、伯爵が用意したCDをセットした。
そして、ホルストの組曲『惑星』の第一曲目『火星』が部屋中に力強く満ち始める。
「……この曲は話し合いに相応しくないな、飛ばすかい?」
伯爵は席にもどるアンナマリアに言った。アンナマリアは首を振る。
「全部通して聞きたいですから」
「そうか」
しかし結局、アンナマリアが口を開いたのは第二曲目の『金星』になってからだった。
学問に関わる大彗星がやってきたのに、友人がハロウィンに気を取られていること、それが彼女の愚痴だった。いつの間にかオットマンに足を乗せてくつろぎの姿勢をとっていた伯爵は、顎に手を乗せてふむ、と言う。
「その、シェーン君とやらの言い分も確かにわかるな。21歳のハロウィンは今年だけだろう?だが彗星は再び巡り来る……」
「でも、私たち、伯爵みたいに何百年も生きられませんから……。彗星が“また来る”のは、何百年周期か、それとも何万年周期かってところですから」
アンナマリアが少々憮然として言うと、伯爵は首をすくめた。
「これは失礼。だが、わたしだってさすがに何万年は生きられまい」
「そうなんですか?」
「そうだ」
「……伯爵、前からお伺いしたかったんですが、一体お幾つです?」
すると、また伯爵はふむと言った。
「……記憶があるのは紀元前32年辺りからか。それ以前のことは良く覚えていないな」
すると、アンナマリアは目を見開いた。
「……吸血鬼って300歳くらいが目安かと思ってました……」
「普通はね。わたしは最古参の吸血鬼という扱いになっている。しかもわたしの場合、紀元前32年時点ですでに成人した姿だったからね」
「……。」
つまるところ2000歳以上だ、という話にアンナマリアは担がれているのかとも思ったが、それは考えないことにした。そもそも吸血鬼が目の前にいる、ということが常識的に考えておかしな事態なのだ。しかし2000年生きているにしては、この吸血鬼、思考がプラスすぎる。普通、やっぱり、そんなに生きたら厭世的にならないだろうか。
「……人間と言う興味深い研究対象がいたからね、飽きなかったんだよ」
アンナマリアの心中を察したのか、伯爵は苦笑しながら言った。
「ともかく、ハロウィンの話だが、君はいいのかね。
あの祭りは、わたしにとっては眉唾物だが、人にとっては楽しいものだろう?
せっかく誘ってくれた友人たちの好意をフイにしてまで、頑なに彗星を観察したものかね。
まぁ、学問として興味深いというのはわかるが……しかも君は、もう三日も彗星に付き合っているのだろう?」
「そうですけど……」
「しかも友人は庭で見る準備もしよう、と言っていると」
「……」
「人間、いや、吸血鬼もだが、時折妥協して交友関係を優先した方がいいときもあるのだよ。……君は少し、頑なになっているのではないかな」
「……」
「こういっては悪いが、彗星は世界中に観察している人がいるのだから、一日くらいいいのではないかね。同じものを見ているのだし」
「……それはそうなんですけど……」
そこで伯爵は少しぬるくなった紅茶を口に運んだ。そして、優しい目を向けて言う。
「なにか、ハロウィンに嫌な思い出があるのかな?」
「いえ、全然。楽しいことばかりで。そうそう、今年は、妹に服を作ってあげようと思っていて……」
ふと、アンナマリアは口をつぐんだ。そして、急に泣きたくなった。
――家族。ふと、彼女はそれを思い出したのだ。
父は歳の離れた妹が幼い頃に亡くなっている。それから、三ヶ月前の“事件”で母と妹も亡くなった。
ハロウィン。そうだ、今年はお下がりが嫌だといった妹に母と新しい衣装を作ってあげよう、と計画していたのだ。たしか、衣装用のあの布はまだ彼女が住んでいた家にあるはずだ。もっと遡れば、父が元気だった頃の楽しい思い出。……それらはすべてあの“事件”でなくなってしまった。
――“事件”。家中に漂う血の匂い。ぐったりとした二人の人間。夏の暑苦しい、嫌な空気。
アンナマリアは口元を押さえた。手が震えている。
伯爵は、その仕草で悟ったようだった。
「……その楽しい思い出が、君を頑なにさせたのかもしれんな」
伯爵は立ち上がると、彼女の傍らに座った。ひんやりとする手で彼女の髪を撫でる。
「わたしがもっとちゃんと目を開いていれば、君は巻き込まれなかったかもしれん。
申し訳ない」
アンナマリアは黙って首を振った。伯爵はため息をつく。
「……それでも、ハロウィンパーティーに行けば気が晴れるかもしれんぞ」
アンナマリアはまた黙って首を振る。
伯爵もまたため息をついた。
「君は頑固だな」
「あの、伯爵」
アンナマリアは伯爵のほうを向いた。話題を変えようとしている、と伯爵は思った。
「うん?」
「私、夕食が終わったら観測に出かけますんで……」
伯爵は思わず半身を引いた。
「出かける?……敷地内から観測してるんじゃなかったのかね」
「はい、東の森の先に、いい広場があるんです。あそこなら街の光もある程度遮られるので」
「東の森……随分歩くね。天体望遠鏡を持って?」
「もちろんです」
「ダドリーがこのところ君が夜に出かけると言っていたがそれだったのか。誰かに付き添わせよう。本当は私が付き添えればいいのだがね、今日は少しやることがあるから」
「いえ、一人でも大丈夫です」
「しかし……」
「観測には時間がかかりますし、皆さんにはやる仕事があります」
きっぱりと言うアンナマリアに伯爵は手を挙げて降参、の意を示した。そこへ一度下がっていたマーサがもどってきた。
「さぁさ、お夕飯の用意ができましたよ。食堂に移ってくださいな」
そう言って、オーディオの電源を切ってしまう。無音になったリビングに伯爵はゆるゆると首を振った。まだ曲は『冥王星』に程遠かった。
「戴くしかないな、さて、天文の女神よ」
そう言って伯爵は立ち上がり、アンナマリアに手を差し出した。アンナマリアは
「だからウラニアじゃありませんてば」
と口答えしてから彼のひんやりした手を取った。
そして伯爵は彼女を隣の食堂へとエスコートする――途中、マーサに向かって人間には聞き取りにくい声でささやいた。
「少し、“喉が渇いた”な――食後に用意しておいてくれ」
マーサは主人の目の色を確認した――伯爵の瞳は先ほどまでは美しい青であったが、今ではなぜか淡い紫色に変化しつつあった。それは吸血鬼の、人間がおぞましいと考える“吸血欲求”がわずかに彼の全身に広がりつつあることを示す色だった。目が赤くなれば、それは“吸血衝動”直前までに“喉が渇いて”いることを示す。
マーサは食事終わりまでには間に合うな、と思い静かに目礼した。
|