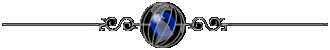|
10月30日。夜。
今夜は大学の天文部主催の彗星観測会が行われる。アンナマリアとミリアムとシェーンはボランティアに借り出されることになっていた。
午前中から準備をし、全てが揃ったのは参加者集合時間の三十分前だった。
その間、三人はもちろん顔を合わせていたわけだが、忙しすぎて明日のハロウィンパーティーの話をしている暇はなかった。
「いやぁご苦労だったねぇ」
もう冬はすぐそこである。参加者はもちろん厚着をしているし――年配の天文ファンや小さな子どもたちの中には手袋や帽子を被っているものもいた――担当の教授は白衣の上にダウンのジャケットを着込んでいる。
教授は一通りの講演を終え、望遠鏡がある大学内の天文台に参加者を案内し終わるとボランティアの学生そう声をかけて回った。――ただし、この時点では仕事は半分も終わっていないのだが。大望遠鏡で彗星を観測した後の、野外での個人観測で彗星に上手くピントを合わせられない人たちに、根気強くつきあうことが今日のメインの活動なのだ。あと、飽きた子どもたちの世話。
教授はなんとなく一緒にいたアンナマリアとミリアムとシェーンのところに来ると――三人を見渡してこう言った。
「そういえば、君たちは明日どうするんだね?」
実は最接近日の31日に観測会を開くという案があったのだが、教授陣の研究としての観測や出張のために今日になったのだ。無論、ハロウィンで人が集まらないだろう、というものも理由にあったが。
三人は顔を見合わせ――ミリアムとシェーンはアンナマリアの顔色を伺った。
「実は、もっと大きな望遠鏡がある天文台の観測会に呼ばれているんだよ。貴重な機会だから、君たちもどうかなと思ったんだ」
「あの、それでしたら、ちょっとむりかな〜〜と思います。先約があるので」
仕方なしに答えたのはミリアムだった。教授は残念そうな顔をする。
「そうかぁ……残念だな。しかし君たちはボランティアに参加してくれたからね。ありがとう。レポートの方も期待しているよ」
そう言うと、教授はくるりと身を返して参加者たちの様子を見にもどってしまった。
アンナマリアは、ミリアムとシェーンと一緒くたにされたことに気づきあっと声を上げかけたが、堪えた。
三人の間に気まずい雰囲気が流れる。
「なぁ、マリー明日の……」
ミリアムに肘でどつかれたシェーンが勇気を持って切り出したのとほぼ同時に子どもの声が響いた。
「ねーねーおねぇちゃーん、すいせーにはしっぽが二つあるってほんとー?」
間延びした声を出した子どもが、アンナマリアの服を引っ張ったのだ。
アンナマリアは振り返って、子どもの視線に屈んだ。
「そうよ、大きな望遠鏡でもう彗星は見た?」
子どもはこっくりと頷く。
「そっか。あのね、ひとつめのしっぽは白くて目立ちたがりだけど、もうひとつのしっぽはちょっと恥ずかしがりやなの。だから見つけられなかったのかもね。もう一回並んで見てみようか?」
「うん!」
アンナマリアはこれ幸い、と子どもに付き添って観測用望遠鏡のところに行ってしまった。
シェーンとミリアムは顔を見合わせ、がっくりと肩を落とした。
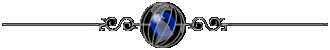
観測会の打ち上げパーティーは後日行われることになっていたので、観測会が終わり参加者が帰ってしまうと、アンナマリアはさっさと帰路に着いた。逃げるように。
彼女の中にハロウィンパーティーに惹かれるものがないわけではない。
美味しいお菓子、楽しいおしゃべり、楽しい仮装。そして、楽しい思い出。
もうそんな楽しいこと、“事件”以来随分していない。それに、ミリアムたちにも申し訳ない気もする。
でも、自分の本分たる学問のための観測はとても重要だ。
――彼女はそう自分に言い聞かせていた。
そこから先を考えようとすると思考が停止する。彼女はいつの間にか伯爵の屋敷に帰り着いていた。
ノッカーを鳴らして家に入れてもらう。リビングに行き着くと、伯爵がホルストの『惑星』を流しながら読書椅子とオットマンに体を預け寛いでいた。
よく見れば、伯爵は手の中で双眼鏡をもてあそんでいた。体は寛いではいるが表情はどことなく不機嫌そうだ。
そんな伯爵を覗き込みながら、アンナマリアは言った。
「……ただいまもどりました」
すると伯爵は青い美しい瞳をすっとあげた。
「お帰り。観測会はどうだったね?」
「皆さん楽しそうでした」
「そうか」
「私、天文台の学芸員もいいかなぁって思って。子どもたちがにこにこしてるのみたら、なんだか嬉しくなって」
「学芸員といえども子どもの相手ばかりできるわけではないぞ」
やはり声にもどこか不機嫌の色がある。アンナマリアは首を傾げた。
「伯爵その……双眼鏡どうしたんですか」
すると、伯爵は双眼鏡を持ち上げた。
「これか。双眼鏡でも見えるというから試してみたんだが……使用人は皆見れたのに、私だけ氷の女王に嫌われたようだ」
氷の女王、という言葉にアンナマリアははじめピンと来なかったがしばし考えて悟る。
「ああ、彗星を見てたんですか!」
伯爵が自分の好きなものに興味を持ってくれたことが嬉しく、アンナマリアは弾んだ声を出した。伯爵のほうはアルカイックなスマイルを浮かべて、言う。
「“わたし以外”はね」
「かなり目立つから、簡単に見れると思うんですけど……」
なぜでしょう、と呟くと伯爵は肩をすくめた。
「さてねぇ……」
アンナマリアは笑うしかない。
「もし、良かったら私の望遠鏡で見ますか?今日はまだ見えると思います」
すると、むくれていた吸血鬼の顔がぱっと輝いた。
「これはこれは、ウラニアに直接指導していただけるとはありがたい!」
「だから天文の女神じゃないですってば」
伯爵はみるみる機嫌がよくなった。ひょいと体を起こし、読書椅子に腰掛ける形になった。
「なんだか、わたしだけ見えないとなると腹が立ってね……。ところで、どこから見るんだい?さっきは二階のベランダから見てみたんだが、高い方がいいと思ってね」
「ここは街の光が届くから、見るならやっぱり森の向こうの広場がいいと思います。
ついでに、一応今日の観測記録をとってもいいですか?大学の天文台の観測記録は教授からもらえるんですけど」
「それは構わないが、『もらえる』とは?」
「ええ、今日夕食も学食でしたし、観測定時にはボランティアの最中だったので。
定時の分を貰うことにしたんです」
その言葉が終わると伯爵は立ち上がった。立ち上がった伯爵は背が高く、アンナマリアを見下ろすほどだ。
「そうか、ではやはり、自分で観測しなくとも問題ないのではないかな?」
伯爵が言ったのは、昨日の「世界中の人が観測している」と言う話だった。
アンナマリアはなぜかギクリとさせられた。
「記録が手にはいれば、明日はハロウィンパーティーに行ってもいいのだろう?」
「でも私、最接近日には彗星を見るって決めたんです」
少し迷いを含んだ声で、アンナマリアは答えた。伯爵はその返答にかりかりと頭をかいた。
「……頑固だなぁ、頑迷と言ってもいいかもしれん。本当は行きたいんじゃないかね、楽しいパーティー」
アンナマリアはぶんぶんと勢いよく首を振った。
「私の本分は勉強です!遊びよりも」
「いや、青春には遊びが必要だと思うが……それに友人も君のその変な頑なさを心配してるんではないかね」
アンナマリアはまたぎくりとしたが、こういって切り抜けた。
「そんなに意地悪なさるなら、私、伯爵が彗星見れなくてもしりません」
伯爵は昨日に続いてまたしても降参した。
「マーサに紅茶をポットに入れさせよう。寒いからな。……やれやれ、君は望遠鏡の準備をしてくれるかい?」
もちろん、と頷いたアンナマリアに伯爵はため息をついた。
「わたしは外套を着てくるよ。森の手前までダドリーに馬車……、じゃなかった、車を出させよう。その方が早い」
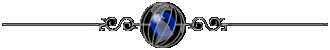
車を降りると伯爵はアンナマリアが大事に抱えていた天体望遠鏡を引き取り、ざくざくと森の中へ入っていった。案内もないのに迷いなく進んでいくその足取りにアンナマリアは慌てた。車を運転してきたダドリーは紅茶を入れたポットと簡易のティーセットが入ったバスケットを大事に抱えて二人の後ろについていく。
「伯爵!場所わかるんですか?それに、森の中は暗くて危ないですよ」
「わたしを誰だと思っているんだ?」
伯爵は本当に心配しているアンナマリアに笑って見せた。そこではたと、彼女は伯爵が吸血鬼だったことを思い出した。彼は彼女の前で血を啜ったりしないので、忘れていたのだ。
空を飛ぶように跳躍したり、などは出会った当初はしていたが最近はさっぱり見ていない。
少し前に彼女は「なんか伯爵って吸血鬼っぽくないですね」と言ったものだが、彼は「……吸血鬼っぽいことをしたら君は嫌がるだろう」とにべもなく返したのだった。
やがて、いつもアンナマリアが歩くよりも早く、森の向こうの広場にたどり着いた。
そこは、正確には“森の向こうの”と言うよりも“森の中にぽっかりできた”広場というような場所だった。
「……この広場も少し狭くなったか」
広場をぐるりと見渡して伯爵は言った。アンナマリアは目印をつけておいた場所に天体望遠鏡を立て、方位を測り、望遠鏡を覗き込み、ノートに時間と彗星の位置を記録する。
「狭くなった、ですか?」
作業をしながら聞くと、伯爵は頷いた。
「森が広がったな」
「そうなんですか……おかげで、街の明かりがさえぎられて助かります」
「なるほど。しかし、このくらいの広さだったら隠遁用の小屋が建てられそうだ」
「また変な噂立ちますよ……」
アンナマリアが望遠鏡を微調整しながら言った。そして、ある星空の一点を望遠鏡に見つめさせて、伯爵を振り返った。
「見えますよ、ほら」
伯爵は身をかがめ、接眼レンズを覗き込んだ。そこへダドリーがやってきて、アンナマリアに紅茶を手渡す。
「ありがとうございます」
「私も少し、見せていただいてもいいですかな」
「ええ、どうぞ」
「見えたぞ!なるほど、確かに氷の女王だ」
伯爵が身をかがめたまま言った。
レンズの向こうには、長く白い尾を引く、コマの青白い、しかし美しい彗星が見えた。
白い尾はまるで不吉の象徴のようにひょうひょうと音を立てていそうだ。かつて彗星は凶兆の証だったが、マリアンナはそれに納得する思いだった。冷たい青と雪に似た白さ。彗星の持つその色は、冷徹な女王にもみえる。
男性ばかりが政の中心にいた昔の時代では、彗星がわがままな女性にみえたのかもしれない、とアンナマリアは思っている。そう、男たちは気まぐれに振り回されることを恐れたのだ。
「しっぽが二本見えませんか?青っぽくて薄いので、見えにくいかもしれませんが」
「白い尻尾よりすこし斜めに延びているものか?」
「それです。正確には青いほうが“真っ直ぐ”、なんですけど」
伯爵は接眼レンズから顔を上げて空を見上げた。そして夜空と天体望遠鏡を見比べる。
「ちょっと長い点にしか見えんな。よく人間はこんなものを思いついたものだ。
……ダドリー」
伯爵は執事を呼び、二人は場所を変わった。
「私は彗星とは尻尾が一本しかないと思っていたのだが……あの青色の尻尾はなんだい?
目の錯覚か?」
「イオンの尻尾なんです。白いのは塵でできてて、種類が違うんです」
「イオン?」
アンナマリアが説明しようと口を開けかけると、伯爵は手を挙げた。
「科学は苦手だ……。そのうち理解したいとは思うが、今日はロマンだけ感じさせておくれ」
アンナマリアは笑って説明を引っ込めた。
執事のダドリーが接眼レンズから顔を上げる。
「少し動いてますね」
「あ、気がついたんですね」
すると、伯爵がびっくりした。
「わたしは気づかなかった」
ダドリーは黙ってまた位置を変わる。そうして執事はアンナマリアに声をかけた。
「思ったより速い速度で動いているんですねぇ。それにしても、私は宇宙を見ていると薄ら寒くなるんですよ、火星の写真など、怖くて一分も見ていられません」
その言葉にアンナマリアは目を見開いた。
「そうなんですか?」
「はい、たぶん、存在が大きすぎるのでしょう。ただ、土星は見れます。あれは芸術品ですから」
ダドリーの最後の言葉に、アンナマリアはなるほどと笑った。確かに、土星は美しい。
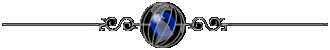
やがて屋敷にもどるころになり――今度はアンナマリアが先行し、自らで天体望遠鏡を抱えて行った。そしてアンナマリアが広場を出かけたところで、伯爵は立ち止まり広場を振り返った。
枯れた下草が、足下で乾いた音を立てる。それを見下ろし、伯爵は言った。
「……ダドリー」
「はい、ご主人様」
「明日の夕暮れまでに、ここの下草をそれなりに整えておけ」
「はい」
「それから……ああ、これは、アンナマリアが眠ってからにしよう。大事な話だ」
「はい、かしこまりました」
そして二人は、先に行ってしまったアンナマリアに追いつくために、歩き始めた。
|