|
「ご主人さま、こんなものが届きましたが……」
ある日の夕方のこと。起きてきたばかりの伯爵に、新聞――朝刊と夕刊両方――を手渡したダドリーは同時に、A4ほどの大きさのある封筒も伯爵に手渡した。
「なんだ?」
郵便物などめったに届かない。伯爵は眉をひそめてそれを受け取った。
「どこかの地上げ屋が土地を売れとかいうのではないだろうな……」
伯爵相手にそうそう喧嘩を売ってくるものもいないのだが、万一の可能性を口にして伯爵は封筒をひっくり返した。
そこには、二匹の蛇が捲きつき頂点に翼を広げた鷹が止まる杖が意匠された立派な封蝋があった。なんと古風な、と言いかけて伯爵は口を閉じた。
「“ケリュケイオン”の印だ――宮廷の医療院の印だな」
「……ご主人さま、ついに健康診断に引っ掛かられたのですか?」
ダドリーが思わず訊ねると、伯爵はまたもや眉を寄せた。
「運動もしているし、食事にも気をつけているのだがなぁ……」
ケリュケイオン――それは、古代ギリシアの神話の伝令の神ヘルメスの象徴である魔法の杖だ。しかしかの悪戯好きな神の手に渡る前は、太陽神にして医術の神アポロンの持ち物であったという。で、あるからして、ケリュケイオンの印は人間たちの間でも医療機関のシンボルとして用いられることが多々ある。
伯爵はペーパーナイフで封を少々乱暴に切ると、中から手紙を取り出した。
ダドリーは黙って控えている。しばらくして、伯爵がひどく低い声を出した。
「……ダドリー、これはどうやら、わたしの健康問題よりも深刻だぞ」
「はい?」
首をかしげる忠実な執事に、伯爵は無造作に書類ともいえる紙束を手渡した。
そこには、こうあった。
『――この実験を知る高位の方々すべてにこの書類をお送しております――
“転化”実験中のダンピールが脱走いたしました。
つきましては、皆様のご協力をいただきたく思います。
詳細は、以下に――』
そして、次にその“ダンピール”プロフィールが記してあった。それから、その隣に写真が一葉。
それは闇のような黒髪と、まるで星を散らすかのようなラピスラズリ色の瞳が印象的な儚げな女性のものだった。
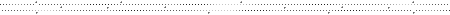
さて一方アンナマリアはその日、行きつけのカフェでミリアムとひとしきりどうでもいい話を三時間ほど続けた後、やっと夕日に気づいて家路についていた。
ミリアムと別れ、小さな路地を最寄りのバス停に向かって歩いて行く。
あたりはオレンジ色に満ちていた。
そして、歩くことしばらく。
人気のない路地に、彼女はソレを見つけた。
「あれ」
それは、道端にうずくまるように座っていた。建物の壁に寄り掛かるその姿は遠目にも具合がわるいのだとよくわかるほどであった。
あたりに人がいないのを見ると、アンナマリアは小走りに駆け寄った。
「大丈夫ですか?」
そう言って屈むと、それは顔をあげた――アンナマリアよりも少し年下のような、幼い印象のある女性だ。
それに、深い深い青色をした瞳。夕日に輝く瞳は、――確かに不調そうではあったが――まるで淡く昼の余韻を残す夜空を切り取ったかのような色をしていた。アンナマリアは一瞬だけ、その瑠璃色の瞳に見惚れてしまった。
彼女は膝の間になにやら不思議な形をしたハードケースを置いて、それを大事そうに抱えている。
「だいじょうぶ……」
女性はそう言った後、うっと口元を押さえた。まるで吐き気に襲われたかのようだった。
「……じゃないです……」
女性はそう言うと、横に倒れこむようにぐらりと傾いだ。アンナマリアが慌ててそれを支える。
「具合悪いんですね、家は近いんですか?」
女性は一度、首を振る。
良く見れば、女性はぜえぜえと息切れのような呼吸を繰り返している。顔色は真っ青を通り越して紙のように白く、だが体温は高い。
――おかしい。
アンナマリアはさすがに異常事態だと気づいて、携帯電話を取り出した。
「病院いきましょう。救急車呼びますね」
念のために、と伯爵に入れさせられていた消防署の番号が役に立ちそうだ。アンナマリアが通話ボタンを押そうとすると、女性が手をのばしてその携帯電話を掴んだ。
真っ白な顔と、熱い手。
アンナマリアが思わず驚いて手を止めると、女性が言った。
「病院は……だめ……」
「えっ……でも」
「だめ……」
女性はそれだけ言うと、アンナマリアにもたれかかるようにして意識を手放した。アンナマリアはあわててそれを支えながら、
――どうしよう。
と思った。だが、悩んでいても事は進まない。
彼女は再び携帯電話に向きなおって、ある番号を選び出した。
「まさかあのようなお電話をいただくとは思いませんでした」
珍しく使用されることになった客人用の寝室で、ダドリーはアンナマリアにつぶやいた。
そう、彼女が選んだのは伯爵の家の電話だったのだ。
電話に出たダドリーにアンナマリアは人が倒れていること、そしてその人が病院に行きたくないと言っていると告げた。
するとダドリーは伯爵に意見を求めた。伯爵の方は
「道端で死なれても困る。病院に行くのが嫌ならこちらに医者を呼べば良かろう」
と言ってダドリーとその息子である運転手を現場に向かわせた。
そしてアンナマリアがヤキモキすること十数分――颯爽と現われた黒い車から執事とその息子の運転手の二人が現れ、倒れている女性を運ぼうとした。
だがここでちょっとした問題が生じた。
女性が抱えていた不思議な形のハードケースを放そうとしなかったのだ。しばらくの格闘の末、ダドリーの息子がそれと彼女を引き剥がすのに成功するとアンナマリアはダドリーを手伝って彼女を車に運び込んだ。
そして、今に至るのである。
女性の眠るベッドの傍らには呼びつけられた屋敷にある薬草園管理者のシビラと給仕頭のマーサが屈みこんでいる。
シビラは女性の脈を見、頬にふれ、喉に触れた。それから彼女はしばらく自らの形のいい顎をつまんでいた。
「なんの病気でしょう?」
マーサが心配そうに言うと、シビラは冷静な口調で言った。
「病気ではないわね。でもひどく体が弱ってるわ、それにこの子……」
彼女はちらりとアンナマリアを見た。アンナマリアは意味がわからずに首をかしげる。
そこへ、伯爵がやってきた。
「どうだ、シビラ、手に負えそうか?」
伯爵がそう言うと、シビラはすっと立ち上がり彼に歩み寄るとその腕をひっつかんだ。
そしてきょとんとした顔の伯爵を廊下に引きずっていく。
バタンとドアが少し乱暴に開き、そして神経質そうにパタンと閉じた。
しばらく後。
伯爵がシビラを伴って戻ってきた。
伯爵は無言でベッドに近づくと、眠る謎の客人を――どこか冷徹な目で――見下ろした。
それから、アンナマリアを振り返る。
「彼女、日暮れに路地に倒れていたのだね?」
「倒れていたというかうずくまるというか……」
それから彼はダドリーに言った。
「彼女、何か身分を証明するものは?」
「荷物でしたらトートバックと、それから、アレを」
ダドリーは彼女の荷物が置いてある部屋の一角を指差した。そこには、変な形をしたハードケースが置いてある。一抱えもありそうな、大きなものだ。ハードケースは黒で、二本のショルダー・ベルトがつけてあった。背負うこともできるケースなのだ。
「……なんでしょうアレ」
マーサが言うと、あっとアンナマリアが声を上げた。
「楽器のケースじゃないでしょうか。学校で背負っている人を見たことあります」
アンナマリアが言い終わらないうちに、伯爵はそのケースに大股に歩みよった。
それからケースの脇に屈みこむ。
彼はケースを慎重に横にすると、幸いにも鍵がかかっていなかったケースの留め具を外した。
「あの、伯爵?」
アンナマリアが思わずその背中にそっと歩み寄って呟くように言うと、伯爵は彼女を振り返って手でケースの中を示して見せた。
「サクソフォーンだ」
中には、ピンクゴールドに輝く管楽器が横たわっていた。
種類としては木管楽器に属し、1840年代に誕生したそのまだ若いと言えるその楽器は、サックスという愛称で親しまれている。独特の曲線を有するその形は、素人目にも「カッコイイ楽器」と映ることが多く人気が高い。アンナマリアもその楽器を知っていた。
「ああ、それサックスのケースだったんですか。どうりで変な形だったんだ……」
「ピンクゴールドの楽器だとすると、金や銀のものよりも高価なものだな」
伯爵はそれだけ言うと、丁寧にケースを閉じ今度はトートバックに手を突っ込んだ。
アンナマリアが唖然としている間に、彼は財布を探りだした。
「身分を証明するものがあるはずた」
伯爵は躊躇することなく、財布を開けた。そして一枚のIDカードを探し当てた。
それから静かに控えていたシビラに視線を送った。
「大当たりだ、シビラ。ダドリー、あの書類を持って来ておくれ。そう、今日届いたアレだ」
主人に言われてダドリーはまるで執事の見本を見せるかのように機敏にさっと踵を返した。
マーサはというと、奇妙な客人のために使った道具一式をどこか困ったような顔で片付け始めていた。
「なんなんです?」
奇妙な雰囲気に包まれ始めた部屋の中で、アンナマリアが思わず問うと、珍しいことに伯爵とシビラが顔を見合わせた。数秒後、シビラは肩をすくめて見せた。伯爵はため息をつき、アンナマリアに向きなおった。
「アンナマリア、驚かないで聞いてくれ」
「なんなんです?」
アンナマリアが眉をしかめながら聞くと、伯爵はベッドに横たわる女性をそっと示した。
「彼女は“ヒト”ではない……“ダンピール”、――いや、女性だから正確には“ダンピーラ”だな。人間と我々吸血鬼の間に生まれた存在だ」
ダドリーが戻ってきた。
その手には、夕方伯爵の手元に届いたあの書類があった。
伯爵はその書類を受け取り、その中の一枚を取り上げて要領を得ない顔をしているアンナマリアに手渡した。
そこには、確かに横たわる客人の写真と――彼女のプロフィールがあった。
『コンスタンツェ・アドリオン
20歳、混血児(ダンピーラ。母は“高貴なる人”)。13歳より血中異常により、病弱。
現在その対処として“転化”実験に協力す。
XX日明け方、医療院特別治療室から脱走。なお、現在特殊治療中につき体力・免疫力低下中。ごく脆弱な細菌に感染した場合でも死亡の可能性あり』
|
![]()