|
その数時間後のことである。
国産の実用一辺倒の四輪駆動車がやや法定速度を超えた速度で、伯爵の屋敷の門をくぐった。だがその車を操る人物のドライビングテクニックは相当なものらしく、砂埃をあげながらもきっちりと玄関前2メートルのところに華麗に停車した。
停車した車から降り立ったのは二人の男――うち運転席から降りた一人は黒い髪と褐色の目を持ち、いかつい体に長身だった。目は切れ長で、さらにそこに眼鏡をかけているので厳めしい雰囲気はぬぐえない。加えて男は黒ずくめの格好に、アタッシュケースを携えていた。総合的に見てその男は、友好的という単語とはほど遠い印象だった。
もう一人は、その男とは全く対照的だった。
波打つ金の髪は異教の美男神のようで、顔は柔和だ。瞳は美しい緑色で、いかにも優男と言った感じだった。だが身長は、がっしりして長身のもう一人と比べるとやや低いという印象を受けた。線も細く、もう一人と比べればどこか頼りなげですらある。
しばらく屋敷を見上げていた二人だが、最初に足を踏み出したのは黒髪の男の方だった。金髪のほうは、おずおずという感じでついていく。
ノッカーに手をかけたのも、やはり黒髪のほうだった。
ゴン、ゴン。
重い音が響く。扉を開けたのは、いつも通り執事のダドリーだった。
その執事にすっと二人が頭を下げる。――慇懃に。
「コンスタンツェ・アドリオンがここにいると連絡をいただきましてまいりました。
わたくしは医者のジークフリート・フォン・エルレンマイヤーと申します」
「医療院のお医者様ですね」
ダドリーはにこりと笑ってそう言った後、ふと黒髪の男の後ろに所在なげにしているもう一人の男に目をやった。
黒髪の男はちらりとそちらを見やると、
「……コレは、わたくしのパートナーのルートヴィヒ・フォン・フェルンバッハといいます。
お邪魔してもよろしいでしょうか」
「ええ、もちろんです。少しお急ぎください」
少しちぐはぐな印象がある黒髪と金髪の二人の男はダドリーについて屋敷に入った
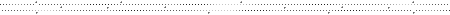
アンナマリアとマーサは、奇妙な客人ことコンスタンツェ・アドリオン嬢に付きっきりになっていた。伯爵とシビラはなにやら話があるのかどこぞへと引っ込んでしまった。
「……ダンピール、ですか」
「はい、わたしも初めて見ましたよ。人間と吸血鬼というのは、大変相性が悪くてもし“混血”が生まれてもすぐに死んでしまうとか」
「そうなんだ……」
「ここまでお育ちになられたのは、ほとんど奇跡かと思いますよ」
マーサは優しくコンスタンツェの額を撫でながら言った。コンスタンツェは相変わらず苦しげに息をしている。
綺麗な子だなぁ、とアンナマリアは思った。ここまで具合が悪くなさそうだったら、きっととびきりの美人に違いない。頬にはやわらかい朱がさし、微笑めばあの印象的な瑠璃色の瞳がきらめいて誰をも魅了するに違いない。だがこの子は吸血鬼と人間のハーフだという。それを思い、アンナマリアはその美しさはやはり吸血鬼の血に起因するのだろうか、とふと考えてしまった。
そこへ、ノックの音が響いた。
「お医者様がいらっしゃいました」
マーサがさっと立ち上がって、ドアを開けるのと、なにやら一部金のものが飛び込んでくるのはほぼ同時だった。
「Meine Prinzessin !」
ソレはアンナマリアをやり過ごして、コンスタンツェの枕もとに飛びつくようにたどり着いた。そしてしきりに名前を呼ぶ。
アンナマリアが唖然として見やると、それは、金の髪の男だった。どうにも優男で、医者には見えない。シャツの胸元は、空いているし。
「どけ、馬鹿者が」
アンナマリアが「静かに」と思わず言いそうになる直前、低く怒りを含んだ声が降り注いだ。振り仰げば、アタッシュケースを抱えた黒髪の厳めしい感じの眼鏡の男が金の髪の男を睨みつけていた。アンナマリアが思わずぎょっとして場所を開けると、彼はそこに無言で入り込んだ。だが、金の髪の男はどかない。
かばうように、コンスタンツェの上に覆いかぶさる。
「殴らないで!」
「俺がその子に手をあげたことがあるのか?」
怒ってはいるが、同時に冷静な声だった。金の髪の男は、一つ頷くと、しぶしぶと言った感じでコンスタンツェの上から退き、立ち上がった。
黒髪に眼鏡の男――ジークフリートと名乗った医者は、テキパキとコンスタンツェの脈を測り、診断に必要な部位に触れていく。そして、彼女の瞼に触れたとき、コンスタンツェがついに目を覚ました。
「ジーク……おじさん……?」
すると、ジークフリートは先ほどの金髪のルートヴィヒに対する態度からは信じられないくらいの優しい声を出した。
「コンスタンツェ、目を覚ましたね。よかった」
「お説教は後だよ!」
二人に向かって、金髪のルートヴィヒが少し甲高い声を出した。ジークフリートが肩越しにそれを睨みつけると、コンスタンツェも彼に気づいたようだった。
「ルートヴィヒ……」
「ああ、心配したんだよ、僕たちのお姫さま。よかった、見つかって」
「少し黙っていろ」
ジークフリートがにべもなくそう言うと、ルートヴィヒは大人しくなった。
ジークフリートは再びコンスタンツェの体に触れる。まるで大切なものを労わるかのような手つきだった。だが繊細なガラスを扱うかの如く怯えた手つきではない。どこに触れれば、どんな情報が得られるのか知っている手つきだった。
「熱があるな」
「……はい」
ジークフリートはこつんとコンスタンツェの額に自分の額を合わせた。従順な声を出した娘に、ジークフリートはそのままの格好でささやく。
「外に出てはいけないと言っただろう。ひどかったら死んでいたぞ。いや、もう少しお前に人間の血が濃く出ていれば、外の空気など一分も耐えられなかった。君の母上の血に感謝しなさい。
なぜ無茶をしたんだ」
「……ごめんなさい」
コンスタンツェは理由を問う声に謝罪の言葉を発しただけだった。
「お説教は――」
「後にする。治療が先だ」
ルートヴィヒの言葉を制して、彼はアタッシュケースを開いた。そこには聴診器やペンライト、注射器など一しきりの医療道具がそろっていた。
彼は一、二本の注射を彼女に施すと、簡易の酸素吸入器のマスクを彼女の口元に持っていった。手をあげて嫌がる娘に、医者は諭すように言った。
「奇麗な空気を吸わなければ、肺がやられてしまう」
娘は唯々諾々と従った。それからジークフリートは独り言のようにつぶやいた。
「車からボンベと空気清浄機を――気休めかもしれんが、持ってこよう」
「我が家の空気はそんなに汚れているかねぇ」
その独り言に、応答があった。驚いて一同が振り返ると、そこにはこの家の主こと、“伯爵”がいた。
その姿を見たとたん、黒髪の男と金髪の男が身を固くするのが感じられた。伯爵はアンナマリアが見たこともないような尊大な態度でベッドに歩み寄った。
見ればもともと膝まづいていたジークフリートはともかく、ルートヴィヒの方も膝をつき、頭を垂れている。伯爵はコンスタンツェの枕もとにたどり着くと、彼女をそっと見下ろした。
「気分はどうかね、お嬢さん」
「……あまり」
コンスタンツェは控えめに答えた。それから、ルートヴィヒと同じように伯爵に向かって頭を垂れているジークフリートを不安そうに見やる。
だが答えたのは伯爵だった。
「気になさらんでいい。話はあとで聞きなさい」
「……はい」
コンスタンツェは素直に答えた。そんな彼女ににっこりと笑いかけた後、伯爵は辺りを見回し、
「ジークフリート・フォン・エルレンマイヤー、我が使用人たちに指示を出したらわたしの書斎に来たまえ。それからそっちのも」
そっちのも、と呼ばれたルートヴィヒが飛びあがらんばかりに身を震わせた。
だがジークフリートはすっと顔をあげ、異を唱えた。
「……すぐにこの者を病院へ戻したいのですが」
「それには私は異論がある。それにお嬢さんは先ほどより落ち着いているね。従いたまえ」
それは、アンナマリアが聞いたことのないほど冷たい、命じる声だった。
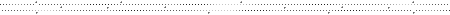
十数分後、伯爵の地下の書斎へとやってきた男二人がしたことは、まずその場に膝まづくことだった。
それから、それぞれが身分を改める。
「この度は恐れ多くも“マグヌス・パテル”のご尊顔を拝見できたことを、存外の喜びといたします。
わたくしは、ジークフリート・フォン・エルレンマイヤー。宮廷の医療院にて医者をさせていただいております」
「同じく“偉大なる父上”にお近づきになれたこと、心よりうれしく思います。
わたくしは、ルートヴィヒ・フォン・フェルンバッハと申しまして、宮廷にてオルガニストを務めさせていただいております」
「オルガン奏者?」
伯爵はわずかに眉をあげた。そして、金髪の男に率直に疑問を投げつけた。
「……君、その医者のパートナーというからてっきり看護師か助手かと思っていたのだが」
すると、二人は少し顔を見合わせた。
「……このようなことを“偉大なる御方”の耳に入れること、少々はばかられますが。彼と私は“生活上の”パートナーなのです」
そうはっきり言い切ったのは、ルートヴィヒの方だった。ジークフリートは無表情である。
伯爵はしばし間を置き、
「……成程、成程。」
と言って顎を撫でた。それから伯爵は二人を見比べ――
「……。生活上のパートーナーをなぜ連れてきたのだ?必要なかろう?」
といささか警戒した口調で医師であるジークフリートに言った。
するとジークフリートが苦り切ったような顔で言った。
「わたくしは置いてきたかったのですが。
コンスタンツェ・アドリオンはわたしの患者であるとともに、わたしの被後見人でもあります。生活はこのルートヴィヒを含めた三人で行っており――というか、彼は彼女の最初の音楽教師でもありました」
すると、ルートヴィヒはこくこくと数度うなづいてみせた。
「成程。荷物にサクソフォーンがあったが、彼女はいま音楽院生であったな。」
「左様にございます」
ジークフリートは慇懃にうなづいて見せた。それを見てから、伯爵はふむ、と言った。
「わたしがそなたらをここへ呼んだのは他でもない。
そのコンスタンツェ・アドリオン嬢のことで、だ」
そこで伯爵は二人を見まわし――ひた、と医者であるジークフリートを見据えていった。
「彼女は“転化”被験者だということだが――それは彼女の望んだことなのか?」
「……もちろんです」
返答にはわずかな間があった。伯爵はその間を聞き逃さなかった。
「ヒトから我々ヴィータになることを、か?」
伯爵は吸血鬼、という呼称を使わなかった。ヴィータ――vita、もはや耳慣れぬ、学術の世界とわずかな好事家たちの間で使われる言葉にある単語である。他の単語と同じようにいくつもの意味を持つ言葉だが、ここでは「命」を――そして、ヒトより「長い命をもつものたち」を指す言葉として使われている。
「彼女はもとより、ヒトではありませんでした。――ダンピーラという意味だけではなく、心も、生活も」
答えたのはルートヴィヒだった。線の細さも相まって、頼りない生き物だ、と思っていた伯爵は眉を上げる。
「ほう?」
伯爵が興味深そうにルートヴィヒを見やると、彼は一瞬ひるんだようだったが話を続けた。
「彼女の母は我々ヴィータ、しかも“高貴なる人”――貴族です。父親はヒトですが、彼女は父の顔を知りません。そして、彼女は母の死後、このジークフリートに育てられました」
呼ばれたジークフリートはぎろり、という音が付きそうな視線でルートヴィヒを睨んだ後、彼の言葉を引き取った。
「マグヌスもご存じのように、混血は歓迎されません。それが、私生児ならなおのこと。彼女の母の一族は、彼女の母が死んだ後、彼女をたらい回しにするところでした」
「私生児?」
伯爵が再び眉を上げた。もちろん、人と吸血鬼の道ならぬ恋の末に生まれた子というのならその可能性も高いだろう。しかし、近年ではどうやってか――19世紀以来、人間側の協力者を得て行われ続けている、人間の耽美主義的側面を利用した啓蒙活動の結果だろうか――吸血鬼を化け物と恐れない人間が増え、また迫害の機会がほぼなくなったためにヒトに親近感を抱く吸血鬼も多く発生したため、いわゆる“合法的”な結婚がちらほらと発生しているのだ。それでも、ごくわずかではあるが。
コンスタンツェは混血のためか、非常にゆっくり年をとる吸血鬼とは違い、人間と同じく一年に一つずつ年をとっているようだった。つまり彼女は見た目の通りの年月を生きており、彼女が生まれたのはちょうど20年前――本人たちの間で様々な問題にどう折り合いをつけるかどうかはともかく、“異例”がわずかながら認められてきた時期であるはずだった。
「引き離された恋の落とし子、というわけか」
新しく異常な恋愛――それを認めないものもまた多い。そこに伯爵が想いを馳せていうと、ジークフリートはわずかに目を伏せた。
「彼女の母にはヴィータの婚約者がおりましたので」
「……成程」
伯爵は顎をなでた。
「さしずめ、君がその婚約者だったというところかな――いや、外れていたら失礼」
ジークフリートは返事をしなかった。肯定の沈黙だろう。その沈黙をしばし部屋に漂わせてから、未だに臣下の礼をとってひざまづいたままの二人に気づいた伯爵は、鷹揚な仕草で椅子をすすめた。
「それで、本題に戻すが。彼女がダンピーラからヴィータへの転化を望んでいたならどうして逃げ出したのかね」
ビロードの布張りがされた二人掛けのソファに浅めに腰かけた二人は、まだ緊張が解けないようだった。そんな二人の前にある大理石のローテーブルを挟んだ主人の席で、伯爵はゆったりと身をくつろがせる。
Magunus Pater――“偉大なる父上”。それが吸血鬼の間での“伯爵”の呼称だった。二千余歳を数える伯爵は吸血鬼の中でも最古参だ。百歳や二百歳の吸血など若造どころか幼児と言われても仕方ないほどの時間を彼は重ねていた。だからこそ――いや実はそれだけではないのだが――、ジークフリートとルートヴィヒは先ほどから敬語と――どこか怯えた――慇懃な態度を崩さない。
そのせいなのか、コンスタンツェの話をしていてもどこか上滑りをしている感覚が伯爵にはあった。
「肩の力を抜きたまえよ。君たちがわたしをどう思っているかは知らんが、目下わたしはコンスタンツェ嬢のことが気にかかるのだ。“転化”は我々とヒトの何らかの進化につながるかもしれない新しい技術であるが、それに我が同胞の子が悪戯にもてあそばれるのはあまり気持ちのよいものではないのでね」
「もてあそぶなど……!」
僅かに語気を強めてジークフリートが反論した。ルートヴィヒが驚いて彼を肘で小突くと、医者は我に返ったようだった。一呼吸置いて、彼は背筋を伸ばして語り始めた。
「ご存じのように、ダンピールあるいはダンピーラが、長命を得ることは稀です」
その口調は科学者じみていて、冷淡に病状を告げる医者のものでもあった。
「ヒトとヴィータの間にあるごく小さな遺伝子的な差異は、ダンピールにとっては致命的な欠陥となりえます。血液中の成分、内臓の機能などの差異は、一つの体にあってはお互いを異物として認識し、攻撃し、やがて己を壊し死に至らしめるまでの強い反応となるのです」
「ガンのようなものか」
「ごく簡単に言えば、似ています。――コンスタンツェは幼少時はそれほどでもありませんでしたが、第二次性徴期から体に異常をきたすようになりました」
「それまでは普通の子でした。駆け回ったり、歌を歌ったり。でも段々体が弱っていって……」
伯爵はルートヴィヒら目をやった。
「しかしサックス奏者ならば、ある程度の体の頑丈さは求められるだろう?肺活量もいるだろうし」
「健康だったころに肺を鍛えるためもあって、はじめたのです。結果彼女に合っている楽器でしたが」
そう言った後ルートヴィヒはそわそわと体を動かした。
「僕は失礼してもかまいませんでしょうか……居てもマグヌスのお役にはあまりたたないと思うので」
「構わん。お嬢さんについていてやれ。知らない者ばかりでは不安だろう」
伯爵がまた鷹揚な仕草でドアを示すと、ルートヴィヒはさっと立ちあがり最敬礼した後やや早い足取りでドアへと向かい、廊下へと消えた。
それをしっかりと見送ってから、伯爵はジークフリートに向き直った。
「コンスタンツェの体の変化は、おそらくは、初潮と関係ある考えております。
混血児の場合、調査の結果男子の死亡率は生後間もなくが多く、女子では初潮の前後が多いのです。男子については詳しい追跡が不十分ですので、これは――」
ジークフリートが説明中にも関わらず、伯爵は軽く片手をあげて彼を制した。
「医学的な話も興味深いが、今わたしが聞きたいのはそういうことではない」
穏やかだが断固とした口調に、ジークフリートは口を紡ぐとわずかに唇をかんだ。伯爵は質問を繰り返さなかった。
「コンスタンツェがなぜ逃げ出したのか――わたしにはわかりかねます。このままだと彼女はゆるゆると死ぬしかない。それを承知の上で“転化”の実験に協力してくれたのです。
“転化”には――人工的に彼女の体の抵抗力を落とす必要がありました。その危険性も伝えました。なのになぜ――逃げたのか」
ジークフリートの声は苦悩に満ちていた。伯爵は顔をうつ向かせ頭頂部を見せる年若い吸血鬼を眺めた後、ゆっくりと背もたれに身を預け天井を見上げた。
「死に急いだわけではないだろう」
幾星霜の年月を重ねた老人の声のような声音で、伯爵は若者に言った。ジークフリートが顔を上げ、偉大なるものを見つめた。
「死を覚悟した者というのは――その身一つで赴くものだ。トートバッグに財布や身分証明書を入れて、あまつさえ重い楽器など持ち出さん。家出という方がしっくりくるな」
ジークフリートが顎を引いた。伯爵が顔を戻して若者を見やると、若者は幾分得心したような表情をしていた。
「それに、家出というにも彼女の所持金はいささか少なすぎたな」
伯爵が少し苦笑して見せると、苦悩していたジークフリートもさすがに眉を上げたのだった。
|
![]()