|
結局行きと一緒の分乗で、一行は屋敷に戻った。
怒られると思っていた娘二人は身構えていたが、特にお咎めはなかった。
だがその代わり、伯爵とジークフリートの間で一悶着があった。すぐにコンスタンツェを連れて帰りたいジークフリートに、伯爵は疲労回復を優先させ泊っていくようにと言ったのである。ルートヴィヒはどちらの味方もしなかった。
その間に、マーサが娘二人にホットミルクを作ってくれた。何も言わないルートヴィヒは紅茶をもらった。三人が飲み物をすすっている間に、伯爵が勝った。
「見たところ、急を要する容体というわけでもない。むしろ疲労している今無理に移動して、道中で倒れた方が大変だ」
君は意外に強いようだしね、と伯爵がコンスタンツェを上から覗き込んだ。コンスタンツェははいと答えながらもソファの上で身じろぎして、隣のアンナマリアにぴったりとくっついた。伯爵は苦笑して、コンスタンツェの頭をぽんぽんと優しく叩いた。
「わたしも君のサクソフォーンは好きだよ。また聞かせてくれ」
伯爵はそれだけ言うと、地下の自室へと下がっていった。
「……怖いヒトじゃないのね、マグヌスって」
ぽつりと言ったコンスタンツェに、アンナマリアも言う。
「たまに得体が知れないけど」
その言葉に、部屋に残されていた年長の吸血鬼二人はぎょっとしたようだった。
「ゲストルームをご用意いたしますね、何かご要望はありますか?」
マーサが黒髪の男と金髪の男に問う。ジークフリートは考え込んだ後、静かな口調で言った。
「コンスタンツェの部屋に、掛け布団を運んでください。たしか長椅子がありましたよね」
「ジーク?」
コンスタンツェが立ったままのジークフリートを見上げる。ジークフリートは見下ろした。
「容体が急変するかもしれないしな。一緒にいる」
「……怒ってないの?」
恐る恐る、という感じでコンスタンツェが聞くとジークフリートはため息をついた。
「終わったことを喚いても仕方ない。……、と、マグヌスが言っていた」
「受け売りかよー」
ルートヴィヒが言うと、コンスタンツェが笑った。
「では、お部屋はお二つでいいですかね」
マーサがルートヴィヒを見ながら言った。アポロンを彷彿とさせる吸血鬼に、給仕頭は臆した様子もなく、いつもどおりだ。ルートヴィヒはうーんと顎に長い指を添えた。
「僕も一緒がいいな」
「はい、かしこまりました。長椅子なんかよりいいものがありますから、部屋に運ばせましょうね」
「いいもの?」
アンナマリアが聞くと、マーサが空になったカップを彼女から母親のように回収しながら片目を瞑って見せた。
「簡易ベッドです。まぁ、でも二つも入らないかもしれませんから、お二人のうちどちらかには、長椅子で寝ていただくことになるかもしれませんがね」
茶目っけたっぷりにいう給仕頭に、一同は笑った。
「じゃあ、コンスタンツェにパジャマを貸してあげる」
「いいの?」
外泊するつもりがなかったらしいダンピールの娘に、ヒトの娘は言った。
「うん。わたしの部屋に行こうか」
「うん!ありがとう」
寝巻ならお客様用がきちんとありますよ、という野暮なことを給仕頭は言わずに微笑みながら二人の娘の空になったカップをトレイに載せたのだった。
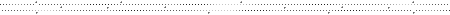
吸血鬼たちは、翌日日が暮れ、その残光が消えて空がようやっと紺色になった頃に発つことになった。コンスタンツェには大きな免疫不全の症状が出ることはなく、また見た目には何か別な病を得た様子もない。ヒトと違う強靭な何かが、彼女の身を助けているのか、はたまた人工的な免疫力低下がそれほど大したものではないのかは、門外漢にはさっぱり分からなかった。
空とコンスタンツェの瞳が同じ色をしている、とアンナマリアは空を見上げて思った。
「それでは、大変お世話になりました」
ジークフリートが頭を下げると、ルートヴィヒとコンスタンツェが遅れてそれを真似た。
コンスタンツェのサックスの入ったケースはルートヴィヒが持っている。ジークフリートとコンスタンツェの間にすったもんだあった末、彼が預かることになったのだ。
「久しぶりに三人で寝ました」
「一緒のベッドじゃないけどね」
そうルートヴィヒと笑いあった後、コンスタンツェはアンナマリアの手を取った。
「本当にありがとう。あなたのおかげだわ。見つけてくれなかったら、死んでたかもしれないし……」
アンナマリアは首を振った。
「当然のことをしただけだよ」
「当然のことができないものも多い」
伯爵が傍らから娘たちを見下ろしながら言った。その目は限りなく優しい。
「さて……宵のうちに旅立つがよい。夜は短い」
そう伯爵が言うと、三人はそろってまた礼をした。そして国産の四輪駆動車の後部座席にルートヴィヒが乗り込み、運転席にはジークフリートが、助手席にはコンスタンツェが座った。エンジンがかかる。アンナマリアが助手席の近くに行けば、コンスタンツェがパワーウィンドを下げた。
「今度わたしの演奏会に来てね!」
「うん、絶対行く!体に気をつけてね」
「ジークがいるから大丈夫」
コンスタンツェはそう言って、窓から手を差し出してきた。アンナマリアがその手を握る。力強い、温かい手だった。
「ほら、マスクをしろ」
ジークフリートが横からコンスタンツェに白いマスクを差し出してきて、どちらからともなく手が離れた。
――確かに大丈夫。
と、アンナマリアは思う。
「出るぞ。……マグヌス、失礼いたします」
「息災を祈る」
見れば、後部座席でルートヴィヒが手を振ってくれたのでアンナマリアも振り返す。金の髪とアポロン然とした容姿のせいで、アンナマリアはどこかの王族に手を振っている気分になり思わず笑いそうになった。
アクセルが踏まれ、エンジンの回転数が上がる。アンナマリアは体を伯爵にくいと後ろへひかれた。車から離れるのを忘れていたのである。
「またね、アンナマリア!」
コンスタンツェが言うのと、車が速度を上げ出すのはほぼ同時だった。
「またね!」
アンナマリアは大きく手を振って見送った。見えなくなったところでやっと手をおろし、傍らの人物にふと尋ねる。
「……治療、上手くいきますよね」
「免疫力を低下させてあれほど元気なら、大丈夫だろう。時間はかかるかもしれないが」
「……牙とか、生えてきちゃうんですかね」
「……、ないだろう、それは」
「ですよね」
珍しく悩ましげな戸惑い声を出した伯爵に、アンナマリアは笑った。伯爵は片眉を上げる。
しかしすぐにその眉を戻して、空を見上げながら言った。
「星が増えてきたぞ。どの季節も夜は冷える。さあ、中に入ろう」
「はい」
伯爵は年若い娘の腰にそっと手を添えて、屋敷の玄関へ向かった。
遠くなりゆく屋敷を肩越しに見つめつづけていたコンスタンツェは、屋敷が地平の向こうに消えてしまうと前に向き直った。そして、運転席のジークフリートを見る。
「ジーク」
「なんだ」
「ごめんなさい」
「まったくだ」
短いやりとりの後、ジークフリートは長いため息をついた。それから道が直線なのを確認してから、ちらりとコンスタンツェをちらりと見た。
「……大丈夫か?」
「少しだけ、だるいかも」
「それもそうだが」
そこへ、後部座席から声がかかる。
「ジークが聞きたいのはそうじゃないよ」
ルートヴィヒは運転席と助手席の間からコンスタンツェを覗き込んだ。
「お父さんのこと」
コンスタンツェは、自分の顔のすぐ近くに並ぶ育ての親二人を見た。ジークフリートは、親しいもの以外には無表情に見える顔をしており、ルートヴィヒはこれとは対照的に分かりやすい心配顔をしている。
「弟がいたのはびっくりしたけど。それだけ、かな」
その言葉に、ルートヴィヒが口を開きかけた。だがそれより早く、運転席から手が伸びて、わっしゃわっしゃとコンスタンツェの髪を乱した。
「もう……」
コンスタンツェは呆れたような声を出して、その手を払いのけようとした。だがその前に、ぼろぼろと瑠璃色の瞳から雫がこぼれ出した。
「ルー、ジーク」
震えながらもしっかりとした言葉で、コンスタンツェは言った。
「ありがとう」
結局、ジークフリートはカーブに差し掛かるまで、被後見人の髪の毛をくしゃくしゃと撫でつづけた。ルートヴィヒは背もたれにもたれて、コンスタンツェとジークフリートをただ黙って見守っていた。
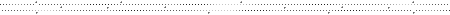
一年半後。
どこぞの劇場で、仰々しい催物が開催される。だがそれはヒトの預かり知らぬことで、着飾った人々はみな長い犬歯をもっていた。
舞台から見て正面の一番良い所に設えてある桟敷席に、赤毛だが豪奢な巻き毛の娘がひとり坐っている。
彼女の右手側には詰襟に腰に古風な剣と銃を吊るした若者が立っている。
左手側には赤いビロード張りの椅子があるが、未だ空席である。下から登ってくる喧騒に、娘は僅か顎を引いた。
その時、桟敷席のドアが開いた。赤毛の娘が見やればまず若者が二人入ってくる。若者は、国際競技会の名誉の旗手が国旗を抱えるときのように二本の手で太い棒を支えている。だが彼らはべつにそれぞれ国旗を掲げているわけではない。二本の太い棒の間には一枚のレースの布が掛けられており、彼ら二人はそれを掲げることで誰かを周りの目から隠しているのだ。――つまり、移動式の簡易の御簾のようなものだ。
だがその御簾も、前方だけから何者かを隠しているだけで、左右と後方には無頓着だ。その替わり、左右と後ろには黒いスーツを着た屈強な男たちが従っている。ヒトの世界風に言えば、シークレットサービスつまりは護衛というやつである。
御簾が赤毛の娘の左手の席の前に進み出た。そして御簾に隠された人物は、その席に座る。
「じい、また顔を隠すのか」
左右は気にしていないので、御簾の人物は赤毛の娘から容易に見て取れた。呆れを含んだ声で娘が尋ねると、くつくつと笑う音がした。
「わたしもとうに年寄りの設定ですので」
赤毛の娘はちらりと御簾を掲げる棒の先を見た。声はそこから聞こえてくる。しわがれた、いかにも老人然とした声だ。
だが、娘の隣、御簾を前にして喋った男は――声よりずっと若い。
マグヌス・パテル――吸血鬼からそう呼ばれる伯爵は、ヘッドセット――インカムを付けていた。マイクを通して老人の声に変換された声が、スピーカーを取り付た御簾の先から響いたのだ。
「“事件”のときにその設定もすでに崩れておろう。なにをいまさら、じゃ」
「知らぬ者もまた多いですからな、陛下」
娘がツンと顎を上げると、伯爵はまたくつくつと笑った。
帝国一の最古参、と言われてヴィータたちが想像するのは、やはり人と変わらない。しわがれ、やつれ、腰の曲がった老人。ヴィータたちの“帝国”のずっと建国以前から生きているという“偉大なる父上”のイメージはまさにそれである。
だがヒトの世で“伯爵”、と呼ばれる実際の“マグヌス”は違った。
黒々とした髪はつややかで、平時は青い瞳は海のようだ。名工が掘り出したとも思える顔立ちや手の造りは干からびた老人の幻想を裏切ることは間違いない。
ヴィータの帝国は、三人目の主を迎えている。建国の荒波を越えた後病に倒れた初代皇帝カーミラ、退位制度を作り出した治世の短い第二代皇帝ラミーカ、そして三代目が“伯爵”の隣に座る赤毛の第三代皇帝ミラーカである。あわせて400年ほどの歴史を持つ帝国で、建国当時から生き続けている古参でも若々しい容姿を保っているものはほとんどいない。マグヌス・パテルの若々しさは吸血鬼たちの中でも異例で異常である。だからこそ、彼は普段御簾の中に身を隠し声を機械的に変えている。
「ここならば下々からは見えますまい」
伯爵はそう言って、御簾を掲げる二人に手を挙げた。御簾が下げられる。皇帝の桟敷席はどの席よりも高いところにあり、覗こうとする無礼者もいない。その事実でもって伯爵は目の前から御簾を取り除いたのだ。同時に、ヘッドセットもとりさってやや乱暴に脇の小さなテーブルに置いた。
「リーデルシュタイン辺境伯は残念だったの」
赤毛のミラーカ女帝がふと言った。伯爵は肘掛けに肘をたてて、怠惰に頬杖をついた。
「これでお祖母さまの代から生きている者もずいぶん減った。建国の士が減っていくの」
「仕方ありますまい。生きる者の定め。星とていつか燃え尽きるもの。ハルトムート・リーデルシュタインはむしろよく生きたほうです。陛下としてはほめてやるべきかと」
「私情を挟まぬ善い行政官であったな」
「ええ」
死者に捧げられるかのように、桟敷席を沈黙が満たした。
「去る者もいますが、今日は生まれるものもおります」
沈黙の末、伯爵は前方のステージを示した。ミラーカの目もそこに注がれる。ステージにはピアノと、譜面台が一つ。
「すでに生まれて幾年も経っているものが、今日生まれる、とはやや奇妙な表現だがのう」
ラミーカはふうとため息をついた。
その最後のため息へ、湧きだすように響いた拍手の音が重なる。帝国の重鎮二人は話すのを止め、舞台にきちんと向き直った。
ピアノと譜面台の周囲に変化はない。その代わり、舞台袖に近いところにある、講義台のところに眼鏡をかけた黒髪の男が立っている。医療院の正装である深い緑色の詰襟を着た男は、ジークフリート・フォン・エルレンマイヤーであった。
今日は、ヒトとヴィータの混血児であるダンピールあるいはダンピーラをヴィータへと“転化”させるためのプロジェクトの結果報告会の日なのだ。コンスタンツェの治療が二カ月ほど前に終わり、国家予算がついたプロジェクトだったためにこのような仰々しい場が設けられたのだ。
司会から“転化”プロジェクトの中心である、と説明を受けたジークフリートは簡単に挨拶をすると、医学的な説明に入った。
「……ダンピール、あるいはダンピーラといった、我々ヴィータとヒトの混血である存在は、その社会的異質性と短命さから長らく顧みられることはありませんでした」
ジークフリートの声は、感情の混じらない学者然としたものであった。
伯爵は一年半前、ダンピールの娘を案じて自分のパートナーをも殺すと脅した男を思い出して苦笑する。壇上のジークフリートはあくまでも冷徹を装っている。
医学的な解説に耳を傾けていると、隣のラミーカがぼそりと
「眠い」
と言った。伯爵は今日何度目かの苦笑をする。
ミラーカが眠気に耐えているうちに、またわっと拍手が上がった。ジークフリートの解説が終わったのだ。ラミーカが気合の息を吐き出して、ビロードの椅子に座り直すのを見て、伯爵はまた笑う。
司会の男が、ジークフリートと入れ替わった。
「それではご紹介いたします。この度の“転化”被験者で今日より我らの“牙のない同胞”となるコンスタンツェ・アドリオン嬢です。コンスタンツェ嬢は音楽院にてサクソフォンを専攻しており――」
呼ばれたコンスタンツェが舞台袖から現れた。拍手が上がる。
現れたコンスタンツェは、発表会にありがちなロングドレス姿ではなかった。黒のパンツスーツに、黒いヒール。その姿はピンク・ゴールドに輝くサクソフォンにむしろよく似合っている。その後ろから、遅れてジャケット姿の金髪の男が現れた。ルートヴィヒだ。コンスタンツェが聴衆に向かって美しい礼をした。
好奇や奇異の目が彼女の上に降り注ぐ。だが“同胞”が住む闇の色のジャケットを身にまとった娘はまっすぐに背を伸ばしている。
そして彼女は、伴奏者としてピアノの前に座ったルートヴィヒに目を向ける。ルートヴィヒは頷いた。
コンスタンツェが息を吸い込み、ルドルフがゆったりと鍵盤の上に指を置く。
奏でられたのは、力強いサックスの音だった。
そして、聞きなれた伴奏が始まる。
力強く、陽気に――だが歩んできた道を感じさせる。伯爵は、ふとつぶやいた。
「アレンジがいいな」
「『煙が目にしみる』か、いい選曲じゃの」
ラミーカも微笑んだ。
クラシックでも選んでくるかと思ったが、彼女が選んだのは往年の名曲だった。
甘やかで、伸びのある音。全身で音楽の喜びを語る。
だが、その裏に何がしかの哀愁に似たものも感じさせる。
煙が目にしみて涙を流し、泣き腫らして、だがそれでも顔をあげて生きて行く。手の甲で涙をぬぐったら笑って見せるのだ。
そう音楽が語っているようだった。
――どこか思いつめたようなところがなくなったのか。
一年半前のジャズ・バーでの演奏を思い出し、伯爵は口の中で呟いた。
演奏がやがて終わり、拍手が上がる。
「さあ、陛下の出番ですよ」
伯爵は傍らの赤毛の娘に言った。ミラーカは前方を見て立ち上がる。下々の者も続いた。伯爵はあえて立ち上がらない。
コンスタンツェとルートヴィヒが皇帝の桟敷席を見上げ、深く礼をした。
ミラーカが拍手を止める。会場から音の全てが消えるまでにやや時間を要した。その間に、ジークフリートが再び舞台へと上がり、ルートヴィヒがコンスタンツェからサクソフォンを恭しく預かった。コンスタンツェは一歩前に出て、背筋を伸ばした。
そこへ、客席中央の通路を通って着飾った女たちがしずしずと何かを運んでいく。
マグヌス・パテルと女帝ミラーカはそれを黙って見守っている。やがて女たちの、何かを掲げて歩いているうちの一人が舞台へと静かに上った。
そして、客席から見えるようにコンスタンツェの横に並ぶ。
女は、美しい細工を施したシャンパングラスの乗った黄金の盆を持っていた。
一拍置いて、女とコンスタンツェが向きあう。
シャンパングラスを満たす液体は黒味を帯びた赤をしている。
「我が新たなる同胞とならんとするものよ、“牙なき眷族”よ」
ミラーカはよく鍛えられた、よく通る声でそう言った。
「我らが糧を受け入れ、我らが同胞たる証を示せ」
赤黒いシャンパンの正体は、血液製剤を溶かしこんだものである。それを飲み干せば、ヴィータとして迎えられる。そのための“儀式”だった。
コンスタンツェは盆の上からグラスを取り上げた。客席がざわつく。コンスタンツェは目を瞑り、息をひとつ吐くとシャンパンを一気に飲んだ。
混じりものがしてあるシャンパンが、白い喉を下る様子が見えた。
繊細なガラス細工が小ぶりな唇を離れる。コンスタンツェはすぐにグラスを盆の上に戻した。盆を運んだ侍女がグラスを取り上げ、聴衆に向かってそれを逆さにしてみせる。一滴たりとも零れてこない。
「コンスタンツェ・アドリオン、確かにその証を見た!今日より我が同胞、我が娘、我が妹なり!」
ミラーカが宣言する。伯爵は脇に放ってあったヘッドセットを取り上げて、下々の者と同じく賛同の声を上げた。
舞台上のコンスタンツェはホッとしている顔をしている。その肩をジークフリートが抱いた。
伯爵はそれを見ると、右手を挙げて御簾の係を呼んだ。伯爵の前に、ふたたび目隠しの御簾が垂れる。
それを見て、立ったままのミラーカが言った。
「じい、帰るのか?」
「見るべきものは見た」
伯爵はミラーカに向かって笑う。
「若人に幸多からんことを」
御簾運びの二人と、護衛を連れて桟敷席を出て他の客と出会うことのない順路を選んで進んでいくと、意外なことに建物の出口で彼を待つ人がいた。コンスタンツェだ。護衛が前に進み出そうになるのを伯爵は押しとどめる。
「おや、ここに来れたのかい」
「はい。たぶんお先にお帰りになるって聞いていたので、特別に」
それからコンスタンツェはきょろきょろとあたりを見回す。
「アンナマリアは……やっぱりいませんね」
「ヒトの子を連れてくるわけにはいかんからな」
伯爵は残念そうな顔をする“新しき娘”の頭をなでる。コンスタンツェはくすぐったそうな顔をした。
「おめでとう。そしてようこそ、“我が子らの国”へ。困難も多かろうが、君なら大丈夫だろう。……お説教はやめておくかな」
「お言葉、ありがとうございます」
冗談めかして言えば、コンスタンツェはにっこりする。
そして、“新しい娘”はポケットから何やら取り出した。それは二通の封筒だった。
「二通しか用意できませんでしたけど、お屋敷の皆さんもぜひ」
封筒は招待状のようだった。それぞれに“マグヌス・パテル”と“アンナマリア”と可愛らしい字で宛名が書いてある。
「音楽院の友達も手伝ってくれる、“お見舞い返し”の演奏会なんです」
「ほう」
伯爵は自分宛の封筒の封蝋を開け、二つ折りの招待状を取り出した。それは飛び出す絵本のように切り絵が施された可愛らしい招待状だった。切り絵は、シルエットでサクソフォーンを表しものだった。伯爵は微笑んでそれを封筒に戻すと、アンナマリアのものとまとめて大切そうにジャケットの内ポケットにしまいこんだ。
「必ず渡すよ」
「お願いします。あと、絶対いらしてくださいね!」
「約束しよう」
伯爵は笑って言った。そして、ふと思いついたように右手の小指を立てて彼女に差し出した。コンスタンツェは首をかしげる。予想通りの反応に、伯爵はまた微笑む。
「とある国の風習でね、約束した時に小指を絡ませるんだ」
コンスタンツェはまだ得心していないような顔だったが、言われたとおりに伯爵の小指に自分の小指を絡めた。伯爵はやさしくその細めの小指を己の太くかさついた指で包む。“最古参の吸血鬼”と、“生まれたばかりの同胞”が指をつなぐ。そして伯爵は彼女の腕ごと二、三度手を上下させると指を解いた。
「約束を破ったら相手に針を千本のませるそうだ」
「ホントですか?でも、マグヌスは約束破らないでしょう?」
初めての行為に不思議そうに解かれた小指を見つめながら、コンスタンツェは言った。
「そうだな。アンナマリアもきっと連れて行く」
「はい!」
屈託のないコンスタンツェの声に、伯爵は大きな手で彼女の頬を包み、祖父が孫にするかのように、そっと額と額を合わせた。
「Ad astra per aspera.(困難の先にある星へ)」
秘密の言葉のように囁かれたヴィータの公用語に、コンスタンツェは一瞬戸惑ったようだったが、頬に当たる大きな手に自らの手を添えて答えた。
「Tibi gratias ago.(あなたに感謝を)」
額と手を放すと、伯爵はコンスタンツェのそばを離れた。コンスタンツェも身をひるがえした。彼女にはこの後“ヴィータ”としてのお披露目のパーティがあるのだ。
伯爵は内ポケットの招待状にジャケットの上から触れて、若者たちの前途を思った。
アンナマリアとコンスタンツェがヒトとヴィータとして再会するのは、その数週間後の話である。
|