|
コンスタンツェは料理に手をつけず、ドリンクを唇を湿らす程度しか口にしなかった。
アンナマリアも段々と喋る話題がなくなり、フォークでポテトを弄ぶようになった。それを伯爵は目配せだけでやめさせる。
二人の娘が押し黙り、伯爵がブラック・ベルベットを傾ける。その光景がバーの片隅でいくらか続いた時、ステージの方で動きがあった。
トン、トン、とステージに人が上がる足音がいやに響いた。コンスタンツェがはっと顔を上げる。
ステージのグランドピアノの傍らに、いつの間にか中年の男が現れていた。
店は薄暗く、顔がよくわからない。瞳の色すら遠すぎて、コンスタンツェは期待と不安の入り混じった顔をしている。
「目の形がよく似ているよ。色はわからないが。……あれがお父上かい?」
遅れてステージにもう二人現れる。コントラバスを胸に抱えたのは、白髪にヒゲの初老の男だった。ドラムセットの所にスティックを持って現れたのは、30代くらいの、三人の中では一番若い男だった。
「ピアニスト、だよね」
コントラバスつまりベーシストの男は歳を取りすぎているし、ドラムの男は若すぎる。事前に聞いていたピアニストという情報も合わせれば、三人の中で真ん中の歳くらいの男がコンスタンツェの父ということになる。――アンナマリアは確認をするように、コンスタンツェを覗き込み、そう聞いた。
「うん、たぶん……」
演奏が始まる。
ロックのような騒がしさ、ポップスのような明るさ、クラシックのような荘厳さはない。
ただ三つの楽器だけが創るどこか艶めいた世界が広がり始める。
ドラムは暴れることなく拍を刻み、ベースが縁の下の力持ちながらも存在感を示し、ピアノがメロディを客に示す。
広がるのは、静かな音楽だった。
客たちの視線が、音楽の源へと動き、僅かな動作すら無意識に止める。
伯爵が中身の残り少なくなったグラスを揺らして、テーブルに静かに置いた。アンナマリアは拳を作ってそれをきちんと膝の上に置く。
ピアノが歌いだした。心地よい旋律の川が流れだす。
コンスタンツェはその源流をじっと見ていた。
やがてドラムのシンバルの音が一曲目の終わりを告げた。客席から、拍手が上がる。
そこへわずか、ドアの開く音がした。
見れば、ややくたびれた様子の男二人が入口にたたずんでいる。それらはもちろん、ジークフリートとルートヴィヒだった。
こちらの席を見つけたルートヴィヒが肩をすくめる。ジークフリートは一度だけこちらを見て、すぐにステージへと視線を移してしまった。
二曲目が始まる。
ウェイターの少年が、入口の男二人にに席に着くように、と慇懃に言った。ルートヴィヒはまっすぐ三人のテーブルへと近づいてきたが、ジークフリートはドア近くの、いわゆるおひとりさま用の席に座ってしまった。ルートヴィヒがまた肩をすくめた。
そのルートヴィヒも、マグヌスと一緒の席に着くことはためらわれたのか、それとも違う意図があるのか、コンスタンツェと背中合わせになる席を選んだ。
アンナマリアはそんな一同を見回し、純粋に音楽を楽しんでいるのが伯爵だけであるのに気付いた。コンスタンツェはなんだか緊張しているし、ジークフリートはむっつりとしているように見える。ルートヴィヒは音楽に合わせて、その音を確かめるようにテーブルの上でピアノを引くように滑らかに指を動かしている。そこには音を吟味するプロ意識が見え隠れしていて、伯爵のように音楽に身を任せている様子はない。
アンナマリアはため息をついて、目を閉じている伯爵のまねをしてみた。
雑念が消える。
頭の芯が解されているようで、アンナマリアはなんだかうっとりした。
やがてまた曲が終わった。
それを見計らったかのように、ウェイターの少年が注文を取りに来た。
伯爵が短く「同じものを」という。
それを伝票に書き留めて、ふと少年は床に目をやった。視線の先には、コンスタンツェの楽器を収めたハードケースがある。
「ね、お客さん。楽器は何?」
「アルトサックスよ」
言うと、少年は手に持っていたボールペンを振った。
「ジャズ、できる?」
「何曲かなら」
言うと、少年はにっこりした。
「おれ、ここの音楽にはサックスが足りないと思うんだよね……セッションしてくれる?」
すると、コンスタンツェは目を見開いた。
「いいの?」
「おっ、乗り気じゃん。頼んでくる。ちょっと待ってて」
だが少年は、仕事は忘れなかったらしくカウンターで注文を女性バーテンダーに告げた後、ステージに向かった。ちょうどコントラバスが弦を直しているらしく、ステージは小休止していた。少年はそっとピアノの男に近づく。
ピアニストの男が振り向く。少年が何やらささやくと、二人は同時にこちらに顔を向けた。
――あれ?
アンナマリアはふと、“何か”を感じた。何だかはわからない。思わず伯爵の方を見ると、彼は顎を引いていた。伯爵はつぎに、カウンターの方を見やった。視線の先にはあの女性バーテンダーがいた。それから最後に、コンスタンツェを見る。一連の行動の後、テーブルの上に片手を置いて指を広げたり閉じたりしている伯爵の顔に、何か表情が浮かんでいるようにも思えたが、店が暗いのとも相まってアンナマリアにはよくわからなかった。
ステージで少年が手招きした。コンスタンツェはちらりとルートヴィヒを見た。ルートヴィヒは気配だけで気付いたのか、僅かな動作で進むようにと伝えただけだった。また彼女は、ハードケースを抱えてジークフリートの横を通った。振り返りつつ進む彼女に、ジークフリートは僅か顔を上げただけで、すぐにテーブルの木目に目を落としたようだった。
ステージに辿り着くと、コンスタンツェはまずピアニストと握手をし、ベーシストとドラマーとも順に握手をした。そして、ステージの端でハードケースを開く。
その間に、ベーシストがマイクを取り上げた。
「飛び入りですが、サックスが加わってくれます」
常連らしい客たちから、おお、と歓声が上がった。コンスタンツェが準備をしている間に、ピアニストが即興でBGMを弾き始めた。準備が終わると、その音楽が静かにひいて行く。
ベーシストがステージの中央に彼女を招く。
「お名前は?」
「コンスタンツェ」
「よろしく、コンスタンツェ。アルトサックスだね。何か希望の曲はあるかい?僕たちができるのだといいけれど――」
コンスタンツェはステージを見回した。そしてはにかんだ様子で言う。
「――“煙が目にしみる”」
すると、ベーシストがにっこりした。
「それならできるよ」
ベーシストがマイクを片づけつつ、コントラバスの所へ戻った。それを見届けて、コンスタンツェはステージの男たちに目配せをした。そして、サックス奏者は息を吸った。
上がって下がって、彼女の息遣いと指が、楽器に歌を奏でさせる。即興のスキャットのようなそれは、さきほど告げた曲のメロディーを取り込みながらのアドリブだった。
やがて穏やかに、サックスの音が沈み――それを合図にしたかのように、ピアノの音が寄り添い始めた。
深い音の中に、明るさを見せつつも、ゆったりとした哀愁がある。ドラムは繊細なリズムを刻み、ベースが曲に深みを持たせる。ピアノは伴奏というよりもコーラスだった。
伸びて、深く沈み、だが軽やかさを感じさせる音のステップ――コンスタンツェはそれを見事に踏んでみせる。
やがて間奏が訪れ、ピアノが歌う。
その間、コンスタンツェはピアニストを見つめていた。やがて二人は目を合わせ、タイミングをはかる――サックスがまた歌った。
「――“愛の炎が死んで その煙が目にしみるのさ”」
本来ある歌詞の最後のフレーズを、伯爵が呟くように歌った。アンナマリアはその言葉に、ステージの上のコンスタンツェを見つめた。
店からは、今晩で最高の拍手が上がった。
ただ、ジークフリートだけはテーブルに両肘をつき組んだ手の上に顔を埋めていた。
コンスタンツェはにっこり笑って、感謝の礼をステージと客席に捧げた。
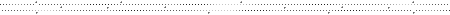
それ以上のことは、そこでは何も起こらなかった。
店を出る際、伯爵が
「三つのテーブルをまとめて。あとは他の客のドリンクも一杯ずつ奢らせてくれないか」
というとウェイターの少年は目を丸くしたが、伯爵が彼に多めのチップを差し出すとすぐににっこりした。
そして揃って店を出る。客人三人は口を利かなかった。
店の外ではファービアンが辛抱強く皆を待っていた。
「御苦労」
従僕が一礼した。そこで伯爵が一行を振り返る。
「さて、三台車があるわけだが……どう分乗する?」
「えっ……と」
コンスタンツェがジークフリートを見上げる。ジークフリートは黙って彼女を見つめ返した。
そして、彼が何か口を聞こうとした時だった。
「すみません!」
突然ドアが開き、男がひとり飛び出てきた。
――あのピアニストだった。
「サックスのお嬢さん!」
バタン、と店のドアが閉まる。コンスタンツェは体ごと振り向いた。
「あ……はい」
ジークフリートが僅かに身構え、彼女の腕を取ろうとしたが――ルートヴィヒに阻まれた。
ピアニストの男が言う。
「あ……、人違いだったら申し訳ないのですが……」
ピアニストは、じっとコンスタンツェの顔を見つめた。ラピスラズリの瞳が、真摯に彼を見返す。
「御親族に……クラーラと言う方は?」
その言葉に、コンスタンツェが複雑な笑みを見せた。嬉しそうな、哀しそうな。
「――クラーラ・フォン・アドリオンならわたしの母です」
ピアニストは驚きと納得が綯い交ぜになった複雑な顔をした。それから何か言おうとしているが、言葉が見つからないのか、それとも選べないのか――先に口を開いたのは、コンスタンツェだった。
「……わたし、父の顔は知らないんです。ピアノを弾く人だった、としか聞いていないんです。――母は、わたしが五歳の時に亡くなりました」
「あ……」
ピアニストは、今知らされた事実に言葉を喪ったようだった。
「“煙が目にしみる”は――母が子守歌代わりに歌ってくれたんです」
「――……、子守歌にしては、哀しいね」
ピアニストはようやっと、という感じで言った。コンスタンツェは苦笑する。
「でも、クラーラはよく口ずさんでくれた。――ぼくのピアノで」
中年のピアニストは、少女とも言えるサックス奏者の手を取った。
「君のサックスの音に、似てる気がしたよ」
コンスタンツェは黙って――しかし笑顔でその手を握り返した。
そこへ、コツ、と靴音が響いた。コンスタンツェが傍らを見上げる。ジークフリートだった。コンスタンツェがそっとピアニストの手を放して、ジークフリートのジャケットの肘あたりをつまんだ。すると意外にも、――かつての婚約者を奪った男を前にして――ジークフリートは彼女に微笑んで見せた。
何か恨み事一つでも言うのではないか――という周囲の心配をよそに、ジークフリートは育ててきた娘の隣に立つだけだった。寄り添うように、守るように。
その彼に――意外そうに声をかけたのは、ピアニストだった。
「あなたは――、20年前、わたしを助けてくれた方ではありませんか?」
ジークフリートは無言でそちらを見やった。ピアニストの顔に確信に少し足りないものが浮かぶ。ジークフリートは、作り笑いをした。
「20年前?さあ、なんのことでしょう」
「20年前、あなたはわたしをあの街から逃がしてくれた――クラーラの親族の追手から」
「20年前といえば、わたしもただの子どもです」
――絶対嘘だ。
アンナマリアとコンスタンツェの頭に同じ言葉が浮かんだ。
ジークフリートは吸血鬼である。人とは違う歳の取り方をする。20年前であれば、1、2歳あるいは3歳ほどしか変わらない――つまり今とほとんど変わらない――容姿であったはずだ。
「そう……ですか」
ピアニストは深追いしなかった。
「親父!」
そこへ、新たな声が加わった。見れば、店の中から少年ウェイターが顔を出している。
少年は突っ立っている集団を見て目を丸くし、そのまま店から出てきた。
「すみません、お引き留めしちゃって。親父、みんな待ってる。ベースとドラムだけじゃもたないよ〜」
少年のピアニストを呼ぶ呼称に、コンスタンツェとルートヴィヒは立ち尽くしたようだった。が、アンナマリアはふと先ほど感じた“何か”に納得がいく思いだった。
――ああ、似てるんだ。
おそらく、あの女性バーテンダーがこの少年の母親で、ピアニストが父親だ。ほどよくどちらにも似ている。さきほどアンナマリアが感じた“何か”は、コンスタンツェとピアニストが似ているということはもちろん、彼女が腹違いであるだろうこの少年ともどこか似ているということに対してだったのだろう。それを彼女は感じたのだ。アンナマリアが目をやれば、伯爵も得心したような顔をしている。伯爵もさきほど直感的に彼らの関係に気付いたのだろう。
それに何も気づかない少年は、コンスタンツェを見つめてにっこりと笑った。コンスタンツェは驚いたように身を震わせた。その肩を、傍らのジークフリートが抱く。だが少年は気にせずに、コンスタンツェに話しかけた。
「ねぇ、名前なんて言うの?」
「……、コンスタンツェ」
「おれはヘルマン。おれ、君のサックス好きだよ」
「!」
コンスタンツェは驚いた顔をした後、にっこりと笑った。花が咲くようだった。その顔に、ヘルマンと名乗った少年は照れたように頭をかいた。
「また来てよ。おれ、トランペットやってるんだ。親父やみんなはなってないって言うけど、今度一緒にセッションしようよ」
無邪気なヘルマンの言葉に、くすり、とコンスタンツェが笑う。
「いつか、ね」
少し大人びた余裕を見せて、コンスタンツェはピアニスト――半分だけヘルマンと血をつないでくれた父に同じ笑みを向ける。
「今日は、ありがとうございました」
「え……ああ」
ピアニストはまだ戸惑い顔をしている。ジークフリートは無表情のままに、抱えるようにしてコンスタンツェの身を反転させた。
コンスタンツェはあわてて振り返る。
「それじゃあね!」
肩越しに手を振れば、切なげな表情の父の傍らで、トランペットを吹くというヘルマンが笑顔で手を振った。よく見れば、“姉と弟”である二人の笑顔が似ていることに気付いたのは、その晩そこにいて事情を知る者たちだけだった。
|
![]()