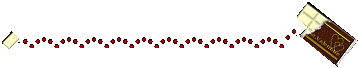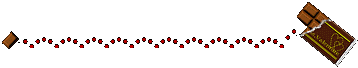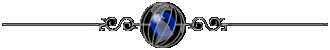|
さて10月31日。ハロウィン当日。
世の中ハロウィン一色である。ジャック・オー・ランタンが一家に一つといわず、様々な場所に溢れ、黒と鮮やかなオレンジのコントラストが世界を彩る。いつもは厄介者の黒も、今日はオレンジのおかげでどこかはずんでいるように見える。
子どもたちは母親に作ってもらった様々な仮装で昼間から跳ね回り、お菓子をもらえるのを楽しみにしている。大人たちは一体何人来るかわからない子どもたちのために備えたお菓子を数えなおして不安になったりもしたが、やはり楽しい期待感のようなものが沸いてくるのだろう、みんなにこにことしている。もしかしたら、自分が子どものときの思い出を懐かしんでいるのかもしれない。

街の郊外である屋敷はどうだろう。
使用人用の休憩室で、ダドリーとマーサはお茶を飲んでいた。
「今年は子どもたち、来てくれますかねぇ」
ダドリーが言うと、マーサが答えた。
「まったくですわ。伯爵が吸血鬼だって広まって以来、時たまいる無謀な性格の子以外はお菓子を貰いに来てくれなくなりましたからね。
『お菓子をくれなきゃイタズラしちゃうぞ!』
なんてここ何年も聞いてません」
「そういえば、子どもたちが来てくれないとはいえお菓子は用意してあったはずなのですが……、毎年、いつの間にか消えてるんですよ。マーサさん、何かご存じないですか?」
「……」
「マーサさん?」
「あら、いやだ。ダドリーさん、ご主人様に頼まれた準備はもうお済になって?」
はぐらかすような口調のマーサにダドリーは真面目に答えた。
「それはもう、もちろん。あとはご主人様がご自分でなさるぶんだけです」
「それはよかったわ!さ、私も腕によりをかけようかしら」
「おや、ちょっと待ってください、毎年行方不明になるお菓子については……、ちょっと、レディ・マーサ、マーサさん」
慌てて厨房に向かったマーサの背中にダドリーは声をかけたが、マーサは行ってしまった。
ダドリーはため息をついて、紅茶を啜った。
「まぁ……腐れ果ててしまうよりはましでしょうかねぇ」
屋敷を取り仕切る男には何もかもお見通しのようだ。
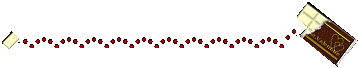
だがここ数年と違い、日暮れになると、ノッカーで玄関のドアを打つものがあった。
ダドリーが少し期待をしてドアを開けると、そこには仮装した若者が二人立っていた。
一人は魔女の格好をして紙袋を提げたミリアムで、もう一人はミイラ男のシェーンだった。
ダドリーは、子どもならともかく若者がバスに乗ってこの格好でここまで来たのだろうか、と思ってしまった。
「あの……突然すいません、ここにアンナマリアはいますか?」
若者二人ははじめて見る“吸血鬼屋敷”の内部に少なからず驚き、おびえているようだった。
「ええ、はい、いらっしゃいますとも。ご学友さまですね。お呼びしますので、リビングでお待ちください」
そういってダドリーは二人を屋敷に招きいれた。二人は顔を見合わせ――恐る恐る屋敷に踏み込んだ。
大理石の彫像が並ぶ廊下を身を小さくして進み、二人はリビングのソファに所在なげに座った。執事だと自己紹介した男が一旦退出すると、ふたりはおのぼりさんよろしく辺りを見回した。
「なんか……すごい」
「つーかさ、やっぱあの人は吸血鬼に仕えてるのかな?」
「そんなばかな。だってどう見てもさっきの庭も普通だよ」
そんな二人の頭上に、しずかなバリトンが降って来た。
「君たち、誰かね」
二人が飛び上がらんばかりに驚いて振り返ると、そこにはガウンを着た男が立っていた。眠そうに目をこすってはいるが、どんな美女よりも美しい肌とどんな俳優よりも美しいプロポーションをもった素晴らしい男だった。顔には憂いの影が感じられる。
魔女の姿のミリアムは、思わずぽっと頬を染めた。シェーンは怯えた声を出した。
「え、えええと、オレたち、アンナマリアの友人で、その……」
すると男は眠そうな目をパッチリと開けた。
「ああ、そうか。てっきりそんな格好をしているから一体何かと。ははあ、そうか……」
二人は自らの姿を見下ろした。たしかに。
「あの、もしかして伯爵さま、ですか」
ミリアムが頬を染めながら聞くと伯爵はにっこりした。
「爵位などもう随分前に廃れたがね、一応まだ保持しているよ」
そして伯爵は二人に手を差し出した。二人は伯爵と握手をしてその冷たい手に驚いた。
「アンナマリアを誘いに来てくれたのだろう、ぜひとも……」
「ミリー!シェーン!」
伯爵が言いかけたところでアンナマリアがやってきて友達の名前を呼んでしまったので、彼は口を閉じた。
「やだ、二人とも仮装したままバスに乗ってきたの?」
「ハロウィンだもの、わからないわ」
「……伯爵も上がってくるなら着替えてきてください。ガウンの下、パジャマでしょう?」
「……起きたばかりでね」
起きたばかりだ、という伯爵の言葉に仮装した二人が顔を見合わせた。今は夕方なのだ。明らかに寝すぎである――人にしては。
「あの、失礼ですけど本当に伯爵さまなんですね。てっきり、ここには……」
「吸血鬼が住んでいるものだと思ってました」
若い二人の言葉に伯爵は鷹揚に笑い、アンナマリアは「ははは」と力なく笑った。
「あっ、それでね、マリーの分も持ってきたのよ」
ミリアムが思い出したように言い、持っていた紙袋を持ち上げた。そしてその中に手を突っ込んでガサゴソとやる。次の瞬間、出てきたのは可愛らしい猫耳がついたカチューシャだった。
「じゃーん」
「ほほぅ、手作りかね」
興味を持ったのは伯爵だった。ミリアムから猫耳カチューシャを受け取ると、ひょいとアンナマリアに向き直った。そして、すっと彼女の頭につけてしまう。
そして伯爵は一歩下がると、満足げに言った。
「似合うぞ」
「尻尾もあるのよ!」
アンナマリアは無言でカチューシャを頭の上から取り去った。
「行かないってば」
そして一言、低い声で告げる。場が凍った。
「マリー……」
つき返されたカチューシャを胸元に寄せて悲しげに言うミリアムの横で、伯爵が腕を組んで嘆かわしげに首を振った。
「申し訳ないけど、今日も観測したいし」
「ええと……」
シェーンは何か言葉を捜していたが、上手く見つからなかったらしい。その間にアンナマリアは身をひるがえして行ってしまった。
「……申し訳ないな」
アンナマリアと同じ台詞を言ったのは伯爵だった。
「いえ、なんとなく理由はわかりますし」
「家族いっぺんになくしたから、元気でないのはよくわかるんです。でもちょっと元気になったらいいなぁって思って」
「……やはりそうだったか」
伯爵は優しく頷いた。
「アンナマリアはいい友達を持ったな。すこし意固地になっているが、仲良くしてやってくれ」
二人はこっくりと大きく頷いた。
「真面目なのが、たまにキズなんすよ」
「まぁ、同年代には異様に思えるかもしれんが、私には頼もしいよ。真面目さと言うのはね」
伯爵は特に他意なく言ったのだが、二人は若干ぎくりとした。それを見て伯爵は笑う。
「だが“遊び”はそれなりにないとね」
そこへマーサがお菓子の入った籠を抱えてやってきた。彼女はガウン姿の伯爵を見るなり素っ頓狂な声で叫んだ。
「まぁま!伯爵、なんて姿でお客様の前に!もう、ダドリーさんは一体何をやってるんでしょう!ああ、もうああもう」
伯爵はおどけるように両手を広げた。
「ダドリーは私の頼んだ仕事をしてたんだ。責めないでやってくれ」
するとマーサは思い当たる節があるのか、不承不承頷く。そして彼女は仮装した二人の若者のほうを向くと、胸を張っていった。
「ここにお菓子があります。合言葉をどうぞ!」
二人の若者は一瞬きょとんとしたが、一瞬後に噴き出して「「お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ!」」と言った。

お菓子をたくさん詰め込んだ紙袋を抱えて、二人の若者は少し元気なくバス停への道を辿っていっている。
伯爵はその姿を屋敷の一番の高所から見ながら、ふむ、と顎を撫でた。
「ご主人様、着替えの準備ができましたよ。ガウンにパジャマでうろつくのはやめてくださいな」
マーサが背後から苦言を投げつけてくる。伯爵は振り返って彼女に言った。
「あのお菓子は手作りかな?」
「一部を除いて、もちろんですとも」
「じゃあ、わたしも合言葉をいえばいいのかな」
するとマーサは身を振るわせた。
「ご主人様がトリック・オア・トリートなんて怖すぎます」
「安心したまえ。君はもう若くない」
「まぁ!いくらご主人様でも怒りますよ!」
マーサがぷりぷりと怒る様子に伯爵は笑った。そして笑いを収めてマーサに言う。
「意固地なウラニアはどうしたものかね」
主人の言葉に肩をすくめた。
「あの娘さんは、わたしの阿呆な子どもたちとは違いますからねぇ。
ご友人が愛想尽かさなければいいのですが」
「人が死ぬというのはかくも重いものだ」
何人もの人間の死を見てきた吸血鬼は、ため息に似た声でその言葉を吐き出した。
「だが残されたものは生きていかねばならん。彼女はあまり能動的な意味で生きていないように思えてね。わたしはそこを心配してるんだ」
「今日はどうなさるんですか」
マーサが心配したような声を出すと、伯爵はにっと笑った。
「観測はさせる。それが彼女の望みだからね。そうだ、マーサ、久しぶりにアレを用意してくれ」
「アレ……ですか?」
要領を得なさそうな顔をしているマーサに伯爵は重ねて言った。
「燕尾服と、裏地の真っ赤なマントだ。インバネスでも構わんが、マントの方がより相応しいだろう」
次々と挙げられた名称にマーサはぽん、と手を叩いた。
「はいはい!了解ですよ、久々にアレをやるんですね」
伯爵はにっこりとした。
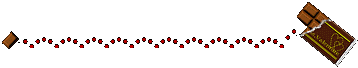
天体望遠鏡は運びやすくケースに入れたし、ペン、ノート、星座早見表、方位磁針、懐中電灯、森の中で遭難したときのための携帯電話、それから、飲み物。
夕食後、アンナマリアが自室で観測のためにそれらのものを確認しているとコンコン、と言うノックの音がした。はい、と返事をするとキィとドアが開いた。
地に着きそうなほど長いマントに身をくるんだ伯爵が吸血鬼然として立っていた。腕を動かしたためにひょいとマントが捲れた。裏地は鮮やかな、血を思わせる赤で、その向こうには燕尾服がちらりとのぞいた。
「こんばんは」
ことさら低い声で言った伯爵にアンナマリアは感想を述べる。
「……びっくりしました。そうしていると本当に吸血鬼みたいですね」
しっかりと撫で付けられた黒髪と、わずかに唇から覗く犬歯。伯爵は唇を弓なりにゆがめた。
「“みたい”は余計だよ――今から行くのかい?」
「ええ」
「今日はハロウィンだな。せっかくだから、いつもは通らない道を通ろうじゃないか」
「?」
アンナマリアが首を傾げている間に、伯爵はつかつかと部屋の中に入ってきて、ドアの向かいにある窓を開け放った。そこから周りを観察して、うん、と言う。
「ここから出ればいいな」
「え?ここ?」
「そうだ。君、荷物をこちらへ」
伯爵は窓枠に腰掛けると左手を差し出した。アンナマリアは首を傾げて躊躇する。伯爵はもう一度言った。
「こ ち ら へ」
命じる口調だった。アンナマリアはふらふらと従ってしまい、大きな天体望遠鏡のケースをその手に任せてしまった。そこでアンナマリアははたと正気にもどったような感じになった。
「君は、こちらに」
だが伯爵は気にした風もなく、今度は右腕を彼女に差し出した。アンナマリアは不審に思いつつも、伯爵が示した範囲内に身を寄せた。途端、抱き寄せられる。
「しっかりつかまっていたまえ」
甘い声で伯爵はアンナマリアにささやいた。ぞくりとする感覚にアンナマリアが気をとられているうちに、彼がスイッと動いた。気づけば、二人は屋敷を取り囲む堅牢な城壁の上にたっていた。
伯爵は一蹴りで部屋からここまで跳んだのだ!
「吸血鬼らしいだろう?」
ぽかんとして辺りを見回しているアンナマリアをマントにくるみながら伯爵は得意げに言った。
「あの、でも伯爵、誰かに見られたら――」
びょうと風が吹いてアンナマリアの長い髪をさらい、伯爵のマントの襟が撥ねた。
伯爵は笑って腕の中の人間の娘を見下ろす。瞳は冷たい青をしていた。
「今日はハロウィンだからね――不思議が起こっても、だれも気にしないさ」
そうして、伯爵は辺りを見回し視線で先を示した。そこには一本杉が寒そうに立ちすくんでいる。
「次の“中継地点”はあそこだな」
「え」
「覚悟したまえ、私の天文の女神」
アンナマリアが状況を飲み込めないうちに、伯爵は何百年と風雪に耐えてきた城壁を蹴った。
そして一本杉のてっぺんに近い枝を伯爵が蹴るころには、体が宙に浮く感覚にアンナマリアは少し怯えながらも、少しわくわくしはじめていた。
東の森の広場にぼんやりと暖かな光がある――空中散歩の終わりにアンナマリアは気づいた。いつも観測をする場所に、先客がいるのだ。
伯爵の腕の中で、アンナマリアは少し顔をしかめた。伯爵はその様子を見て、最後の“中継地点”に少しだけ――ほんの数秒だが――長く留まった。枝が揺れる。
――私の場所はあるかしら。
アンナマリアはそんなことを考えていた。伯爵はふと口元に柔らかな笑みを浮かべ、最後の枝を蹴る。ふわりと体が持ち上がり、最高点に達し、ゆるゆると放物線を描きながら降下していく。
先客は一人きりだった。トン、と伯爵が広場に下りるとその先客はしずしずと近づいてきた。
「ダドリー」
「これに」
それは執事のダドリーだった。アンナマリアはきょとんとして彼を見る。
「あれ、どうしたんですか?」
ダドリーはにっこりとして自分の後ろを優雅に指し示した。
そこには、ガーデン・パーティ用の大きな野外用テーブルが美しい赤と白二枚重ねのテーブルクロスを掛けられて鎮座していた。
中央にはコンテストに出場できるほど大きくならなかったお化けかぼちゃが見事ジャック・オー・ランタンに変身してあたたかなオレンジの光を振りまいている。
そしてその隣には、大きな大きなパンプキン・パイ!
口に含むとさくさくと軽快な音を立ててくれそうな狐色のパイ生地は彼女を誘っているかのようだった。
その周りには、ワインの瓶が数本。ラベルは適度に汚れていて、どうやら本当の年代物らしいことがわかる。その近くに控えているワイングラスには汚れないようにと白い布がかけてある。よく見れば、干しブドウ入りのパンもちょこんと控えめに存在している。
それから、フルーツ・ポンチにプリンにチョコレートやキャンディなどお菓子も目白押しだ。銀の蓋が被せてある皿には、チキンか何かが隠れているのだろうか。
「あの、伯爵、これは……」
「ハロウィンだからね。どうだい、あのランタンは明るすぎるかな?」
「いいえ」
ランタンの灯りは、街中とは比べ物にならない。
「別に支障はありませんけど……あの、これは?」
テーブルに並べられた物は、とても三人四人で食べきれるものではなかった。
誰か他にくるのだろうか?伯爵はハロウィンは眉唾だ、と言っていた気がするが……。
「うん、我々はまだ準備があるからね。君は観測をしていたまえよ」
「え」
だが伯爵は、アンナマリアの質問の意図が読み取れているだろうに答えを与えなかった。
アンナマリアはなんだか気圧されて、定点に天体望遠鏡を設置しに行った。
そんな彼女を確認してから、伯爵は忠実な執事に言った。
「行こうか、ダドリー」
「はい、ご主人様」
二人は音を立てずに広場を去った。

「ええっアンナマリア来ないの!?」
所変わってマイク――ハロウィンパーティーの主催者――の家。時間は、シェーンとミリアムが伯爵の屋敷を後にし、バスに揺られて、街をふらつきつつ彼の家にたどり着いた後のことだ。ちなみにマイクはまだ普通の格好をしていた。
「うん――どうもだめだったよ」
そう行ってシェーンはマイクに一抱えもあるお菓子が詰まった袋二つを――途中でミリアムに一つ押し付けられていたのだ――彼に押し付けた。マイクはそれを受け取って袋からこぼれだしそうなお菓子に目を白黒させる。
「なぁ、これ、お前ら、年甲斐もなくあちこちでトリック・オア・トリートなんてやってきたんじゃないよな?」
「アンナマリアのところに行ったら、貰えたんだ」
「年甲斐もなくトリック・オア・トリートって言ったけどね」
「行った?行ったって吸血鬼屋敷にか?!」
マイクは二つのお菓子の袋を抱えなおしつつ身を乗り出して二人に聞いた。
「うん」
「ど、どうだった?!」
わくわくした顔を見せるマイクに魔女のミリアムとミイラ男のシェーンは顔を見合わせた。
「普通だったな」
「ええ、普通だったわ」
「はあ?」
「あのね、伝説どおり、伯爵はいたんだけどどう見ても普通の人だったわ」
「普通に人も働いてるみたいだしな」
マイクは何も言わずちょっとガッカリしたような顔をした。その顔を見て、ミリアムが付け加える。
「あ、でも、伯爵ってとっても綺麗な人だったわ!いいなぁアンナマリア、あんな人と過ごせるなんて」
「綺麗?……なんかあんまり男には使わない形容詞だな……」
マイクはうっとり顔のミリアムに首を傾げてから、まぁお前ら上がって準備手伝え、と言って二人を招きいれた。
さてさらに時間が経ち、時間と空間はまったくもって“夜”といわれるに相応しいものとなった。
庭に並べたテーブルの上に、それぞれが持ち寄ったものが並ぶ。やがてマイクの――まだあの合言葉がいえる年頃の――妹たちがもどってきて、パーティーに花を添えることとなった。
マイクは肉球のついた犬の手袋と犬耳をつけている。どうも狼男のつもりらしい。
「アンナマリアが来たら犬と猫そろったのになー」
「おいお前、なんかアメコミのヒーローにしようとか言ってなかったか」
「向かいのおっちゃんと被ったからやめた」
「向かいのおっちゃんってあのビールっ腹のか」
シェーンとミリアムは赤と青の派手なアメリカン・コミックのヒーローの格好をした中年男を思い浮かべて噴き出した。おそらく本人も受け狙いだろう。
若者たちが笑いあっていると、びゅうっと冷たい風が吹いてきた。どんな冬の風よりも怖気が走るその冷たさに、三人は思わず身をすくめた。そして、風の吹いてきたほうを振り返る。
そこには、マントをはためかせた男と――白い、大きな犬が立っていた。
その男の正体にまず気づいたのはミリアムだった。
「あ、伯爵さんだ」
「こんばんは」
犬はぺろりと鼻をなめた。ミリアムはマイクの家の庭と歩道を隔てる膝丈の塀に近づいていった。伯爵と犬は歩道に立っていたのだ。
ミリアムは辺りを見回す。
「あの、マリーを連れてきていただけたんじゃ……ないんですね」
伯爵は苦笑した。クゥン、と犬が鼻を鳴らす。それにつられて、残りの二人が寄ってきた。
「ずいぶんでっかい犬ですね」
狼男のマイクが言うと、白い犬は彼を上から下まで見渡してフンッと鼻を鳴らした。
犬はどんな大型犬よりも大きく、後足で立ち上がれば若者たちと同じほどの高さを持ちそうだった。
「……なんか狼みたいだな」
シェーンが言うと、犬は尻尾を振った。ミリアムが再び伯爵を眺める。
「それ、吸血鬼ですね」
全身を覆う裏地の赤い黒いマントと、燕尾服。それは『吸血鬼ドラキュラ』の作者ブラム・ストーカーによって後に吸血鬼の典型の衣装となった組み合わせだった。
「そう、吸血鬼だとも」
そして、伯爵はにっこりとミリアムに微笑みかける――その笑みはミリアムだけでなく、男二人をも魅了した。
「ところで、“私を招き入れてくれないかな”」
三人はややぼうっとした頭でそれをただ単に会場に入れてくれ、という意味だと解釈した。
この家の住人であるマイクが入り口を指し示す。白い狼のような犬が主人に先立ち、中に入った。すると、マイクの妹とその友達が彼に気づいて歓声を上げながら走り寄ってきた。
「すごい!狼犬だわ!」
兄よりも真実に近いことをのべた天使姿のマイクの妹は屈んで白い狼に手を伸ばした。白い狼は穏やかに少女に歩み寄る。
その頃には、伯爵は敷地内に入り込んでいた。伯爵は優しい瞳を白い狼を撫でる少年・少女たちに向けた。
「君たちは、アンナマリアを知っているかね」
すると、少女たちは顔を見合わせる。
「妹のセラフィーナと友達だったよ。だから、本当はお姉ちゃんが来るの、楽しみにしてた」
そう言った少女たちの目には悲しさが見て取れた。
「そうか」
伯爵は優しくそう言った。そして、周囲を見渡す。
ひゅおう、と冷たい風がまた吹いた。
伯爵のマントがはためき、裏地の赤が闇夜に映えた。そして伯爵は白い狼を見下ろした。
「はじめようか、ダドリー」
「はい、ご主人様」
白い狼が口を利いた!!
――若者たちのその夜の記憶は、そこで一旦途切れている。

「……伯爵とダドリーさん、遅いなぁ」
観測記録も一通りとり終わったアンナマリアは辺りを見回した。ジャック・オー・ランタンもどこか心細げだ。
「……準備ってなんだろうね」
アンナマリアはテーブルに歩み寄るとジャック・オー・ランタンに話しかけた。ゆらゆらと蝋燭の炎が揺れて、ジャックはないしょと言うように笑った。
ひゅっと風が吹いて、下草が踏まれる音がした。
アンナマリアは、二人が帰ってきたのかと思って振り返る。見れば、森の出口に真っ白な狼が佇んでいた。アンナマリアはぎょっとして身を硬くした。
この森に狼がまだいたのだという事実に驚き、相手が肉食の獣だということに怯える。
アンナマリアはそれでも冷静に頭を動かした。
――何か食べ物を投げれば……。
しかし、狼は匂いにつられた様子もなければ、近寄ってくる気配もない。ただ、そこに佇んでいる。
さく、さく、という下草を踏む音が再びした――それも複数。狼が肩越しに後ろを振り返る。アンナマリアもつられてそちらを見た。伯爵かもしれない、と思ったのだ。
だが、現れたのは伯爵ではなかった。
幽鬼のようないくつもの影が、ふらふら、ふらふらとこちらへ近づいてくる。
「!!」
アンナマリアは思わず後ずさった――テーブルに阻まれてしまったが。
魔女、ミイラ男、狼男――それらがふらふらとまるでゾンビのように歩いてこちらに向かってくるのだ。
ハロウィンはこの世とあの世の境が曖昧になると聞いた。森かどこかが、向こうの世界と繋がってしまったのだろうか――アンナマリアはそう考えて、焦った。
だが、その魔女・ミイラ男・狼男の後ろに――同じようにふらふらとあるく天使姿の少女を見つけてアンナマリアはぽかんと口を開けた。
よく見れば、その奇妙な行進を成しているのは彼女の友人たちではないか!
白い狼は黙ってそれらを見ていたが、行進の最後の一人が広場に入りきるとおもむろに、氷の女王に届くのではないかというような遠吠えをした。長く尾を引く声が、森と広場に木霊する。
そして木霊が消えると同時に――森の中から、三度手を打つ音が聞こえた。
すると、彼女の仮装した友人たちはその音を合図にしたようにバタバタと倒れ始めた。
アンナマリアはぎょっとして、友人たちへもとへと走り寄った。
「ちょっと!ミリアム!!」
と言って魔女を揺する。
「シェーン!これなんなの!」
と言ってミイラ男を叩く。
「マイク!起きて!」
と言ってできの悪い狼男を仰向けにした。
また三度、手を打つ音が森から聞こえ来る。すると、またその音に反応したかのように倒れた人々が身じろぎし始めた。
「う、……ん?」
身を起こし始めたミリアムのところに慌てて戻り、アンナマリアは彼女を手助けした。
「ミリアム?」
「……アンナマリア?」
ミリアムは目をこすり、きょとんとした顔で彼女を見た後辺りを見回す。
「ここ、どこ?」
「どこって……東の森だけど……」
ミリアムはアンナマリアの返答に要領を得ない顔をした。その間に他の人々は立ち上がり、辺りを見回していた。
「お?」
シェーンとマイクが大きなテーブルに気づいた。ジャック・オー・ランタンは得意げに表情を揺らす。
「……なんだ、これ」
パンプキン・パイにワインにチキン、それにお菓子――人々は不思議そうに見下ろした。
「一体、どうしたのよ、皆。これ、いたずら?」
アンナマリアがミリアムに聞くとミリアムは勢いよく頭を振った。
「違うわ、私たち、マイクの家の庭でパーティーをしてて……、……してて、どうなったのかしら?」
ミリアムは首を傾げた。ぼんやりとして、思い出せないのだ。そんな二人の方へ、声が飛んできた。
「おうい、アンナマリア、このテーブルの上のもの、食べていいのか?」
「なんか、すげえ豪華だぞ」
アンナマリアは立ち上がって、二人の男友達の元へ行った。
「まって、それは伯爵が用意してくれたもので、よく、わからないのよ」
「伯爵?」
二人は先ほど伯爵にあったような気がしたが、思い出せない。そして、マイクがテーブルの上に食べ物でも食器でもないものを見つけた。
「なんかカードだ……『アンナマリアへ』って書いてあるぞ」
それは白い小さな封筒に入ったメッセージカードだった。開けてみると、薔薇の柄が入ったメッセージカードに流麗な字でこう記してあった。
『Dear
観測は上手く行ったかい?
それでは、ご友人とパーティーを楽しまれますように。
Julius』
「伯爵だわ」
アンナマリアが言うと、友人たちはカードを覗き込んだ。
「楽しまれますように、だって!」
「じゃあ戴いてもいいのね!」
はしゃぎだした友人たちは、ついてきたマイクの妹とその友達を呼び寄せた。
アンナマリアはその様子を困ったように眺めている。そしてミリアムたちの首筋をじっと観察した。特に異常はない。
――じゃあ、伯爵、皆に何もしてないんだわ。ただ、つれてきただけ。
そして、誰かがパンプキン・パイに手を伸ばしたときだった。
ぱっと、広場が暖かなオレンジ色の光に包まれだした。
見れば、森の端の広場に面した木の枝にジャック・オー・ランタンたちかぶら下がり、さぁパーティーだ!と言わんばかりに次々と自らに光を秘め広場を明るくていっているのだ!
仮装した人々は歓声を上げて、ジャック・オー・ランタンたちに賞賛の拍手をささげた。
アンナマリアはぽかんと口を開け、そして――声を立てて笑った。
そしていつの間にかいなくなった白い狼には、誰も気づかない。
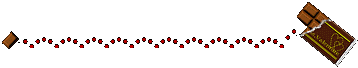
白い狼は、一つずつ器用に、そして人に見つからないように枝の上のランタンたちに蝋燭を備えていっていた。広場の周りを一周して、ふうとため息をつき、最後の一本を備え、そのまま隣のランタンのない木に飛び移る。器用に四本の足を使って枝を上へ上へとのぼっていく。
そして、枝が細くなり始めたところでのぼるのを止めると――隣の枝から声が聞こえてきた。
「ご苦労、ダドリー」
「やれやれ、ご主人様も手伝ってくださったらよかったのに」
「人型は目立つからな。それに、私は完璧主義者だ」
それは太い枝に足を投げ出し、幹に体を預けている伯爵だった。右手には脚の部分に艶かしい裸体の女神を施したフルートグラスを持っている。その中にはもちろん、シャンパーニュ地方で作られた透明な発泡ワインが注がれている。
狼男の執事ダドリーは、それを見て不安そうな声を出した。
「お味がお気に召しませんでしたか?」
伯爵は首を横に振る。
「なんとも美味なるシャンパンだ。しかし――私には一味足りないので、いまマーサを呼んだのだ」
そこへバサバサと羽ばたきの音がした。みればなにやら一羽の鳥がこちらへ向かって飛んで来て――伯爵の脚に降り立った。
「まったく、私は梟じゃないので夜目が利かないんですよ、ご主人様」
それは一羽の烏だった。烏はマーサの声でぷりぷりと怒ってみせる。
「だが、君はただの烏じゃあるまい」
笑いながら伯爵が言うと、カラスのマーサはどこからか取り出した錠剤を彼の手に落とした。
伯爵は礼を言ってそれを受け取り、裸体の女神が支えるグラスにそれを落とした。
しゅわ、と音を立てて錠剤が溶け――透明なシャンパンは赤く染まった。
「これこそ美味なり」
伯爵はそれを一口口に運んだ。錠剤は血液の塊だったのだ。
それから、伯爵は広場を見下ろした。見れば猫耳をつけられた彼の天文の女神が天使姿の少女に引っ張られていく。その先には、氷の女王を見守る彼女の天体望遠鏡があった。
どうやら天使は彗星を見せてと女神にせがんだようだ。
アンナマリアは少し楽しげに少女に指導をしている。
少女が氷の女王に夢中になると――アンナマリアがふと視線に気づいたようにこちらを振り返った。
吸血鬼と乙女の視線が絡んだ。
伯爵はグラスを上げ、彼女に挨拶した。
「Happy Halloween.」
するとその言葉が聞こえたのか、それとも違うのか、アンナマリアはわずかに首を傾け、呆れたような、困ったような、そして、暖かな笑みを彼に向けた。
伯爵は笑って、グラスを再び傾けた。
氷の女王は暖かな色の広場を静かに見下ろしていた。
Fin.
|