|
きらきらしたラピスラズリの瞳に見つめられて、アンナマリアは思わずどきりとしてしまった。
「助けてくれたの、あなたね」
先ほどの――ジークフリート、といっただろうか――医者らしき人物がほどこした処置で苦痛が和らいだのだろうか、コンスタンツェは傍らに所在なげに、しかし心配そうにしていたアンナマリアを見つけてにっこりとした。
アンナマリアはその笑顔の可愛さになぜかどぎまぎして、どもりがちに答えた。
「ああ、うん。びっくりしたよ」
歳が近いことは先ほどの“手配書”で知っていたので、アンナマリアが軽い口調で言うとコンスタンツェは苦笑した。
「ごめんなさい。――私はコンスタンツェ。皆コニィって呼ぶわ。あなたの名前、教えてくださる?」
――「くださる」、なんて、お嬢様なんだ!
先ほどこの子が「お姫様」と呼ばれていたことを思い出して、アンナマリアは感心しながら自己紹介をした。
「私はアンナマリア。友達はマリーって呼ぶわ」
「アンナマリア、優しそうな名前ね。私の名前、“変わらないもの”って意味があるみたいで、よく頑固って言われるの。羨ましいわ」
それからコンスタンツェは横になったままきょろきょろとあたりを見回した。
「あの、わたしの楽器、あるかしら?」
「もちろん!」
アンナマリアが席を立って、サックスの入ったケースを慎重に抱え上げてみせるとコンスタンツェは再び笑みを見せた。
「よかった。あの、本当に助けてくれてありがとう」
アンナマリアはこれまた慎重にケースを置いてから、再びベッドの傍らの椅子に座った。
「ねぇ、どうしてあんなところにいたの?あの、あなたは――とても特別な治療を受けていて、病院から出ちゃダメだったんじゃ?」
アンナマリアが聞くと、コンスタンツェは困ったように視線を泳がせた。
その僅かの間に、偶然にもノックの音が響いた。マーサが何か持ってきたのか、と思ってアンナマリアは立ち上がり、ドアを開ける――するとそこには、見目麗しきアポロンが立っていて彼女はあんぐり口を開けてしまった。
「ああ、ねぇ、君、コンスタンツェの具合はどうだい?」
たゆたう金の髪に美しいエメラルドグリーンの瞳、色素の薄い肌――女ピグマリオンが削り出したとも思える伯爵の男らしい美しさとは違う、どこか中性的な美しさを存分にひけらかしたような男が立っていたのだ。伯爵の持つ美が夜を切り出したような女の憧れならば、彼の美は少女が真昼の木陰で見た夢の王子様のものだろう。
見慣れぬ者が先ほどコンスタンツェをお姫様と呼んでいた男だと気付くのに、アンナマリアはたっぷり15秒ほどかかってしまった。
「ああ、ええと、目を覚ましてます」
それからアンナマリアはぎくしゃくと部屋の中へと振り返った。するとコンスタンツェが起き上がって、こちらに顔を向けるところだった。
「ルートヴィヒ?」
「ああ、コンスタンツェ」
ひょいとアンナマリアが道を開けると、ルートヴィヒと呼ばれた男は大股ながらもどこか優雅にベッドの傍らへと到着した。それから、きゅうとコンスタンツェと抱きしめる。コンスタンツェも彼の背に手をまわした。
「紹介するわ、わたしの人生で初めての音楽の先生」
「さっきは取り乱していたからね、失礼した。僕はルートヴィヒ・フォン・フェルンバッハだ。オルガン奏者をしてる」
コンスタンツェから離れたルートヴィヒはアンナマリアに手を差し出した。
「あ、どうも」
なんだか間抜けな声を出しながらアンナマリアがその手を握ると、今度はコンスタンツェはルートヴィヒに言った。
「アンナマリアさんよ。助けてくれたの」
「本当にありがとう」
ルートヴィヒはそう言ってぎゅっとアンナマリアの手を握りこんだ。アンナマリアはあわてる。
「当たり前のことをしただけですよ。病院はだめ、っていうのは焦りましたけど」
いまでは理由はわかりましたけど、と付け加えると目の前の二人が苦笑した。
「それにしても、なんであんなところにいたんです?」
「ああ、そうだよ。コニィ、なんで病院を抜け出したりしたいんだい」
アンナマリアが純粋な、ルートヴィヒが少し眉をしかめた表情で問うとコンスタンツェは困ったような――叱られた子どものような顔をした。
「あの――それは……」
「お父さん、かい?」
ルートヴィヒが真面目な顔をして言った。横目でそれを見たアンナマリアは、美形が真面目な顔をするとやっぱり絵になるんだなぁ、と場違いなことを考えてしまった。
コンスタンツェはしばしルートヴィヒをまっすぐ見つめた後、僅かにうなづいた。ルートヴィヒはその仕草にため息をついて、長めの金の前髪をかきあげた。またこれも絵になる。きらきらとあちこちに光のしずく――あるいは現代的に言えばエフェクト――が飛んだような気がした。
「“転化”が終わったら、いくらでも会いに行けるって行っただろう。僕との約束は忘れたのかい?」
ルートヴィヒは責めるようにではなく、ただ確認するようにそう言って、ベッドの脇に屈みこみコンスタンツェの目を覗き込んだ。コンスタンツェは一瞬目をつぶって、再び瞼を上げた。そしてまっすぐにルートヴィヒを見返す。
「ごめんなさい」
抑えているが明瞭な謝罪の言葉に、ルートヴィヒはまたため息をつきスラックスのポケットに手を突っ込んだ。それから背筋を伸ばして、天井――の向こうのどこか――を見上げた。金の髪がさらりと音を立てたような気がして、アンナマリアはちょっと呆れた――何にかは自分でもよくわからない。
「ジークに僕まで怒られるよ……。まあ覚悟はしてたけどサ」
「ルーは悪くないわ。ジークにはちゃんと言うし……」
「うーん、でも調べてって言われて調べちゃったの僕だし、“転化”治療中に結果報告しちゃったのも僕だしねぇ。6対4で僕の判断ミスで半殺しかなぁ」
「半殺し……?!」
蚊帳の外気味にされていたアンナマリアがぽつりと言うと、コンスタンツェが彼女の方を見て苦笑した。顔色が悪い。そして妙に白い指先で彼女自身を指ししめした。
「わたしのことは聞いてる?」
「ええと」
アンナマリアは言葉を択ぶため視線をさまよわせた。その間にルートヴィヒはコンスタンツェのベッドに腰掛けて、長い脚を組んだ。
「ハーフ、だっけ。人と、吸血鬼の」
「Vita」
「え」
柔らかな声音にアンナマリアはベッドを見た。コンスタンツェがまっすぐ見返してくる。
「吸血鬼は自分たちのこと、ヴィータって呼ぶの。あんまりよくない言葉でしょう、“吸血鬼”って」
「……、確かに」
伯爵はアンナマリアの前で一度も自分たちのことをヴィータ、と呼んだことがない。いつも彼女の前で齢二千余歳の男は自分を吸血鬼、と呼んでいた気がする。そのことに気付きアンナマリアが首をかしげると、ルートヴィヒが言った。
「マグヌスが付けた僕たちを表す初めての“自称”だからね。古いヴィータはそのまま吸血鬼っていう“他称”を使うこともあるよ。特にヒトに対してはね」
「へえ……。……、マグヌスって?」
アンナマリアがひとつの疑問納得して、もうひとつの疑問を提示すると、吸血鬼側の二人は眉をあげて顔を見合わせた。
「……もしかして君、なぁんにも知らない……?」
ルートヴィヒは困っているようだった。コンスタンツェはルートヴィヒとアンナマリアを交互に眺めた後、きゅっと口をつぐんだ。アンナマリアが弁解しようと口を開きかけると、ルートヴィヒが手を挙げて制した。
「そっか。ええと、この御屋敷の御主人だよ。彼は僕たちの……なんて言うかな、“マグヌス・パテル”なんだ」
「マグヌス――」
自国の言葉ではない言葉に、アンナマリアは一瞬戸惑った。彼らの言語だろうか、と思考停止しかけてあっと気付く。
「ラテン語、ですか?高校の時の古典で出てきたような」
「そうだよ。僕たちは公用語として古典ラテン語を使うんだ」
コンスタンツェが少しおどけたような口調で「Salve!」と言った。アンナマリアも「Salve」と返す。数年前に一番最初に覚えた単語だ。
「ええと……“偉大な”“お父さん”?」
「そうなるね」
「じゃあ、“vita”は、“命”」
「そう」
それぞれに頷かれて、アンナマリアは思案するように顎をつまんだ。
「伯爵、エライ人なんですか?」
「……エライどころの話じゃないよ」
そう言ってルートヴィヒは傍らのコンスタンツェに目をやった。
「コニィが脱走しなかったら、こんなに間近で会える人じゃないんだよ。“僕たち”にとってはね。……それで、脱走についてだけど」
ルートヴィヒは脱線してしまった会話を戻すようだったので、アンナマリアは伯爵についてよく知らないという新事実について考えるのを無意識に放棄した。
「朝までに戻るつもりだったわ」
コンスタンツェが弁解した。アンナマリアは目の前のラピスラズリの瞳を持つ乙女がなにやら大変な事情で入院していたことを思い出した。
「この街の近くじゃないよね、入院してた病院」
「ええ。電車を乗り継いだわ」
「でもあの場所は駅から遠かったし……、目的地はこの街にあるの?」
「そう」
コンスタンツェはまっすぐアンナマリアを見つめる。
「あのね、“ハーフ”だって聞いてるでしょう、わたしのこと。わたしね、お父さんのこと知らないの。何にも」
アンナマリアは少し驚いて、表情で先を促した。コンスタンツェは少しだけ顔をうつ向かせた。
「お母さんも、わたしが五つの時に亡くなったけれど。お母さんがヴィータで、お父さんがヒト。それがわたしがダンピールとして生まれた理由。たった一週間の恋だった、って」
コンスタンツェは自分の胸に手を当てる。何を思っているのだろうか、とアンナマリアは思った。
「お父さんは演奏旅行のピアニストだったって。それでね、わたし、いまはダンピール――ハーフだけど、“転化”が成功すれば完全に“吸血鬼”になっちゃうの」
「それって、自分で決めたこと?」
アンナマリアはベッドの傍らの椅子に腰をおろして、きちんと膝の上に拳を作って手を置いた。
「うん。本当はダンピールのままでもよかったんだけど、それだとわたしのヒトの部分と、ヴィータの部分が殺し合ってしまうのだって。まだ死にたくはないから、わたし、賭けてみることにしたの」
「未完成の技術だから危険だけど、死を待つよりは、ね」
ルートヴィヒは優しく付け足した。その言葉は父のような、兄のような、優しい言葉だった。ルートヴィヒはオルガン奏者だと言った。当然医療の知識はないだろう。だがその言葉には、コンスタンツェの選択に対する全幅の信頼が染み込んでいるようだった。
「それと、ジークフリートおじさん……、さっきの黒髪の人はお医者さんで、お母さんの婚約者だったの。わたしが生まれてから、ダンピールの研究をずっとしてるの。“転化”の研究もね。
もし、“転化”がうまくいかなくて、わたしが死んでしまっても、研究データがおじさんの手元に残ることになるの。わたしはお母さんのおなかの中にいるときから、というかお母さんがお父さんに恋をした瞬間から、おじさんに迷惑をかけ続けているの。だから、恩返しの意味も込めて“転化”実験に協力することにしたの。成功すれば“めっけもの”だし、失敗しても研究の糧になるしね」
アンナマリアは目を見開いた。たしかこの子は見た目通りの年のはずで、アンナマリアよりも年下だ。だが覚悟がすわっている。淀みなく語る言葉に迷いや後悔はない。顔色が悪いため、ひ弱に見えるが、目には力がある。ともすれば可憐にも儚げにも見える彼女の外見に、彼女は最初ヴァイオリンを思い浮かべた。お嬢様が弾く繊細な楽器――ステレオタイプなそのイメージは、彼女が抱えていたハードケースに入った力強い音を出すアルト・サックスよりも彼女にふさわしいように思われる。だが、今はそのイメージが崩れつつある。
迷いなく力強い低音。
ラピスラズリ色の力強い瞳とその音が重なる。
星を散らしたようなその瞳が雲ひとつない夜空を思い起こさせ、その星空の下、コンスタンツェが自由気ままに、だが力強くサックスを吹き鳴らす光景がアンナマリアの目の裏に浮かんだ。
「でもね」
と、コンスタンツェが続ける。アンナマリアは少しだけ首を傾かせて、彼女の話を聞いた。
「わたし、ヒトじゃなくなるから。お父さんからもらったもの、捨てることになるから、その前に会いたいなって思ったの。それで、お父さんの居場所をルートヴィヒに調べてもらったの」
「それがこの街だったんだ」
今まで何度も聞いただろうコンスタンツェの覚悟を、再びじっと聞いていたらしい。コンスタンツェが疲れたように息を吐きだすと、ルートヴィヒが静かに言った。
「しかしヒトでなくなる前に、なんて。そこまで聞いてればお見舞いの時に喋ったりしなかったよ、約束までしたのに」
苦笑とため息を混ぜたルートヴィヒにコンスタンツェは再び謝る。
「ごめんなさい」
「でも……倒れちゃったってことは、お父さんに会わずに帰っちゃうの?」
「ジークが許さないだろうからね。一刻も早く連れて帰りたがってる」
アンナマリアの問いに答えたのはルートヴィヒで、その言葉にうつむいたのはコンスタンツェだった。
「「ここまで来たのに……」」
同時につぶやいたのは、年の近いヒトとダンピールだった。二人は思わず顔を見合わせる。
アンナマリアはコンスタンツェの顔をじっと見つめて、眉を寄せた。
「なぁに?」
不思議そうなコンスタンツェに、アンナマリアはずいと顔を近づけた。
「お父さん、どこに住んでるの?」
「住んでる、というか……この街のバーでピアノを弾いてるって。そこに行こうとしたの」
「お店の名前、わかる?」
コンスタンツェはある名前を口に乗せた。そこはアンナマリアも知っている所だった。
「むう、そこは確か学生には高嶺の花……。ただ今日は定休日じゃないはず」
アンナマリアはそう言うと、やおら立ち上がってドアに向かった。きょとんとしている二人を尻目に、ドアを開けて廊下をうかがう。誰もいない。それからまたドアを閉めて、今度はベッドのそばの窓から庭を見下ろした。シビラの小屋の電気はついているが、外にいる気配はない。外はもう夜を迎えて暗くなっていた。
「……具合どう、コニィ」
アンナマリアは窓の縁に手をかけたまま、コンスタンツェに聞いた。
「さっきよりずっといいわ」
その言葉にアンナマリアは一つ力強くうなづいた。
「伯爵たちが部屋に来ないうちに、お店に行こう!」
「えっ」
驚嘆の声を上げたのはルートヴィヒだった。コンスタンツェは目を見開いただけだ。
アンナマリアは体ごと向き直って、ベッドに座る“ハーフ”の少女と目を合わせた。
「あのね、私、もう家族誰もいないの。母も父も妹も、みんな死んじゃった。それってすごく寂しい。会えるなら会いたいって思う」
「会えるなら……」
コンスタンツェが繰り返した。アンナマリアはうなづく。
「コンスタンツェは会えるじゃない。だから、会いに行こう」
「……うん!」
若い二人の勢いに、ルートヴィヒがあわて始めた。
「待って!具合がまた悪くなったらどうする気だい?!」
「そしたら、おじさんを呼べばいいわ。今度はそばにいるもの」
「それだったら許可を取って……」
「くれると思う?“過保護なジークフリート”が」
「……無理だろうね」
「でしょう?」
ルートヴィヒは困ったように眉根を寄せた。これがまた絵になる。
「私、車の免許あるのでなんとかして車借りてきます。歩くんでなければ、体力も消耗しないでしょう?」
その言葉にコンスタンツェがもぞもぞとベッドの中で動き、伸びをした。ルートヴィヒは困り果てた顔で年若い娘たちを交互に見た。コンスタンツェがそっとベッドを出た。
「コニィ」
「体、だいぶだるくないの」
それからコンスタンツェはサックスが入っているハードケースのそばに屈んだ。ショルダー・ベルトを取り上げて、慣れた手つきで背に背負う。重荷にふらついた様子もなく、きちんと立つ。
「うん、いける。他の荷物は置いてっていいかな」
「大丈夫。置いとけば帰ってくるっていう意思表示にもなると思うし」
「ちょっと待って、僕を置いていかないでよ」
自分たちだけで話を進める娘二人は戸惑いの声を上げた金髪の美男子を見やった。ルートヴィヒは怒ったように腕を組んで見せる。
「いってらっしゃい、なんて言うと思う?」
「……わたしの知ってるルーなら言ってくれると思う」
「死ぬかもしれないのに?」
「死なないよ。――ここでは」
迷いのない声だった。ルートヴィヒは今晩何度目かのため息をついた。
「わかった、止めない。だけど、いってらっしゃい、ともいわない」
「――」
コンスタンツェが僅かに目を伏せた。そんなコンスタンツェに、ルートヴィヒはふっと笑い、身をかがめて彼女を覗き込んだ。
「僕も行くから、ね」
コンカタンツェがぱっと花が開いたように笑った。アンナマリアはそんな彼女を見て、ぐっと背を伸ばした。
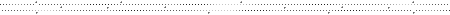
コンコン、と地下の主人の部屋にノックの音が響いた。ジークフリートと“伯爵”が同時にそちらを見やる。返事を待って入ってきたのは、執事のダドリーだった。
「ご主人さま、アンナマリアさまがお車をお借りしたいとおっしゃっているのですが……」
「アンナマリアが?」
伯爵はふむ、と考え込んだ。
「どうしてかな?」
「はい、コンビニにお買い物に行きたいそうで。なんでも、アドリオンさまが食べたいものがあるとか」
「コンスタンツェが?」
ジークフリートがやや過敏に反応した。伯爵は手を挙げて若者を制する。
「屋敷にあるものでは対応できないのか?」
二つ続けての質問にダドリーはひとつの答えで返した。
「はい。なんでも、特別なアイスクリームだそうで……。どうしてもそれがよろしいようで、お元気になっていただくのが一番かと思いまして。フェルンバッハさまもご一緒されるということなので、大事ないかと思いますが」
「……、ルートヴィヒが?」
「まあ、異様なほどの安全運転だしな。構わん」
伯爵が許可を出すと、ダドリーは頭を下げて部屋を辞した。
「やれやれ、食欲があるようだな。君の被後見人はしばらくは大丈夫そうだ」
伯爵がくつくつ笑う。だが、ジークフリートはじっと床を見つめて動かない。
「なんだか嫌な予感が」
「うん?」
伯爵が体をくつろがせて若者を不思議そうに見やった。
「いえ、勘なのですが……」
ジークフリートが不安げに部屋のドアを見やった。
|
![]()