|
「ああ、うん、自分で出せますー!お気遣いなく!鍵!鍵だけで大丈夫です、ええ!」
使用人のための区域で、アンナマリアは慌てて手を振った。それに、庭師兼運転手のダドリーの息子が首を傾かせる。
「本当ですか?送り迎えならいたしますよ、お客様もご一緒とのことですし……」
「いえ、ホントに!お客さんも仰々しいの苦手だって言ってたし!」
「そうですか……」
出番がないことにわずかにシュンとしたように見えたダドリーの息子だが、すぐに鍵を取りに行った。そわそわと待っていると、いつの間にか後ろからひょっこりとルートヴィヒが顔を出した。
「うまくいった?」
「“お客さん”は隠れてて!上手くいきかけてるから」
と、そこへ声がかかる。ルートヴィヒがひょいとドアの向こうに隠れた。
「車庫のシャッターは重たいですから、お見送りを兼ねてご一緒します。アンナマリアさんの力では開けられませんでしょうし」
「あ、いや、うん、えっと……だ、大丈夫です!」
「えっ?」
鍵を握って不思議そうな顔をしたダドリーの息子にアンナマリアは慌てる。が、そこをフォローしたのはひょっこりと顔を出したルートヴィヒだった。
「本当にお構いなく。枕元で病状にはらはらしてても仕方ないんで、お嬢さんにお願いしたんですよ。車庫のシャッターぐらい、お安いご用ですから」
きらきらと光り輝くような――実際犬歯の目立つ白い歯は光っているような歯がしたが――笑顔でルートヴィヒが言うと、今度は慌てたのはダドリーの息子だった。
「お、お客様にこのようなむさくるしい所をお見せすることになるとは……!」
どうやら、彼には使用人の居住区に客が入ってきてしまったことの方がが大変なことだったらしい。自分がすでに客ではなく家族に近い存在になっている、とその反応に気付かされてアンナマリアはちょっぴり温かい気持ちになった。
「大丈夫ですって。今女手が不足しているウチより綺麗ですから」
ルートヴィヒが言うと、はあ、とダドリーの息子が言った。その隙に、アンナマリアは彼の手から鍵を奪い取る。
「そーいうわけで!行ってきます!」
「あ、はい、お気をつけて」
勢いに任せて言うと、この屋敷の運転手は勢いにのまれてくれた。
車庫の片隅で薄手の毛布をまとって隠れるように、サックスの入ったハードケースを抱えて隠れていたコンスタンツェが物音に身を震わせたのは、それからわずか後のことだった。
「シャッターって……」
「あ、そこをグイッとあげてもらえれば」
「あ、上がった」
ガラガラとシャッターが上がっていく音と、男女の話声にコンスタンツェはそっと顔を出した。
「もう大丈夫だよ」
アンナマリアに言われて、コンスタンツェは毛布を羽織ったまま立ち上がった。
「上手くいった?」
「ばっちり」
アンナマリアは右手をかざして鍵を見せた。カチャカチャと音を立てる鍵にコンスタンツェがにっこり笑う。歳の近い娘たちは、並ぶとコンスタンツェの方が幾分背が低く、髪の色も似ているのでアンナマリアの妹といえば通じそうだった。
ルートヴィヒが目を細めた。そして開けたシャッターを見上げながら訊く。
「それにしてもマグヌスは自動にしないんだねぇ、シャッター」
「自分で開けないから気付いてないのかも」
「なるほど。で、言いだしっぺの主犯さん、次は?」
アンナマリアが雪花石膏のように真っ白なクーペの助手席のドアを開けて、背を倒した。
「コンスタンツェには後ろに乗ってもらうとして……楽器はトランクに入れようか」
するとコンスタンツェが首を振った。抱えた楽器を抱きしめ、幼子のように言う。
「持ってる」
「そっか。じゃあ、後ろに乗って。私が“いい”っていうまで隠れてて」
「うん」
コンスタンツェが後部座席に身を隠すと、助手席にルートヴィヒが、運転席にアンナマリアが乗り込んだ。
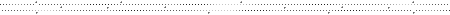
「――車が出て行ったな」
伯爵は天井――つまりは地下から地面を見上げて――何気なく言った。ジークフリートも同じように上を見上げるが、広がるのは天井ばかりで音は拾えない。
その様子に伯爵が薄く笑う。
「ヒトも脆弱になったと聞く。我らの子らもか」
「は――もうしわけありません」
「能力が淘汰されたということは、必要なくなったということ。足音に耳をそばだてて逃亡の機会をうかがうこともなくなった――そういうことだ」
伯爵が立ち上がる。ジークフリートはそれを目で追う。伯爵は部屋の片隅にある地球儀に歩み寄った。伯爵は意味もなく、おもむろに、それをくるりと回す。
「我らとヒトの間に“協定”が成って100年ほど。まさかこれほどに世が変わろうとは」
言って、伯爵は人差し指でピタリと回転する地球儀を止めた。指はアジア大陸とインド亜大陸の間に置かれている。そこに目を当てたまま、伯爵は言葉を重ねる。
「リーデルシュタイン辺境伯を知っているか」
「はい。我々とヒトとの間の“協定”にご尽力なされた方。かの御方の血液研究への助成がこの度の“転化”研究にも役立っております」
「そうか。――病に伏していると聞いた」
「――、延命治療は拒否されております。痛みだけを取ってくれ、と」
「やせ我慢をするかと思ったが――そうか」
伯爵は哀しげに笑って、地球儀から目と指を放した。
「女一人、だ」
「え?」
「女一人で男の人生というのは如何様にも変わってしまう、そういう時代になったな。今までは、逆だったか」
「はあ」
「君の場合は、女二人と言った方が適切かもしれんね」
「……」
「変わっただろう、婚約者が身ごもって」
ジークフリートは返事をしない。伯爵の顔にはよく読みとれない表情がある。
「“こうならなかった道もある”――リーデルシュタインの場合もそうだ。
それが、たった一人の出現で変わってしまう」
「――リーデルシュタイン辺境伯は、ヒトを愛されたのですか?」
ヒトに婚約者を奪われた男が熱のない声で聞いた。伯爵は苦笑する。
「いいや。彼が愛したのはヴィータだ。だが、ヒトのために死んだ」
ジークフリートが息をのむ気配をした。伯爵は続けた。
「怨むことはたやすい。だが、彼はできなかった。彼女が“怨むなかれ”と望んだから。
君は違うかね」
「……」
伯爵はまた苦笑した――今度は余計な事を聞いた自分をあざ笑うかのように。
「失礼、個人的なことを聞いた。忘れたまえ」
「はじめは、少し。」
だが、ジークフリートは口を開いた。
「わたしは正直、相手が男でも女でも構わないのです。そういう風に生まれました。悩んだこともありましたが、仕方のないことでした。コンスタンツェの母は、もともとおおらかで、俺が誰を――男だろうが女だろうが――好きでも気にしておりませんでした。
家同士の取り決めでその彼女と婚約すると聞いたとき、正直ほっとしたものです。なにせ俺のコトを知っていましたから」
自嘲気味の言葉に伯爵は顎を引いた。促すわけでもなかったのに、ジークフリートは続ける。
「だけど彼女は理解してくれているだけで――恋も知らない人だった。
そして彼女の初めての恋で、授かったのがコンスタンツェ。生まれるまでは、怨みました。けれど、ふにゃふにゃ泣く赤ん坊の顔を見たら――どうでもよくなりました」
かなり省略して話してはいるのであろうジークフリートの言葉に、伯爵は思考を一瞬泳がせただけで考えるのを止めた。
「そうか」
「事実、彼女と一緒のこの20年間――大変でしたが、楽しかった。ルートヴィヒも手伝ってくれました。騒がしくも楽しい我が家。――続けられるのなら続けたい」
言葉には、“ねがい”が込められているようだった。
「病院から逃げ出してここまで来るほどだ、彼女なら乗り越えるさ」
ジークフリートが口元だけで笑った。そして、言う。
「彼女の顔を見に行ってもよろしいでしょうか」
「ああ。わたしも一緒に行ってもいいかな」
「構いません」
さて、行ったところで客室は完璧に無人であった。
「――!」
息をのんで固まるジークフリートの傍らで、伯爵は顎を撫でた。
「はあ、まったく弱ってるとは思えんね。ハードケースが消えている所を見ると、お手洗いだとは思えん。……ダドリー」
「はい」
傍らの執事を呼ぶ伯爵の声は平素と変わらない。だが老練の執事は珍しく困ったような声を出した。
「アンナマリアが一枚かんでいそうだね?」
「はい、恐らくもう一人のお客様も……」
「ふむ。我々はあの娘を少し甘やかしすぎたかな」
ダドリーは珍しく何も答えなかった。
その間に、ジークフリートは部屋の片隅に残されていたコンスタンツェの荷物に近づく。それに気付いて、ふむ、と伯爵がまた顎を撫でた。
「荷物を残して、楽器だけ持って行ったようだな。戻ってくる気はあるのだろう」
「……そのようです、財布もなにもかもあります」
屈んで中身を確かめたジークフリートが固い声で言う。
「だが、外は雑菌がたくさんいて今のコンスタンツェにはどれも危険です。すぐ連れ戻さなければ」
「……彼女はこの街に用があってきたのだろうな。君は知らないようだが」
伯爵は背中で腕を組んで探るように部屋の中を歩きだした。
「そう、君は知らないようだが、どうやら連れのオルガン奏者は、一緒に出かけたところから見ると何か知っているようだね。あるいは、娘たちに丸めこまれたか」
「……」
ジークフリートはゆっくり立ち上がった。伯爵も立ち止まる。ダドリーは背筋を伸ばしたまま微動だにしない。
「……、ここ数日のことでしたが、ルートヴィヒが妙な動きをしておりました。見慣れぬ郵便物が届いたり……。
それと、病室でなにやら二人でこそこそしている様子も」
「ふむ、なるほど。うちのウラニアはそれの突発的な協力者となったか。見たところコンスタンツェ嬢もオルガン奏者も人を脅すような人物ではないから、強要されたのではあるまい。またウラニアの性格からして、これもお節介なところがあるから悪いことをしにいったのでもあるまい。
戻ってくるのを待てばいい」
「待てばいい?!」
それまでなんとか堪えていたジークフリートがついに声を荒げた。
「コンスタンツェは死ぬかもしれないんです!ごく微細な刺激か細菌で!すぐに!連れ戻さなければ!」
若者の必死な形相に、さすがに伯爵は顎を引いた。
「ダドリー」
「はい」
「クーペで行ったのだったな」
「はい」
執事にひとつだけ確認すると、伯爵はスラックスのポケットに手を突っ込んだ。
次の瞬間、取りだされたのは携帯電話だった。
ジークフリートがそれを見て一瞬怒りを忘れて固まる。
「失敬だな君は。わたしだってケータイくらい持っている。年寄りを見くびるでない」
言い当てられたジークフリートは慌てた。
「申し訳ありません……」
「いや、君が落ち着いたならそれでいい」
「……アンナマリアさまにお電話を?」
「かけても出ないだろう。それよりもっといいものがある」
執事の質問に否と答えて、伯爵は小さなガジェットのボタンを色々と押し始めた。ジークフリートとダドリーが固唾をのんで見守る。
「……クーペにはGPS機能が付いている」
「はい」
「そして、このケータイでその位置を調べられるのだ」
「はい」
伯爵はまだボタンをいじっている。若干、眉間にしわが寄っている。老眼だろうか、と思ってしまったジークフリートは無意識に頭を振ってその考えを追い払った。眉間のしわの理由はすぐに判明した。
「……が、操作の仕方を忘れてしまった」
「息子を呼んでまいります」
ダドリーがさっと踵を返した。ジークフリートは失礼にも、なんと呑気な連中か、と思った。
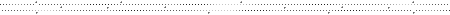
「……なんかラジオから音がしない?」
助手席のルートヴィヒがふと声を出した。運転に集中していたアンナマリアが
「え?」
というと、ルートヴィヒはラジオのボリュームを上げた。しかし、無音である。というか電源がオフになっている。
「どうかしたんですか?」
「いや、なんか、キーンて。電波音が」
ルートヴィヒが首をかしげると、娘二人も首をかしげた。――彼とは違う意味で。
「何にも聞こえませんけど……」
「……なんかの起動音っぽいものもしたんだけど気のせいかな……」
その言葉に、後部座席のコンスタンツェがハードケースを大事そうに抱きしめてそっと言った。なぜか、声をひそめて。
「あのね、このくらいの、高級車だと普通付いてるんじゃない?……、盗難防止追跡用GPS」
「「……」」
「ルーの聞いた音、それかも……」
その言葉に、前の席の二人がため息をついた。
「ばれたね」
「バレたな。よりによって夜に目立つ白い車だし。あとは時間との勝負かねぇ」
ははは、とルートヴィヒが乾いた笑いを響かせた。
アンナマリアはというと、グン、とアクセルを踏み込んだ。覚悟していなかった二人が急な加速で背もたれに体を押し付けられる。
「スピード上げます!」
「上げる前に言おうか!!」
ルートヴィヒが悲鳴のように叫んだ。
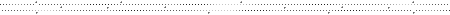
「申し訳ありません。意地でもわたしが車庫までついて行っていれば……」
「弁解はいい、ファービアン。安全運転をしろ」
庭師兼運転手のダドリーの息子ファービアンが恐縮しているのを軽くいさめて、伯爵は黒塗りの車に乗り込んだ。こんなときでも彼は後部座席に座る。
「お客様は?」
「自分の車で行くそうだ。爆走されても困るから、適度な速度で誘導しろ」
「かしこまりました」
屋敷の敷地を出ると、すでに路肩にジークフリートが乗ってきた四輪駆動車が待機していた。運転手同士が目配せして、ファービアンが先行した。
伯爵が助手席で携帯電話を取り出した。
「街のメインストリートから少し外れたところにある、ジャズ・バーの近くだ。……この店は、たしかカクテルが美味かったな」
ファービアンはバックミラーで後続車を確認していたので返事をしなかった。
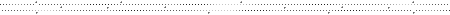
さて先に着いたのはやはりクーペ組のほうであった。アンナマリアが手近な路上パーキングに車を止めると、まっ先に降りたのはルートヴィヒだった。それまで自分の坐っていた席を手前に引いて倒し、コンスタンツェに手を差し出す。ふわりと降り立つ乙女とそれをエスコートする青年の図は、まるで映画のワンシーンのようだった。パーキングメーターの前でアンナマリアがそれに見とれている間に、ルートヴィヒが今度はこちらに来て、ポケットから取り出したコインをメーターに入れた。
「あ」
「いや、このくらいは出すよ」
小銭入れを構えていたアンナマリアは戸惑ったが、ルートヴィヒはスマートにそれを無視してメーターが吐きだしたチケットを受け取り、開けられたままだった助手席のドアのところに戻った。席を戻して、上半身だけ器用に車内に入るとフロントガラスにシール状のチケットを張る。
それから、ルートヴィヒはクリップウォレットを取り出すと、中くらいのお札を取り出しアンナマリアに差し出した。
「さすがに何も頼まないわけにはいかないだろうから。いつ追手が来るかわからないから料理は本格的なのは頼まないでね、あとお酒もダメ」
「わかってます。でも、いいんですか?」
「うん。僕は外にいるから、コニィのことを頼んだよ」
「えっ」
声を上げたのはコンスタンツェだった。ルートヴィヒは笑う。
「僕が行っても仕方ないことだから。それに、“鬼さん”が来たら食い止めなきゃならないしね」
その言葉に、コンスタンツェが口元を引き締めて頷く。それから、抱えていたハードケースを背負った。
「いってらっしゃい。君なら大丈夫。僕の自慢の教え子だもの」
「いってきます」
コンスタンツェがアンナマリアに向き直る。
「行こう!」
アンナマリアが手を差し出すと、躊躇なくコンスタンツェが握った。
走り出す娘たち二人の背中を見送って、ルートヴィヒはスラックスのポケットに手を突っ込み、背筋を伸ばし、夜空に向かって息を吐いた。
淡い照明の店内に入り、アンナマリアとコンスタンツェはどちらからともなく手を放した。立ち尽くすように入口に立つコンスタンツェを促してアンナマリアはテーブル席に着く。
コンスタンツェは席に座る前に床に楽器のハードケースを大事そうに置いた。
店の奥にピアノが置いてある小さなステージがあった。
「生演奏をするお店なんだよ」
「うん、知ってる」
コンスタンツェはじっと誰もいないステージを見つめている。
「いらっしゃい」
そこへやってきたのは、メニューを持った店員だった。彼は意外なほど年若く、高校生ぐらいの少年に見えた。変声期を脱したばかりらしい不安定さの残る低音で、客の二人に言う。
「決まったら呼んでね」
少し生意気そうにも聞こえるが、接客慣れしている笑顔のせいでそれも緩和される。
アンナマリアが「さて」とメニューを見ている間、カウンターの近くに戻る少年をコンスタンツェは見つめていた。カウンターの中には珍しく、中年の女性のバーテンダーがいた。
コンスタンツェの視線に気づいて、アンナマリアもカウンターを振り返る。
「似てるね、親子かな」
たくさんのボトルに淡い照明が反射している。そのせいで、二人が輝いているように見える。親しげに言葉を交わしている様子は、明らかに母と息子のようだった。
「たぶん、ね」
コンスタンツェは短く答えた。
それからアンナマリアが回してきたメニューに目を落とす。
そこへ、ウェイターの少年がやってくる。
「決まった?」
そのウェイターにアンナマリアは尋ねる。
「ジンジャーエールって辛口の方?」
「両方あるよ」
「じゃあ辛いほうで」
少年が伝票に書きとめながら上目づかいで今度はコンスタンツェを見た。
「わたしはシャーリー・テンプル」
「あなたにピッタリだ」
「ありがとう」
伝票から顔を上げそう言った若いウェイターの顔にはちゃめっけがあった。コンスタンツェも笑う。彼が去ってから、アンナマリアが言った。
「私には何も言わないんだ」
「ジンジャーエールじゃ言いにくいわよ」
くすくすとコンスタンツェがまた笑った。アンナマリアもつられて笑う。
だがすぐに、コンスタンツェは緊張したような面持になって、テーブルの上で手を組みじっとそこを見つめ始めた。その空気が気まずくて、アンナマリアは言う。
「何か頼もうか?お腹すいてない?」
「ううん、大丈夫。アンナマリアは?」
「少し空いてるから、ポテトとソーセージでも頼もうかな……」
それからアンナマリアはあたりを見回した。女性のバーテンダーが綺麗なグラスにそれぞれの飲み物を注いでいる。客はぽつぽつといるだけで、混んでいる様子はない。静かすぎることもないし、騒がしいというほどでもない。
「……お父さんらしい人、いないね」
「まだ裏に居るんだよ、きっと」
「ピアニスト、だっけ」
四六時中店内で接客しているわけではないだろう。思い直して、アンナマリアはコンスタンツェが見つめる人のいないステージをあらためて見た。
しばらくしてあのウェイターがジンジャーエールとシャーリー・テンプルを持ってやってきた。アンナマリアが追加注文をする。
コンスタンツェがやや緊張しているように見えてきたので、アンナマリアはちょっと強引に乾杯してみせた。
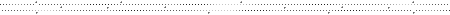
「あそこですね」
「あの店先の金髪の若者はオルガン奏者だろうな」
店の前をいったん通り過ぎ、手近な路上パーキングに向かうと見覚えのあるクーペがあり、伯爵は苦笑した。
「当たりだな」
ファービアンに車を止めさせている間に、伯爵は悠々とルートヴィヒのいる店の前に向かう。
“マグヌス”に気付いたルートヴィヒがこちらを向いた。挨拶代わりに片手をあげかけたところで、あたりに乱暴なブレーキ音が響き渡り、店の前の路肩に四輪駆動車が止まった。
エンジンが止まり、車から降りたのはもちろん黒髪のジークフリートだ。伯爵が立ち止り、ルートヴィヒがそちらを向いた――その時だった。
風を切って一歩でジークフリートがルートヴィヒとの間を詰め、胸ぐらをつかんでそのまま店の外壁へと彼を押し付けた。
ドン、と鈍い音がした。
「コンスタンツェは何処だ?!」
「あたたた、人を誘拐犯みたいに扱わないでよ」
見れば、ルートヴィヒはわずかに地面から浮いている。伯爵はふむ、と言って珍しくポケットに手を突っ込んだ。
「似たようなものだろうが!コンスタンツェは今免疫力が下がってるんだ!」
「ちょっとだけだから……待っててよ。っていうか苦しいし……」
だがジークフリートはルートヴィヒをそのまま揺すぶった。ガン、と鈍い音がして建物の外壁にルートヴィヒの後頭部がぶつかった。金髪の青年がうめく。
「コンスタンツェは何処だ、言え!」
「彼女の邪魔をしないなら言う!」
喉が締め付けられているせいで、掠れた声でルートヴィヒが言う。
「邪魔?なんのことだ」
「お父さんと会いたがってる」
そこに至って、ようやっとジークフリートはルートヴィヒを解放した。げほごほとルートヴィヒが咳き込む。息を整えて、彼はジークフリートと対峙した。
「こそこそ何かをやっているとは思ったが……!」
「ヒトじゃなくなる前に会いたい、って。だから調べた。でも病院を抜け出すとは思ってなかった」
「お前はなんでも認識が甘すぎる!」
ジークフリートがイライラと髪を掻き毟った。ルートヴィヒは困ったように頬をぽりぽりとやる。
「それで?」
「邪魔しないなら教える。邪魔するなら教えない」
「約束はできん」
「じゃあ無理だ」
その言葉に、ジークフリートは呻いて犬歯をむき出しにした。ヴィータの獣じみた威嚇行動だ、久々に見たぞ、と伯爵は思った。シューと、唇の間から爬虫類のような威嚇音がした。
「殺すぞ」
低い、本気の声だった。グルルル、と喉の鳴る音がする。
「殺したら、コニィが泣くよ」
だがルートヴィヒは怯えも見せず、静かに返した。
しばし、無言の対立。
伯爵はそれを眺めるのに飽きて、ため息をついた。
「路地裏でやりたまえ、そこが似合いだ」
「マグヌス」
「営業妨害も甚だしいな。わたしはこの店に入る。ファービアン」
「はい」
伯爵は振り返らずに、背後に控えていた従僕を呼んだ。
「ここでできる話し合いに収まらず、なおかつ路地裏にでも移動しないようならば、始末しろ」
「かしこまりました」
ぐっとファービアンが左腕を持ち上げた。筋肉がさざめいて、ぶわりと空気が動いた。次の瞬間には左腕は一回りも大きくなって、灰色の剛毛におおわれていた。爪は黄金色のカギ爪になっている。彼の父ダドリーもそうであろように、彼もまた人狼だった。
炯炯と光り出す爪と揃いの黄金色の瞳に、年若い吸血鬼たちは身を固くした。
一部の吸血鬼は、人狼を不得手とするのだ。
ファービアンが一歩二人に近づく。二人はさすがに後ずさった。ファービアンはため息をついて、左腕を元に戻した。
「それでは、仲良くやりたまえ」
伯爵は楽しげにバーのドアを開けた。
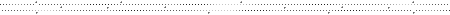
「――お嬢様がた、ここは空いているかね?」
不意に降ってきた心地よいバリトンに、アンナマリアとコンスタンツェはびっくりして振り返った。
「伯爵、脅かさないでください」
アンナマリアが言うと、コンスタンツェがきょろきょろした。
「あの……」
「君の連れなら表で話し合い中だ」
かたん、と伯爵は自ら空いていた椅子を引いて腰掛けた。そこへ、あの少年ウェイターがやってくる。
「ブラック・ベルベット」
彼が何か言う前に、伯爵は注文した。ウェイターはコンスタンツェになぜか視線を投げて肩をすくめた。コンスタンツェが苦笑すると、少年はカウンターの女性バーテンダーのところへ戻って行った。
その間に、伯爵はテーブルの上にあった皿からフライドポテトをひょいとつまんで口に放り込んでいた。その姿に、アンナマリアがぽかんとする。
「……ああ、フォークがあったのか」
伯爵は遅まきながら気づいて、紙ナプキンで手を拭いた。
「……それもそうなんですけど……」
――吸血鬼もポテト食べるんだ。というか、伯爵も手でつまんでモノ食べるんだ……。
アンナマリアの抱く吸血鬼像が幾度目かの崩壊を迎えたことなど、伯爵はちっとも気にしていない――あるいは気付いていない――雰囲気で、彼はフォークにソーセージを刺した。
そして次の瞬間にはパリッとジューシーな音を立てて伯爵はソーセージを食していた。いつもならナイフを使う。アンナマリアはなんだかうなだれたくなってうなだれた。
「どうした?支払いのことなら心配するな」
「いえ、あの……はい」
アンナマリアはもう何も言わなかった。
そこへ、ウェイターの少年がブラック・ベルベットを運んできた。伯爵はテーブルにおかれたそれを黙って口元に運ぶ。シャンパンとスタウトの底から上がる気泡は潰れずに細やかな白い泡へと溶けて行く。黒と白の織りなす上品な色合いは伯爵に似合いの色だった。伯爵が酒類ではワインとシャンパン以外を口にしている所をあまり見たことがないアンナマリアだが、心の奥底で
――ちょっとイメージが回復したわ。
と胸をなでおろした。これで七色に輝くカクテルなど頼んでいたら、彼女の中の“吸血鬼像”は木端微塵だったに違いない。いくら伯爵があらゆる意味で“規格外”だったとしても。そんなアンナマリアの物思いの間に、伯爵はコンスタンツェに話しかけていた。
「シャーリー・テンプルか。なるほど」
「あ……ジークがどうしてもわたしをバーに連れて行かなくちゃいけなかったとき、決まって飲ませてくれたんです」
「その頃から昼に寝て、夜に起きていたのかな?」
「はい。でも時々、元気だったときは昼間に出歩いたりしていました。普通のヴィータと違って、あの頃は紫外線アレルギーの症状がなかったんです。昼も夜も、楽しいことがいっぱい。昼にはアニメを見たり、公園で同じ歳くらいの子とブランコに乗ったり。夜はジーク……おじさんが勉強を見てくれて、ルートヴィヒが音楽を教えてくれました」
「“学校”には?ヒトのでも、ヴィータのでも」
「月に何度か、ヴィータの方に。だけどあんまり、わたし友達がいなくて」
自嘲するように笑ったコンスタンツェの表情にアンナマリアはふと考え込んでしまった。彼女の生まれのせいだろう。
だが伯爵は、アンナマリアのように考え込んだふうもなく、ブラック・ベルベットを傾けながら言った。
「友達など、親友と呼べるのがひとりふたりいるだけでいいのだよ」
「……それだったら、います」
自らへの嘲りが消えたコンスタンツェの笑みに、伯爵は目を細めて見せた。アンナマリアもなんだかほっとする。
「それにしても、逃亡の終着点がジャズ・バーとは」
伯爵がやや息を大げさに吐き出しつつ言った。コンスタンツェが彼を見る。
「まだ、目的は果たせないかね?」
「はい、あともう少し……時間をください」
「それを乞うべきは、わたしにじゃないね。表で話し合っている君の保護者にすべきだった」
その言葉に、コンスタンツェが俯いて「ごめんなさい」と言った。伯爵はまるでたわいない悪戯をした孫を見つけた祖父のような顔をした。
「目的を果たしたら、きちんと本人に言いなさい」
|